たまにはロマンチックな気分になるのも良いと思います。そんな朝です。
そして私は庄野英二の『星の牧場』を思い出しました。内容はつぎのようなものでした。
復員兵イシザワ・モミイチはインドネシアで戦ってきたが、愛馬ツキスミを失い、記憶を失っていたのです。彼が山中の牧場に辿りついて、音楽を演奏するジプシーたちと出会い、そこで心の癒しを得るのです。空には満天の星が輝いていました。・・・そして幻想的な話が続きます。
この牧場の上の満天の星空という光景が心に焼き付いてしまったのです。
それ以来、牧場のそばの雑木林の中に小屋を建てるのが夢になりました。
そんな折、1973年の頃でしたか、新聞に「別荘を建てる山林を格安で売ります」という広告を見ました。
小学生だった息子と現地に行ってみるとその山林は牧場から白樺が混じっている雑木林を通リ抜け、その先の崖を下りた谷間のような土地です。
谷間に大きな松の木や雑木が生えた暗い林でした。そしてその松林の西側には花崗岩が白く輝く甲斐駒岳が高々と聳えていたのです。
暗い、じめじめした谷のような場所なので躊躇していたら、不動屋さんが、「この一画を買うと庭の中をヤマメのいる清流のある別荘が建てられますよ」と真剣に薦めます。
「ヤマメの棲む清流」に負けて買う決心をしました。何本も樹を切って貰い、小さな鉄筋コンクリートの小屋を建てました。
さて「星の牧場」ですが、それは小屋の前の崖を登り、白樺の雑木林を通って行くと広い牧草地に出ます。
乳牛を30頭ほど飼っている牧場です。石原さんという一家が牛の世話をしています。
早速、挨拶に伺い、すぐに親しくなりました。気持ちのよい家族でした。祖父、祖母、中年の夫婦に小学生くらいの息子が2人いました。私どもも子供が2人いたので乳牛をよく見に行きました。
山林の小屋に泊まっていると、石原さん一家の祖母が孫の小学生とともに一升瓶に入った牛乳を何度も届けてくれました。
その上、春には筍を掘ってくれるのです。正月には赤飯やなまこ餅もくれるのです。
夏の夜にはその牧草地にあがって天の川を見上げました。周囲が暗いので星々が鮮明に見えるのです。
北西の方角には八ヶ岳が見え、大泉村らしい集落の家々の灯が小さくチラチラ見えます。
それはまさしく庄野英二の『星の牧場』のなかに出て来る光景と同じようだったのです。
そこは星の美しく見える高原なのです。
私の山林の中の小屋が完成したのは1974年です。完成以来、茫々50年です。
牧場をしていた石原さんも乳牛を飼うのを止め、生活に便利な集落に立派な家を作り悠々と暮らしています。お世話になったので時々寄りお礼をしました。
私の山林の小屋のまわりの風景をお送り致します。甲斐駒岳や山林の風景は50年前と同じです。
1番目の写真は私の小屋の西に聳える甲斐駒岳です。
2番目の写真は石原さんの牧場の東にある真原の風景です。
3番目の写真は山林の中の小さな、小さな小屋です。
最近はイノシシや猿や鹿が急に多くなりよく見かけるようになりました。
小屋の庭を流れる小川にはヤマメが棲んでいました。
この山小屋のお陰である小説家とも親もくなりました。
小屋を建てて数年した時、山林の中でもの思いにふけりながら散歩をしている若い男の人に会いました。人気の無い山道で会ったので少し話をしました。
彼は小説を馬場駿という筆名で沢山書いていた人でした。
彼は兄の山荘に一緒に住んでいるから寄ってみないかと言います。山荘は約1000坪ほどある山林の中に建っていました。広い山荘に兄弟が2人きりで暮らしています。私は馬場駿と彼の兄と親しくなりました。
ある時、兄弟は石造りの暖炉が完成したから一緒にビールを飲もうと誘ってくれたのです。
行ってみると暖炉は自然石を上手に組み、間をコンクリで固めた立派な出来でした。
薪を焚きながらよく冷えたビールを男3人が飲むのです。赤く揺れる炎と香しい煙が男たちを楽しくさせます。
4番目の写真は馬場駿と彼の兄の山荘の庭に咲いていたカタクリの花です。私が撮った写真です。

5番目の写真はその山荘の庭にあるコブシの花です。写真は馬場駿の兄さんが撮ったもので、ブログ「北杜市・自然の中で」、http://sizen068.blog95.fc2.com/ から転載させて頂きました。
このように私は山林の中に小屋を建てたおかげでいろいろな人々と親しくなりました。これらの人々も年々歳歳しだいに年老いていきます。
私自身も年老いて山林の小屋へは行けなくなりました。昨年秋と今年の一月
息子夫婦と孫二人が私どもを小屋へ久しぶりに連れて行ってくれました。
小屋の周囲の自然の風景だけは変わりません。しかし知り合った人々はみんなみんな消えてしまいました。年年歳歳、自然は変わりませんが、懐かしい人々は変わるのです。
今日は庄野英二の『星の牧場』をご紹介し、私の山林の中の小屋にまつわる思い出を書きました。そこでまじわった人々を懐かしく思い出します。みんなみんな消えてしまった人々です。
それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)
=========================================================
庄野英二の『星の牧場』
高原の牧場で働く青年モミイチは、戦争のなかで受けたショックとマラリアの熱で記憶を失っている。だが、1兵隊のときの愛馬ツキスミのことだけは忘れられず、今もその麻の音が時折耳に聞こえてきた。ある日、麻の音を追いかけて山奥深く入り込んだモミイチは、初めて踏み込んた美しい花畑でクラリネットを吹く男に出逢う。彼のテントで一夜を明かし、聞いたのは森の中で暮らす不思議なジプシーたちのことであった。各々が得意の仕事を持ち自由な生活をおくりながら、時々一緒になって音楽を演奏して楽しむという。ツキスミのことを心配してくれるジプシーたちに心惹かれたモミイチは感激し、牧場に戻ってきても彼らのことばかり考えていた。美しい音色を奏でる鈴をたくさん作った彼は、再び山奥深く入り込みジプシーたちを捜し求める。そして、オカイコを踊らせるバイオリン弾きの美少女、ビオラを奏でるそり兄をはじめ、たくさんのジプシーたちと出逢い素晴らしい歓待を受けた。彼らの「次の満月の夜、森の奥で開かれるジプシーたちの・バザールで再会しよう、それまでにツキスミのことを尋ねておこう」という言葉を胸に、モミイチは牧場に戻った。だが、彼を心配した牧場主夫婦、許嫁のゆきはこれ以上自由にしておけぬと監視する。満月の夜、牧場を抜け出せぬモミイチは泣くのだった。夏も過ぎ去ろうという頃、再び山に出かけた彼は歩き回るが、かつての場所にジプシーたちの姿は見えなかった。捜し疲れて眠り、眼を覚ますと流れ星の降る中をツキスミが駆けめぐっている。夜空ではジプシーたちのオーケストラがシンフォニーを響かせている。歓喜にあふれたモミイチはツキスミの背に乗って、夜空で待ち受けるジプシーたちの許へと昇っていくのだった。(終わり)












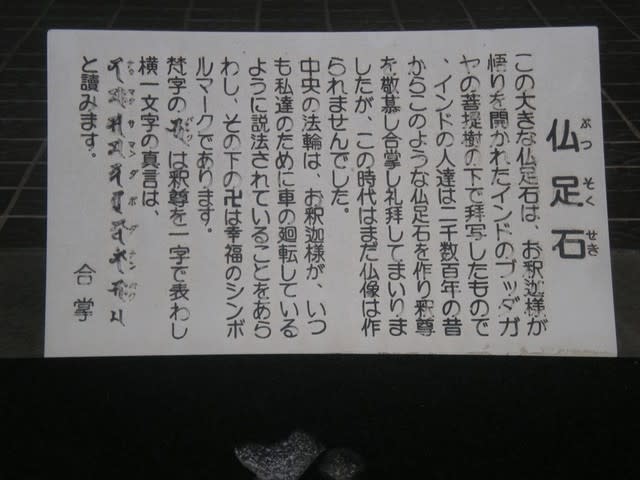
 一年中水が枯れない小川です。
一年中水が枯れない小川です。


















