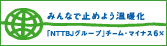| 女の一生モーパッサン,新庄 嘉章新潮社このアイテムの詳細を見る |
【一口紹介】
◆出版社からの内容紹介◆
修道院で教育を受けた清純な貴族の娘ジャンヌは、幸福と希望に胸を躍らせて結婚生活に入る。
しかし彼女の一生は、夫の獣性に踏みにじられ、裏切られ、さらに最愛の息子にまで裏切られる悲惨な苦闘の道のりであった。
希望と絶望が交錯し、夢がひとつずつ破れてゆく女の一生を描き、暗い孤独感と悲観主義の人生観がにじみ出ているフランス・リアリズム文学の傑作である。
◆著者◆
(1850-1893)フランス生れ。母親の実兄の親友であるフローベールに師事し、創作の指導を受ける。
1880年普仏戦争を扱った中編『脂肪の塊』で作家としての地位を確立、以後10年間で『女の一生』等の長編を6作と『テリエ館』「月光」「オルラ」等の中短編を300余次々に発表した。1892年自殺を図り、翌年パリの精神病院で生涯を閉じた。
【読んだ理由】
「読んでおきたい世界の名著」(三浦朱門編)を読んで。
【印象に残った一行】
『さて二人はじっと見つめあった。鋭くて、相手の心を見ぬくような、動かぬ目で、二つの魂がそこで溶け合うことを信じている目で、見つめあった。二人は互いの目の中に、目のうしろに、存在の計り知れぬこの未知の部分なかに、相手をさがし求めた。無言の執拗な問いで、たがいに探り合った。自分たちはおたがいに相手にとってどうなるのであろう?いっしょに始めたこの生活はいったいどうなるのであろう?結婚というこの断ちがたい、ながい差向いての対談のうちに、二人はおたがいに、なんと多くの喜びを、幸福を、あるいはそれとも幻滅を準備しているのであろう?すると、二人とも、これまでに会ったことのない人間同士であるかのように思われてくるのだった』
【コメント】
没落の一途を辿るあまりにも悲しい女の一生が、人間の持つ良心への最後の信頼の崩壊と共に描かれている。