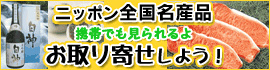【まくら】
吉原遊女の墓があることで知られている寺に、三ノ輪の浄閑寺がある。
ここには遊女と遊廓関係者約二万五千人が葬られている。
安政大地震で亡くなった遊女と遊廓関係者がもっとも多い。
災害で亡くなったために合葬されており、そこから「投げ込み寺」と呼ばれている。
しかし遊女を軽く扱ったのではないし、遊女でない従業員も一緒に葬られているのだ。
浄閑寺、西方寺、正憶院など吉原周辺の特定の寺には、心中した遊女や引き取り手のいない下級遊女たちもまた葬られた。
しかし災害や心中のようなケースでない限り、遊女は通常三年半の年季が終わると結婚したり商売をするので、個々の墓に入る。
また年季途中で病死した場合は、親や兄弟に引き取られて家の墓に入るか、または抱え主の旦那寺に入る。
抱え主の寺であれば、複数の遊女の墓が並んでいても不思議はない。
出典:TBS落語研究会
【あらすじ】
吉原の喜瀬川花魁(おいらん)。今日も今日とて、地方人の杢兵衛(もくべえ)大尽が
せっせと通って来るので、嫌で嫌でたまらない。
あの顔を見ただけでむしずが走って熱が出てくるぐらいだが、そこは商売、なんとか顔だけは、と、廓(くるわ)の若い衆に言われても嫌なものは嫌。
「いま病気だと、ごまかして追い返しとくれ」
と頼むが、大尽、いっこうにひるまず、
「病気なら見舞いに行ってやんべえ」と言いだす始末だ。
なにしろ、ばかな惚(ほ)れようで、自分が嫌われているのをまったく気づかないから始末に負えない。で、めんどうくさくなった若い衆、
「実は花魁は先月の今日、お亡くなりになりました」
と、言ってしまった。
こうなれば、毒食らわば皿までで、
「花魁が息を引き取る時に
『喜助どん、わちきはこのまま死んでもいいが、息のあるうちに一目、杢兵衛大尽に会いたいよ』と、絹を裂くような声でおっしゃって」
と、口から出まかせを並べたものだから、杢兵衛は涙にむせび、
「どうしても喜瀬川の墓参りに行く」と言って、きかない。
「それで、墓はどさだ」
「えっ? 寺はその、えーと」
困った若い衆、喜瀬川に相談すると「かまやしないから、山谷あたりのどこかの寺に引っ張り込んで、どの墓でもいいから、喜瀬川花魁の墓でございます
と言やあ、田舎者だからわかりゃしない」と意に介さないので、しかたなく大尽を案内して、山谷のあたりにやってくる。
きょろきょろあたりを見回して、その寺にしようかと考えていると大尽、
「宗旨は何だね」
「へえ、その、禅寺宗で」
「禅寺宗ちゅうのがあるか」
中に入ると、墓がずらりと並んでいる。いいかげんに一つ選んで
「へえ、この墓です」
杢兵衛大尽、涙ながらに線香をあげ
「もうおらあ生涯やもめで暮らすだから、どうぞ浮かんでくんろ、ナムアミダブツ」
と、ノロケながら念仏を唱え、ひょいと戒名を見ると「養空食傷信士、天保八年酉年」
「ばか野郎、違うでねえか」
「へえ、あいすみません。こちらで」
次の墓には、「天垂童子、安政二年卯年」とある。
「こりゃ、子供の墓じゃねえだか。いってえ本当の墓はどれだ」
「へえ、よろしいのを一つ、お見立て願います」
出典:落語のあらすじ
【オチ・サゲ】
間抜落ち(あまりにも間抜けな事がオチになるもの)
【噺の中の川柳・譬(たとえ)】
『女郎買い振られて帰る果報者』
『傾城にかわいがられて運の尽き』
【語句豆辞典】
【お見立て】ご指名の意。張り見世で客が、格子内にズラリと居並んだおいらんを吟味し、敵娼(あいかた)を選ぶこと
【牛太郎】別名妓夫(ぎゅう)。若い衆。客引き。遊郭の若い衆(使用人)小見世では客引きなどをする見世番。
【中どん】遊びに来た旦那衆(客)を花魁に引き合わせるのが役目。この噺で花魁(おいらん)と杢兵衛の仲立ちをして大活躍をしている。
【張り見世】見世と道を格子で仕切った部屋、そこで花魁と呼ばれる遊女が位の順に坐っているところ。
【この噺を得意とした落語家】
・三代目 古今亭志ん朝
・五代目 古今亭志ん生
【落語豆知識】
【お店噺(たなばなし)】商家が舞台の噺。



吉原遊女の墓があることで知られている寺に、三ノ輪の浄閑寺がある。
ここには遊女と遊廓関係者約二万五千人が葬られている。
安政大地震で亡くなった遊女と遊廓関係者がもっとも多い。
災害で亡くなったために合葬されており、そこから「投げ込み寺」と呼ばれている。
しかし遊女を軽く扱ったのではないし、遊女でない従業員も一緒に葬られているのだ。
浄閑寺、西方寺、正憶院など吉原周辺の特定の寺には、心中した遊女や引き取り手のいない下級遊女たちもまた葬られた。
しかし災害や心中のようなケースでない限り、遊女は通常三年半の年季が終わると結婚したり商売をするので、個々の墓に入る。
また年季途中で病死した場合は、親や兄弟に引き取られて家の墓に入るか、または抱え主の旦那寺に入る。
抱え主の寺であれば、複数の遊女の墓が並んでいても不思議はない。
出典:TBS落語研究会
【あらすじ】
吉原の喜瀬川花魁(おいらん)。今日も今日とて、地方人の杢兵衛(もくべえ)大尽が
せっせと通って来るので、嫌で嫌でたまらない。
あの顔を見ただけでむしずが走って熱が出てくるぐらいだが、そこは商売、なんとか顔だけは、と、廓(くるわ)の若い衆に言われても嫌なものは嫌。
「いま病気だと、ごまかして追い返しとくれ」
と頼むが、大尽、いっこうにひるまず、
「病気なら見舞いに行ってやんべえ」と言いだす始末だ。
なにしろ、ばかな惚(ほ)れようで、自分が嫌われているのをまったく気づかないから始末に負えない。で、めんどうくさくなった若い衆、
「実は花魁は先月の今日、お亡くなりになりました」
と、言ってしまった。
こうなれば、毒食らわば皿までで、
「花魁が息を引き取る時に
『喜助どん、わちきはこのまま死んでもいいが、息のあるうちに一目、杢兵衛大尽に会いたいよ』と、絹を裂くような声でおっしゃって」
と、口から出まかせを並べたものだから、杢兵衛は涙にむせび、
「どうしても喜瀬川の墓参りに行く」と言って、きかない。
「それで、墓はどさだ」
「えっ? 寺はその、えーと」
困った若い衆、喜瀬川に相談すると「かまやしないから、山谷あたりのどこかの寺に引っ張り込んで、どの墓でもいいから、喜瀬川花魁の墓でございます
と言やあ、田舎者だからわかりゃしない」と意に介さないので、しかたなく大尽を案内して、山谷のあたりにやってくる。
きょろきょろあたりを見回して、その寺にしようかと考えていると大尽、
「宗旨は何だね」
「へえ、その、禅寺宗で」
「禅寺宗ちゅうのがあるか」
中に入ると、墓がずらりと並んでいる。いいかげんに一つ選んで
「へえ、この墓です」
杢兵衛大尽、涙ながらに線香をあげ
「もうおらあ生涯やもめで暮らすだから、どうぞ浮かんでくんろ、ナムアミダブツ」
と、ノロケながら念仏を唱え、ひょいと戒名を見ると「養空食傷信士、天保八年酉年」
「ばか野郎、違うでねえか」
「へえ、あいすみません。こちらで」
次の墓には、「天垂童子、安政二年卯年」とある。
「こりゃ、子供の墓じゃねえだか。いってえ本当の墓はどれだ」
「へえ、よろしいのを一つ、お見立て願います」
出典:落語のあらすじ
【オチ・サゲ】
間抜落ち(あまりにも間抜けな事がオチになるもの)
【噺の中の川柳・譬(たとえ)】
『女郎買い振られて帰る果報者』
『傾城にかわいがられて運の尽き』
【語句豆辞典】
【お見立て】ご指名の意。張り見世で客が、格子内にズラリと居並んだおいらんを吟味し、敵娼(あいかた)を選ぶこと
【牛太郎】別名妓夫(ぎゅう)。若い衆。客引き。遊郭の若い衆(使用人)小見世では客引きなどをする見世番。
【中どん】遊びに来た旦那衆(客)を花魁に引き合わせるのが役目。この噺で花魁(おいらん)と杢兵衛の仲立ちをして大活躍をしている。
【張り見世】見世と道を格子で仕切った部屋、そこで花魁と呼ばれる遊女が位の順に坐っているところ。
【この噺を得意とした落語家】
・三代目 古今亭志ん朝
・五代目 古今亭志ん生
【落語豆知識】
【お店噺(たなばなし)】商家が舞台の噺。