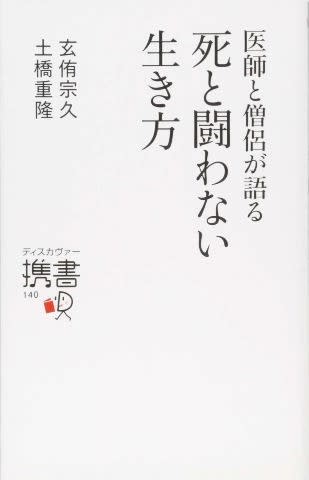目次
第1章 排除するだけでは病気は治らない(ガンになる臓器と性格や生き方は対応している;
本物のガンでも治ってしまう人はいる;ガンは治療どころか診断すらしないほうがいい? ほか)
第2章 死と闘わない生き方とは(亡くなった人の生き方を聞く;病気を治す「薬師如来」と身心を癒す「阿弥陀如来」;
日本人にとって死は「無くなること」ではなく「どこかへ行くこと」だった ほか)
第3章 ガンになる「性格」「生き方」がある(ガンは「心の病気」;左乳ガンと右乳ガンの患者は生き方や性格がまったく違う;
メンタルなストレスとフィジカルなストレス ほか)
第4章 医療の仕組みがこわれる時(「山分けシステム:の中にいる医者は患者のことなど考えていない;
手術の達成感よりも大きかった患者さんからの言葉;医療はもともとお布施で成り立っていた ほか)
第5章 「死後」と向き合う(輪廻の思想は日本には入ってこなかった「お地蔵さん」は日本流にアレンジされた仏様;
患者さんが死ぬ瞬間、何かが「抜けた」感じがある ほか)
第6章 ガンは「概念」の病気(ガンは考えすぎることで起こる病気;理性は生命の働きを弱めてしまう;
一本の植物になって風になびいてみると ほか)
第7章 「不二」の思想と出会う(物事を二つに分け、片方を否定して片方を肯定するのは良くない;
「病気は悪いものだ」という考え方をやめれば世界が変わる;てず変化していくことを愛する ほか)
著者等紹介
玄侑宗久[ゲンユウソウキュウ]
1956年、福島県三春町生まれ。慶應義塾大学中国文学科卒。さまざまな仕事を経て、京都天龍寺専門道場に入門。2001年『中陰の花』で第125回芥川賞を受賞。2007年、柳澤桂子氏との往復書簡『般若心経 いのちの対話』で第68回文藝春秋読者賞、東日本大震災の被災地を描いた短編集『光の山』で平成25年度芸術選奨本賞を受賞。2008年より福聚寺第35世住職
土橋重隆[ツチハシシゲタカ]
外科医、医学博士。1952年、和歌山県生まれ。和歌山県立医科大学卒業。西日本で最初の食道静脈瘤内視鏡的栓塞療法、和歌山県で最初の腹腔鏡下胆嚢摘出手術を施行。帯津三敬病院にて終末期医療を経験、現在は三多摩医療生協・国分寺診療所で外来診療を行なっている。全国各地で講演活動を展開(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


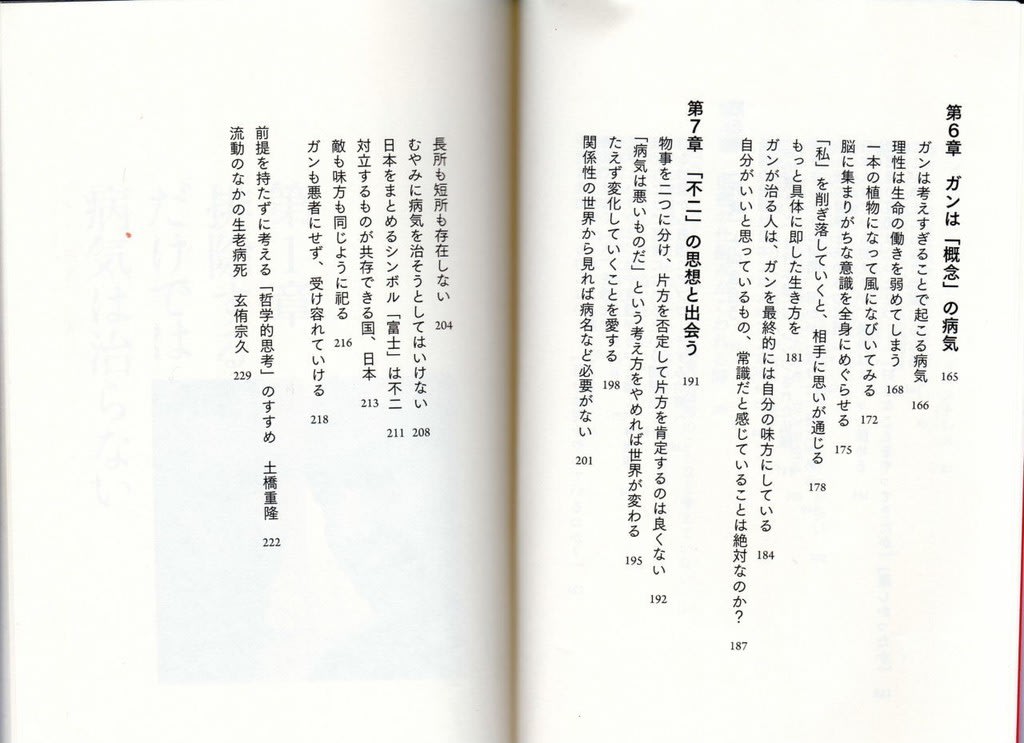
トップクラスの技術を持つ外科医としてガンの手術現場で実績を上げ続けた医者がある時疑問を持つ。
手術は成功しているがその患者は人間として幸せになっているのか?と。
国と厚労省と医者集団と薬品業界は患者という人間を見ずに強力な山分けシステムを作っているだけではないのか?
そして臨済宗の僧侶は檀家のガンによる死を送るたびにそれぞれのガンとその檀家の生き方に共通性を感じてきた。
沢山の生死の現場を踏んできた医者と僧侶の対話。こんな思索をする医者も日本にはいるんだと目からウロコが落ちる本だった。
探したがこの本の書評も大手メディアにはなかった。テレビや新聞の広告の大スポンサーである医薬品業界の山分けシステムを
はっきり口にするこういう本は無視されるのだろう。