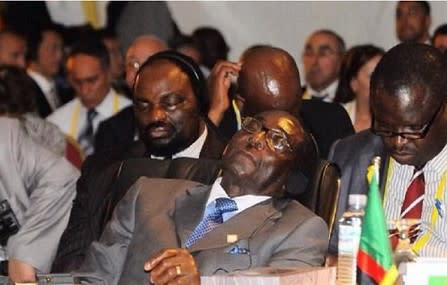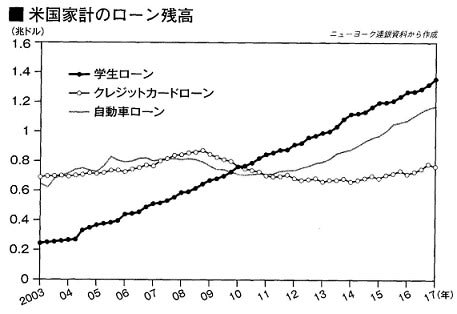(「トルコは分断させない」と支持者に訴えるエルドアン大統領【6月23日 TRT】 大統領の目には支持者だけが国民として映っているようにも・・・)
【“分断”を招いているのは・・・】
トルコ政府系メディアは、先月に行われたエルドアン大統領の演説を以下のように報じています。
****エルドアン大統領 「トルコは分断させない」****
レジェプ・ターイプ・エルドアン大統領は、誰かにトルコを分断させはしないと述べた。
エルドアン大統領は、シャンルウルファ県ジェイランプナル市で出迎えてくれた人々に演説し、
「我々はこの国民を、アラブ人を、クルド人を愛している。我々は1つの国民である。トルコ人、クルド人、ラズ人、ボシュニャク人、アラブ人と共に8000万人の1つの国民である。79万平方メートルのこの領土は我々の祖国である。この地を誰にも分断させたことはないし、これからもさせない。ガバルならガバル、ジュディならジュディ、テンドゥレクならテンドゥレクなどどこにでも我々は参上する。トルコ共和国以外の国家は認めない。」と述べた。
エルドアン大統領は、シャンルウルファ県でシリア人に示されているもてなしの心に対しても感謝した。
エルドアン大統領はまた、アクチャカレでも演説し、
「シリア北部でテロ組織PYDとYPGがあがいている。テロ組織と共に誰がいようと、背後に誰がいようと、トルコ共和国は軍と共にあらゆる機会を駆使してシリア北部に国家が樹立されることを決して容認しない。」と述べた。【6月23日 TRT】
*********************
上記演説で出てくるガバル、ジュディ、テンドゥレクという地名は、クルド系反政府武装勢力PKKの拠点としてトルコ軍が攻撃を行ったところのようです。
「トルコは分断させない」「我々は1つの国民である」・・・・まっとうな発言ではありますが、実際のところ、エルドアン大統領によるギュレン支持者、クルド系の反政府勢力及び野党、更には政府に批判的なジャーナリスト等に対する容赦ない弾圧で、まさにトルコ国内が“分断”状態に陥っていることは、これまでも取り上げてきたところです。
従来から強権的姿勢については批判がありましたが、特に、クーデター未遂事件以降は、支持者以外は自分を狙う“敵”に見えるようです。“こんな人たち”の存在が許せない・・・ようにも。
昨年11月にクルド系有力野党の国民民主主義党(HDP)の共同党首、デミルタシュ氏とユクセクダー氏ら同党国会議員11人を拘束したのに続き、12月には更に大規模な粛清を実施しています。同じクルド系のPKKとの関係を疑ったものと思われます。
****トルコ、クルド系野党の118人拘束 PKKと関連か=国営通信****
トルコの警察当局は、少数派民族クルド人の武装組織「クルド労働者党(PKK)」との関連が疑われるとして、クルド系有力野党の国民民主主義党(HDP)の幹部ら118人を拘束した。国営のアナドル通信が12日、伝えた。
イスタンブールのサッカー場の近くで起きた、38人が死亡し155人が負傷した2回の爆弾攻撃に対し、PKKの分派とされる組織が11日に犯行声明を出したことを受けて、当局が全国規模の一斉捜査を実施した。
同通信によると、南部アダナで夜明け頃、装甲車両やヘリコプターの支援を受けた警官約500人が捜査を開始、HDPの幹部25人を拘束した。
イスタンブールや首都アンカラでは、地元幹部を含む20人と17人がそれぞれ拘束されたほか、南部メルシンで51人、北西部マニサ県で5人が拘束されたという。
議会の第2野党であるHDPの党首らは、PKKと関連した疑いですでに収監されている。【2016年12月12日 ロイター】
******************
【最大野党党首の抗議行進がイスタンブールへ】
エルドアン政権の攻撃は最大野党・共和人民党(CHP)にも向かっています。
こうした政権による国内を“分断”する大規模粛清が続く中で、CHP党首クルチダルオール氏が首都アンカラから最大都市イスタンブールへと歩く抗議のデモ行進を行っており、エルドアン大統領の神経を逆撫でしているようです。
抗議行進のきっかけは、CHPの議員が、トルコ情報当局に関する情報をメディアに漏らしたとしてスパイ容疑で逮捕され、禁錮25年の判決を受けたことです。
****トルコ大統領、弾圧抗議の野党行進に苛立ち *****
反政権勢力への大規模な弾圧を続けるトルコのエルドアン大統領が最大野党・共和人民党(CHP)が始めたデモ行進にいら立ちを募らせている。
同僚議員へのスパイ罪での実刑判決に抗議するため、首都アンカラから最大都市イスタンブールへと歩くクルチダルオールCHP党首を「嘘つき」など激しい表現で非難。行進が大規模な反政府運動へと発展することを懸念しているもようだ。
「政府が裁判所に指図していることを証明すれば辞任するのか」。20日、アンカラ郊外の屋外で同僚議員や支持者を前に演説したクルチダルオール氏はエルドアン政権が司法を影響下に置いていると批判した。
エルドアン氏は同日夜の夕食会で「(クルチダルオール氏は)嘘を作り出す機械だ」と反撃した。別の機会には「司法の呼び出しを受けても驚くな」などと脅迫じみた発言も飛び出していた。
68歳のクルチダルオール氏が夏場に400キロメートル以上の行進を開始したのは15日。政党の旗は用いず、白いシャツ姿で「正義」と書かれたプラカードを掲げる。多い日には数千人の支持者が加わり、呼応したデモ行進が別の都市でも始まった。
トルコは7月15日、昨夏に軍の一部が起こしたクーデター未遂事件から1年を迎える。エルドアン政権は事件直後に発令した非常事態宣言を維持し、約15万人の公務員や軍人らを解雇・停職した。1万6千人の裁判官や判事のうち4人に1人が職を追われた。恣意的な捜査や判決が横行しているとの批判が根強い。
クーデター未遂事件はエルドアン氏の呼び掛けに応じた多数の市民が街頭に繰り出したことで早期の制圧につながった。しかし政権側は「正義は路上では追求できない」(ユルドゥルム首相)などと野党の抗議には取り合っていない。
エルドアン氏は過去の総選挙や大統領選で勝利を重ね、大統領権限集中の改憲の是非を問う4月の国民投票も僅差で承認に持ち込んだ。これらの勝利を盾に強権統治を正当化、国民の分断が深まっている。
2013年にはイスタンブール中心部の再開発問題をきっかけに全国的な反政府運動が発生した。エルドアン氏はデモ隊の強制排除で乗り切ったが、政権基盤を脅かされた苦い記憶がある。今回のデモ行進が同様の事態につながる可能性を懸念しているもようだ。【6月22日 日経】
*******************
クルチダルオール氏の行進に対し、政権側は「テロリストと共闘している」と激しく非難しています。
****「正義の行進」で政権に抗議=野党党首、徒歩で450キロ―トルコ****
クーデター未遂事件から間もなく1年を迎えるトルコで、強権姿勢を強めるエルドアン政権に抗議するため、最大野党の中道左派・共和人民党(CHP)の党首らが、首都アンカラから最大都市イスタンブールまで歩く「正義の行進」を行っている。
行進は9日に終わる予定だが、政権は「テロリストと共闘している」と反発、両者の激しい衝突を招く可能性もある。(中略)
同党支持者以外にも共鳴の輪が広がり、ロイター通信によれば、参加者は7日時点で約5万人に膨らんだ。最終日の9日には、イスタンブールの刑務所の外で大規模集会が行われる予定だ。
昨年7月15日に起きたクーデター未遂事件後、非常事態宣言下で約5万人が逮捕されたが、CHP議員の逮捕は今回が初めてだった。クルチダルオール党首は「国会の全権力はエルドアン氏に移譲された。トルコは民主主義を失いつつある」と述べ、行き過ぎた権力集中に警鐘を鳴らした。
しかし、エルドアン大統領は「テロリストやその支持者を守るために抗議を始めたのならば、目的が正義だと説得することはできない」と批判。ユルドゥルム首相も「街頭で正義は見つからない。やめるべきだ」と警告している。【7月8日 時事】
*********************
【「無人ビラ撒きプリンター」も】
エルドアン政権への抗議は「大統領侮辱罪」での逮捕につながることも考えられますので、抗議活動のなかには奇抜なものもあるようです。
****トルコの反政府活動家、苦肉の策の「無人ビラ撒きプリンター」****
<エルドアン大統領の強権体質に抗議するビラ捲きで、活動家がまんまと逃げおおせた仕掛け>
トルコのイスタンブール警察は現在、あるドイツ人活動家を捜索している。ホテルの一室の窓から、レジェップ・タイップ・エルドアン大統領に対する抗議活動を呼びかけるビラを撒いた容疑だ。部屋からは、ビラを印刷したプリンターが発見されている。
ドイツのウェブサイト「Bento」によると、そのビラには、「仲間が殺されたり、投獄されたりするのを許すような、意志のない追随者になるな」と書かれていたという。また、「力を合わせれば、我々はどんな体制よりも強くなれる。独裁者に死を!」とも書かれていたようだ。
ビラが撒かれたのは2017年7月1日の朝のことで、ホテルの従業員がすぐ警察に通報した。
イスタンブールのタクシム地区にあるそのホテルの一室は、26歳のドイツ人セバスティアン・エンデンの名前で予約されていた。
「センター・フォー・ポリティカル・ビューティー」(ZPS)に所属するあるドイツ人活動家がBentoに語ったところによると、今回の行動は同組織によるものであるようだ。ZPSは、政治的積極行動主義に基づく抗議行動を展開しており、過去にも「独裁政権」に反対してビラを配布するキャンペーンを呼びかけている。
エルドアンは最近、トルコ野党と欧州連合(EU)加盟国から激しい批判を浴びている。2016年7月に起きた「軍事クーデター」失敗の後、急速に独裁色を強めつつあるからだ。ない
警察は、何百枚も通りにばらまかれたビラの出所が、遠隔操作されたプリンターであることを突き止めたという。トルコの日刊紙デイリー・サバーによると、印刷機はホテルの部屋の窓際に置かれ、印刷されたビラが通りに撒かれる仕掛けになっていた。(中略)
エンデンの容疑は不明だが、トルコでは「大統領侮辱罪」に対して最高で4年の実刑判決が待っている。
トルコ検察当局は、2014年8月の大統領就任から2016年半ばまでの間に、エルドアンを侮辱した容疑で市民約2000人が起訴されている。被告人のなかには元ミス・トルコや学生、学者、メディア関係者なども含まれている。【7月5日 Newsweek】
********************
【悪化する欧州との関係】
犯行に及んだ者はトルコ系ドイツ人ということでしょうか。
欧州にとっては中東・アフリカからの難民問題でトルコの協力が不可欠であるという事情がありますが、また、ドイツのように国内にトルコ系移民を多数抱えている国も多いなかで、エルドアン政権の強権的政治姿勢に対しては欧州各国は不信感を強めています。
大統領権限集中の改憲の是非を問う4月の国民投票の際も、トルコ政府閣僚の欧州でのトルコ人集会への参加が拒否されたりして、欧州各国とトルコの関係がギクシャクしていましたが、ドイツで現在開催中のG20に参加するエルドアン大統領がドイツ在住のトルコ人の集会で演説をしようとしたところ、ドイツ政府から拒否されるといった事態にもなっています。
ドイツとしては、エルドアン大統領への不信感もありますし、トルコ国内の“分断”をドイツ国内のトルコ系住民のなかに持ち込まれては困るという事情もあるでしょう。
そうした良好とは言い難い雰囲気のなかで、ドイツではエルドアン大統領への過激な抗議行動も。
****エルドアン氏殺害で賞品? 芸術作品めぐりトルコがドイツに抗議****
トルコ政府は4日、レジェプ・タイップ・エルドアン大統領らを殺害すれば賞品として車を与えると訴えた芸術作品を、ドイツの首都ベルリンの首相官邸前に設置することを許可したとして、ドイツ政府に正式に抗議した。
問題の作品は3日にアンゲラ・メルケル独首相の官邸前に設置された。高級自動車メーカー「メルセデス・ベンツ」のCクラスが置かれ、その前に張られた横断幕には「この車が欲しい?独裁者を殺せ!」と書かれたメッセージとともに、エルドアン大統領、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領、サウジラビアのサルマン国王の姿が描かれている。
作品を制作したのはフィリップ・ルッホ氏が率いる芸術集団「センター・フォー・ポリティカル・ビューティー」。この団体は難民政策に抗議してベルリン中心部にトラ4頭を展示するなど、これまで様々な活動を行ってきた。
トルコ外務省は声明で、「ベルリンの首相官邸前に設置された作品を強く非難する」と発表。また「横断幕は暴力を直接的に扇動するもの」だと主張し、事態を収拾するために必要な措置を講じるようドイツ当局に求めた。
横断幕に描かれた指導者3人は全員、ハンブルクで7~8日に開かれる主要20か国・地域(G20)首脳会議(サミット)に参加する予定だったが、サルマン国王は出席を取りやめている。【7月5日 AFP】
*******************
この横断幕が現在どうなったのかは知りません。日本なら、即座に撤去されるでしょうが。
もともとエルドアン大統領は、当初はイラン・ロシア・アルメニア・中国など、EU諸国以外の国々とも関係強化を図る、「ゼロ・プロブレム外交」と呼ばれる全方位外交を展開していました。
しかし、現在は上記のような欧州との対立に加え、冒頭演説にもあるシリアのクルド人勢力に関しては、今後支援するアメリカとの間で綱引きが予想されます。
更に、昨日ブログで取り上げたカタール断交問題では、サウジアラビアなどのアラブ諸国と対立する形にもなっています。
「ゼロ・プロブレム外交」どころか、周囲はプロブレムばかり・・・といった状況。
更に、国内にはイスラム過激派やPKKのテロに加えて、野党勢力との対立など“分断”が進行・・・ということで、内外ともに課題山積です。
そういう状況なので、エルドアン大統領のようなタフで強気な指導者でないとリードできない・・・と言うべきか、エルドアン大統領のような強引な政治手法なので、多くの課題が内外に生じていると言うべきか・・・・。
個人的には、後者の側面が強いように思っていますが。