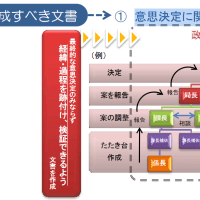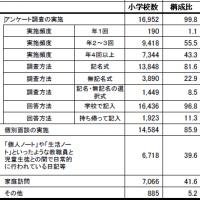安倍晋三が2021年4月21日午前9時前、靖国神社を参拝した。参拝のあと、安倍晋三は記者団に対し「国のために戦い、尊い命を犠牲にされた、ご英霊に尊崇の念を表するために参拝した」、そう述べたと2021年4月21日付「NHK NEWS WEB」記事が伝えている。
安倍晋三が2021年4月21日午前9時前、靖国神社を参拝した。参拝のあと、安倍晋三は記者団に対し「国のために戦い、尊い命を犠牲にされた、ご英霊に尊崇の念を表するために参拝した」、そう述べたと2021年4月21日付「NHK NEWS WEB」記事が伝えている。当ブログ記事のメインは安倍晋三の靖国参拝問題だが、「NHK NEWS WEB」記事のメインは首相の菅義偉が木札に「内閣総理大臣菅義偉」と記した真榊を奉納したことの情報の方となっている。こちらから先に取り掛かることにする。
記事は菅義偉が総理大臣就任(2020年9月16日)後の10月に行われた秋の例大祭でも「真榊」を奉納しているとの情報を追加している。この真榊奉納について詭弁家の官房長官加藤勝信が午前の記者会見で「私人としての行動であり、政府としてそれに対してコメントを申し上げる立場にはない。靖国神社を参拝されるか否かは、菅総理大臣が適切に判断される事柄であると考えている」と発言しとを伝えている。
木札に「内閣総理大臣菅義偉」と記した真榊を秘書官か誰かに持たせて靖国神社に奉納したのである。それを「私人としての行動」だと言う。詭弁とは「道理に合わない、言いくるめの議論」のことを言う。道理に合う言いくるめの議論など存在しないから、道理に合わないということになるのだが、なぜ言いくるめなのかは証明しなければならない。
この「NHK NEWS WEB」記事は中国政府はこれまでのところ公式の反応を示していないとした上で中国国営新華社通信の報道を伝えている。
新華社通信「日本の菅総理大臣が、内閣総理大臣の名義で靖国神社に『真榊』と呼ばれる供え物を奉納した。菅総理大臣は去年10月にも真榊を奉納したが、官房長官だった時期には奉納したことがなかったことから、安倍前総理大臣のやり方にならったとみられる。
靖国神社には第2次世界大戦のA級戦犯がまつられており、中国は日本の政治家の誤ったやり方に断固反対するとともに、日本には侵略の歴史を直視して反省し、実際の行動でアジアの隣国と国際社会の信頼をえるよう求める」
要するに菅義偉は官房長官時代は真榊の奉納はしていなかったが、首相就任後に去年10月と今回4月の真榊奉納を始めた。
共同通信配信の2021年4月21日付「東京新聞」も、〈首相は官房長官時代は真榊を奉納していなかったが、首相就任後は安倍氏の首相在任時の対応に倣っている。〉と書いている。菅義偉本人は安倍晋三に倣っているわけではないと言うかもしれないが、官房長官時代にはしなかったことを首相になって始めたということは少なくとも安倍・菅政権は首相を仰せつかったなら日本国家を代表して内外の情勢が許すなら直接参拝を、許されないなら真榊奉納を習わしとするとしていることを意味することになる。
このことを裏返すなら、菅義偉は首相になっていなかったなら、真榊の奉納はなかったことになる。となると、詭弁家加藤勝信が言うように「私人としての行動」と言うことはあり得ず、木札に記したように「内閣総理大臣菅義偉」としての奉納と言うことになる。それを「私人としての行動」とするのは加藤勝信が得意とする言いくるめの議論以外の何ものでもない。
事実でないことを「事実です」と押し通せば、事実に変え得るという確信のもとに事実と装う薄汚い言いくるめを多々見受ける。詭弁家化加藤勝信は当然として、安倍晋三然り、菅義偉然り、接待疑惑で国会参考人招致された総務省官僚やその他の官僚然り。
安倍晋三の場合は首相を退任して一国会議員の立場だから、何も問題はないだろうと見た靖国参拝かもしれないが、事実、上記「NHK NEWS WEB」記事もその他も菅義偉の真榊奉納に中国は既に触れたように「侵略の歴史への直視と反省」を求め、韓国は「深い失望と遺憾の意」を表すると同時に中国と同じく「歴史への直視」を求めているものの、安倍晋三個人に対しては直接的に非難する文言は見当たらない。
と言うことは中国も韓国も、総理大臣として日本国家を代表する立場での参拝や真榊奉納に特段の疑義を持たせていることになる。安倍晋三自身もこのことを承知しているはずで、このことは総理大臣を辞任したあとの去年9月と10月に参拝していると上記「NHK NEWS WEB」記事が伝えていることからも窺うことができる。
こういった点からも加藤勝信が菅義偉の真榊奉納を「私人としての行動だ」とするのは薄汚い言いくるめの議論に相当することが理解できる。
安倍晋三が参拝後に記者団に述べた参拝理由を再び取り上げてみる。「国のために戦い、尊い命を犠牲にされた、ご英霊に尊崇の念を表するために参拝した」
この「国のために」の「国」とは断るまでもなく天皇絶対主義体制下の大日本帝国国家を指す。民主主義国家日本は戦前は一度も存在したことがないのだから、靖国神社の戦没者はそのような国のために戦うことも、尊い命を犠牲にすることもできない。
要するに安倍晋三本人が事実でないと言いくるめようと言いくるめまいと、安倍晋三が言う「国のために」の「国」とは「天皇絶対主義体制下の大日本帝国国家」を指していて、参拝後の常套文句は「天皇絶対主義体制下の大日本帝国国家のために戦い、尊い命を犠牲にされた、ご英霊に尊崇の念を表するために参拝した」という意味を取ることになる。
また、「天皇絶対主義体制下の大日本帝国国家が起こした戦争のために戦い、尊い命を犠牲にされた」ことを受けて「ご英霊に尊崇の念を表する」としているのだから、安倍晋三は、当然、その戦争を「戦い、尊い命を犠牲」にするにふさわしい戦争だったと肯定的に歴史認識していることになる。
大体が「尊崇の念を表する」とは「尊(たっと)び崇(あが)める」という最大級の称賛で評価していることになるのだから、肯定的な歴史認識で捉えていなければ、こういった評価はできない。戦没者を偶像化の一歩手前にまで持っていっている評価と言えないことはない。
では、天皇絶対主義体制下の大日本帝国国家とはどのような国家で、その国家の戦争を国民はどのように戦うことになったのだろうか。
昭和天皇が敗戦翌年の1946年2月に侍従長藤田尚徳に語ったとされる<「立憲国の天皇は憲法に制約される。憲法上の責任者(内閣)が、ある方策を立てて裁可を求めてきた場合、意に満ちても満たなくても裁可する以外にない。自分の考えで却下すれば、憲法を破壊することになる」>(2006.7.13.『朝日』朝刊/『侍従長の回想』)ことを以って開戦を阻止できなかった理由に挙げているという。
大日本帝国憲法第4章「国務大臣及枢密顧問」は次のように規定している。
第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
第56條 枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
【輔弼】「天子の政治を助けること。旧憲法で、天皇の機能行使に対し、助言を与えること」
【諮詢】「参考として問い尋ねること」(以上(『大辞林』三省堂)
要するに国務大臣(総理大臣を含む)は天皇の政治に助言を与え、その政治を助ける役目を負い、枢密顧問は天皇が意見を求めたことを審議する役目を負っている。この枢密顧問の役目は旧憲法下に存在した諮詢機関なる組織の役目を見れが理解できる。「天皇がその大権を行使するにあたって意見を徴した(求めた)機関」(同『大辞林』)とされていて、枢密院、元老院、元帥府などがこの機関に当たると言う。
昭和天皇が侍従長藤田尚徳に語った言葉によると、国務大臣の天皇に対する助言も、枢密顧問の天皇の求めに応じた審議の結果も、「意に満ちても満たなくても裁可した」と言うことになる。このことが事実とすると、天皇は国務大臣や枢密顧問に対して従属的な立場に立たされていて、実質的な権限は天皇よりも国務大臣や枢密顧問の方が上と解釈しなければならなくなる。
だが、大日本帝国憲法のどの条項を取っても、天皇は他の機関の上に位置していて、決して下には位置していない。求めた意見に対して「意に満ちても満たなくても裁可する以外にない」といった意志決定の構造はどこを探しても見当たらない。
昭和天皇の言葉のように「憲法上の責任者」が内閣であるとすると、大日本帝国憲法の天皇に対する絶大なる権力の保障は見せ掛けと化し、天皇は単なるお飾りだったことになる。
先ず大日本帝国憲法は前文に当たる箇所に、〈国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ傳フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ將來此ノ憲法ノ條章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆(あやま)ラサルヘシ〉と規定している。要するに「国家統治ノ大権」は代々の天皇に付属した権利ということになる。そして「憲法ノ條章ニ循ヒ」とは主として以下の「條章」を指す。でなければ、「国家統治ノ大権」とは言えない。
第1章天皇
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬(統合して一手に掌握すること)シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第13條 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
例え天皇が憲法に従って他の機関に助言や意見を求めることはあっても、大日本帝国国家の統治権者は天皇であり、「神聖ニシテ侵スヘカラス」絶対的な存在であり、大日本帝国国家の元首であると同時に統治権を一手に掌握していて、このような絶大な権能を妨げる憲法上の条項は見当たらない。見当たったなら、「神聖ニシテ侵スヘカラス」という絶対的な存在と自己矛盾を来すことになり、大日本帝国憲法から見た天皇の姿はとてものことにお飾りには見えないことになる。
では、安倍晋三やその他が「国のために戦い、尊い命を犠牲にされた」とする戦争の開戦を宣言した昭和天皇の実在の姿を2007年4月号「文藝春秋」掲載の『小倉侍従日記』から探ってみる。日記の掲載は昭和14年5月3日から始まり、敗戦1日前の昭和20年8月14日で終っている。開始の5月3日から4日後の5月7日の日記に対する歴史家半藤一利氏の解説には「天皇このとき38歳。皇太子5歳」とある。
『小倉侍従日記』昭和14年5月11日の日記には大本営陸軍参謀付などを務めた1歳年下の弟宮秩父宮殿下が昭和天皇との御対顔の申し出があったのに対して昭和天皇が「困ったな困ったな」と困惑した様子が記されている。この様子を半藤一利氏は『昭和天皇独白録』を用いて解説している。
「それから之はこの場限りにし度いが、三国同盟に付て私は秩父宮と喧嘩をしてしまった。秩父宮はあの頃一週三回くらい私の処に来て同盟の締結を進めた。終には私はこの問題については、直接宮には答へぬと云って、突放ねて仕舞った」
昭和天皇は日独伊三国同盟の締結には反対だった。
『『小倉侍従日記』〈昭和14年10月19日「白鳥〔敏夫〕公使、伊太利国駐箚(ちゅうさつ・駐在)より帰国す。軍事同盟問題にて余り御進講、御気分御進み遊ばされざる模様なり。従来の前例を調ぶるに、特殊の例外を除き、大使は帰国後、御進講あるを例とす。此の際、却って差別待遇をするが如き感を持たしむるは不可なり。仍(よ)つて、御広き御気持ちにて、御進講御聴取遊ばさるるようお願いすることとせり〉――
在イタリア白鳥敏夫公使が帰国し、慣例となっている天皇への御進講に昭和天皇は乗り気ではなかった。小倉侍従は慣例を破ると差別待遇のような印象を持たせることになるから、広い気持ちになって御進講を受けるようにお願いすることにしたという内容である。
この内容について半藤一利氏が解説している。「側近が、どうか広い気持ちで白鳥大使に会ってくださいと天皇に頼まざるを得なかったのはなぜか。三国同盟問題で、特に自動的参戦問題(日独伊三国同盟第3条自動参戦条項はドイツまたはイタリアがアメリカから攻撃を受けた場合は日本が自動的に参戦することを規定していた)について内閣が揉めているとき、ベルリンの大島大使ともども、駐イタリア大使白鳥敏夫は、何をぐずぐずしているのか、早く同盟を結べ、といわんばかりの意見具申の電報を外務省に打ち続けていた。これに天皇は怒りを覚えていた」
第3条「締結國中何レカ一國ガ、現ニ歐州戰爭又ハ日支紛爭ニ參入シ居ラザル一國ニ依リ攻撃セラレタル時ハ、三國ハアラユル政治的經濟的及軍事的方法ニ依リ相互ニ援助スヘキ事ヲ約ス」
アメリカとは書いてないが、アメリカを念頭に置いた条項だと言う。昭和天皇はこの第3条の自動参戦条項に反対していた。アメリカとの戦争に反対していたことと整合する。
半藤一利氏が『西園寺公と政局』(原田熊雄著)に記してある天皇の発言を紹介している。「元来、出先の両大使が何等自分と関係なく参戦の意を表したことは、天皇の大権を犯したものではないか。かくの如き場合に、あたかもこれを支援するかの如き態度をとることは甚だ面白くない」
大使や公使の分際で天皇自身が反対している自動参戦条項に賛成するような口の挟み方は天皇の大権を犯すようなものではないかと立腹した。だが、この立腹は同時に天皇の大権の無力を証明して余りある。天皇の大権を「第1章天皇」で規定してある各条項の権限に基づいて行使すれば、日独伊三国同盟の協議を直ちに打ち切るよう命ずることができたはずだが、直接内閣に命じて打ち切ることはできずに大使、公使に腹を立て、八つ当たりした。
さらに半藤一利氏は解説している。
「9月7日ヒトラーの特使スターマーの来日、1週間後の14日には大本営政府連絡会議、16日の臨時閣議で決定と、三国同盟の締結が承認されるまで、あれよあれよという早さである。16日の近衛首相上奏のとき、参戦義務によって国際紛争にまきこまれるのを憂慮した天皇は、『今しばらく独ソの関係を見極め上で締結しても、晩くはないではないか』と最後の反対意見を言ったが、それまでとなった。この日の御前会議ですべてが決したのである」
この解説がが記している、天皇が「最後の反対意見」を述べたこと自体が、「憲法上の責任者(内閣)が、ある方策を立てて裁可を求めてきた場合、意に満ちても満たなくても裁可する以外にない」としていた天皇自身に課せられた役目としている従属性に反する意思表示であろう。
日独伊三国同盟に対する昭和天皇のそもそもからの反対意思が内閣の決定過程に何ら反映されなかったということは日本帝国憲法「第1章 天皇」で描く絶対権力者としての天皇の姿に反して現実には自らの意思を国策に反映させるだけの力を有していなかったと見るべきが自然ではないだろうか。つまり天皇は「第1章 天皇」の規定に似ても似つかないお飾りに過ぎなかった。
『小倉侍従日記』〈昭和15年9月27日(金)本夜8・15、ベルリンに於いて、日独伊三国条約締結調印を了せり。直に発表、同時大詔渙発せらる。〉――
【大詔】「天皇の詔勅。みことのり」(『大辞林』)
【渙発】「詔勅を広く発布すること」(『大辞林』)
半藤一利氏の解説「9月24日の天皇の言葉。
『日英同盟のときは宮中では何も取行われなかった様だが、今度の場合は日英同盟の時の様に只慶ぶと云ふのではなく、万一情勢の推移によっては重大な危局に直面するのであるから、親しく賢所に参拝して報告すると共に、神様の御加護を祈りたいと思ふがどうだろう』(『木戸日記』)
昭和天皇の「万一情勢の推移によっては重大な危局に直面する」はアメリカとの戦争を危惧しての言葉であり、その危惧自体がアメリカとの戦争に反対意思であることを物語っている。
そして大詔の一説。
「帝国の意図を同じくする独伊両国との提携協力を議せしめ、ここに三国間における条約の成立を見たるは、朕の深くよろこぶ所なり」〉――
【賢所】(かしこどころ)「宮中三殿の一。天照大神 (あまてらすおおみかみ) の御霊代 (みたましろ) として神鏡を奉安してある所。」(goo国語辞書)
半藤一利氏の解説による昭和天皇の言葉は天皇自身の無力を語って余りある。日本帝国憲法「第1章 天皇」に規定された絶大権力を以ってすれば、反対していた日独伊三国同盟を葬り去ることができたはずだが、そのような力を持っていなかったことが露見しただけではなく、この条約の第3条自動参戦条項によって日本がアメリカと戦争を起こすことを恐れて、そうならないように天照大神の御霊に頼んで日本の平安無事を祈る。つまり国家統治ノ大権を有しながら、内閣を動かすことができずに神頼みに縋るしかなかった。
しかも、条約の成立に反対していたにも関わらず、自身の意に反した成立を詔勅で「朕の深くよろこぶ所なり」と迎え入れなければならなかった。天皇という存在に対して無条件に従属的であった一般国民は天皇のこの詔勅の言葉によって「天皇陛下バンザイ」の気持ちで歓迎したに違いない。
では、昭和天皇がアメリカとの戦争にも反対していたことと、その反対意思を内閣の決定に反映させることができなかった無力を半藤一利氏の解説を混じえた『小倉侍従日記』から拾い出してみる。
『小倉庫次侍従日記』〈昭和15年1月29日(月)「歌会始 御製 西ひかしむつみかわして栄ゆかむ世をこそいのれとしのはしめに」〉――
「年の初めに当たって、西も東も心を交わし合って世界が栄えることを祈ろう」。日米戦争反対意思の現れ以外の何ものもでもない。
『小倉庫次侍従日記』〈昭和16年9月5日(金)(前略)近衛首相4・20-5・15奏上。明日の御前会議を奉請したる様なり。直に御聴許あらせられず。次で内大臣拝謁(5・20-5.27-5・30)内大臣を経、陸海両総長御召あり。首相、両総長、三者揃って拝謁上奏(6・05-6・50)。御聴許。次で6・55、内閣より書類上奏。御裁可を仰ぎたり。〉――
内大臣(ないだいじん)は木戸幸一。陸軍参謀総長は杉山元(げん)。海軍軍令部総長永野修身(おさみ)。
半藤一利氏解説「あらためて書くも情けない事実がある。この日の天皇と陸海両総長との問答である。色々資料にある対話を、一問一答形式にしてみる」
天皇「アメリカとの戦闘になったならば、陸軍としては、どのくらいの期限で片づける確信があるのか」
杉山「南洋方面だけで3ヵ月くらいで片づけるつもりであります」
天皇「杉山は支那事変勃発当時の陸相である。あの時、事変は1ヶ月くらいにて片づくと申したが、4ヵ年の長きにわたってもまだ片づかんではないか」
杉山「支那は奥地が広いものですから」
天皇「ナニ、支那の奥地が広いというなら、太平洋はもっと広いではないか。如何なる確信があって3ヵ月と申すのか」
杉山総長はただ頭を垂れたままであったという。
杉山元は陸軍参謀総長として海軍と協力して南洋攻略の戦略を立てていたはずである。その戦略を昭和天皇に丁寧に説明し、結論として導き出された作戦完了日数を「3ヵ月」と伝えなければならないはずだが、戦略との関連付けもなしに「3ヵ月くらい」云々のみで済ます。国家統治ノ大権を有し、「第1章天皇 第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」の規定によって一般の国務から独立するとされた陸海軍の統帥権を握っている天皇に対する扱いとしては、言葉や態度は丁寧であっただろうが、粗略に過ぎる。対して天皇としても、陸海軍の統帥権者の立場から精通していなければならない戦略を聞かされていなかった疑いが出てくる。つまり重要な国策決定の場から昭和天皇は排除されていた状景が否でも見えてくる。この状景は大日本帝国憲法の天皇に関する各条項が単なる名目に過ぎないことを教えかねない。つまり益々お飾りだったことの色彩を色濃くすることになる。
『小倉侍従日記』〈昭和16年7月29日(火)本日、日本軍、仏印に平和進駐す。〉――
半藤一利氏解説「前日の28日に陸軍の大部隊がサイゴンに無血進駐をした。『好機を捕捉し対南方問題を解決する』という国策決定にもとづく軍事行動である。アメリカは、ただちに在米日本資産の凍結、さらに石油の全面禁輸という峻烈な経済制裁でこれに対応している。海軍軍務局長岡敬純(たかずみ)少将は『しまった。そこまでやるとは思わなかった。石油をとめられては戦争あるのみだ』といった。」
仏印とは現在のベトナム・ラオス・カンボジアを併せた領域だが、無血進駐を可能にしたのは1940年6月にナチスドイツ軍がパリに到達し、フランスは6月22日にドイツと休戦協定を締結、国土の北部半分をドイツが占領、南半分はドイツ傀儡の政権が誕生したからである。つまり仏印のフランス軍は本国からの支援は望めない状況で日本軍と対峙しなけれならなかった。仏印フランス軍は無血降伏が犠牲を最小限にとどめる最良の作戦だったに違いない。
中国大陸には日本だけではなく、アメリカもイギリスもフランスも進出していて相互に競合関係にあり、日本の関東軍が1931年に満州事変を起こして翌1932年(昭和7年)3月に中国の東北部に建国した満州国をアメリカは不承認を決めたことでアメリカと日本の間に緊張関係が生じていただけではなく、1940年(昭和15年)9月27日の日独伊三国同盟締結によって日米の緊張関係はさらに悪化、、日本軍の1941年(昭和16年)7月29日の仏印進駐は南シナ海を挟んだフィリピンがアメリカの植民地であるという関係上、アメリカの警戒は危機管理上の想定内とする戦略を立てていなければならなかったはずだが、海軍軍務局長岡敬純少将の「しまった。そこまでやるとは思わなかった。石油をとめられては戦争あるのみだ」はフィリピンにまで目を向ける危機管理まで組み込んだ戦略を立てていなかったとしか思えない。
戦略とは長期的・全体的展望に立った目的行為の準備・計画・運用の理論と実践方法を言う。国策には常に欠かすことができない方法論だが、陸軍参謀総長の杉山元と言い、、海軍軍務局長少将の岡敬純と言い、軍の中枢人物であるという事実に逆説する関係で戦略なるものに対する視点を欠いていたとは驚きである。こういった手合が日本軍の支配的位置に就いていた。
日本はアメリカから在米日本資産の凍結や石油全面禁輸といった経済制裁を受けて、対米関係の修復に乗り出さざるを得なかった。1941年春から日本陸軍の中国大陸撤退を条件に、満州国の国家承認、日独伊三国同盟の是非、 日米通商関係の正常化などを論点とした交渉が野村吉三郎駐アメリカ大使とコーデル・ハル国務長官との間で開始された。(Wikipedia)
『小倉侍従日記』〈昭和16年11月5日(水)第7回御前会議(東一の間臨御、10・35-0・30、休憩、再開1・30-3・10)(後略)〉――
半藤一利氏解説「この日の御前会議で、11月末までに日米交渉妥結せずとなった場合、大日本帝国は『自存自衛を完うし大東亜の新秩序を建設するため、このさい対米英蘭戦争を決意』という『帝国国策遂行要領』を決定する。武力発動の時期は12月初頭と決められた」
『小倉侍従日記』〈昭和16年12月1日(月)本日の御前会議は閣僚全部召され、陸海統帥部も合わせ開催せらる。対外関係重大案件、可決せらる。〉――
半藤一利氏解説「開戦決定の御前会議の日である。『杉山メモ』に記されている天皇の言葉は、「此の様になることは已むを得ぬことだ。どうか陸海軍はよく強調してやれ」。杉山総長の感想は「童顔いと麗しく拝し奉れり」である」
結局日米会談は決裂した。
『小倉侍従日記』〈昭和16年12月8日(月)(前略)今暁、米、英との間に戦争状態に入り、ハワイ、フィリッピングアム、ウェーク、シンガポール、ホンコン等を攻撃し、大戦果を収む。前12・00(正午)防空下令、夕刻警戒官制施かる。〉――
1941年(昭和16年)12月8日に日本海軍はハワイの真珠湾攻撃を決行、昭和天皇の意思に反して太平洋戦争に突入した。真珠湾攻撃の大戦果に国民は歓呼した。日米が開戦したことによって日独伊三国同盟の規定に従い、ドイツとイタリアはアメリカに宣戦布告し、その布告を受けて、アメリカは欧州戦線に自動的に参戦することとなった。日独伊三国同盟で昭和天皇が危惧したこととは反対の事態が発生した。イギリスのチャーチルはアメリカの参戦によってドイツの敗北を予想したと言う。
かくこのように大日本帝国憲法に規定された天皇の国家統治の大権に反して天皇は国策決定に無力であった。その一方で一般的国民にとって天皇は大日本帝国憲法の規定とおりに絶対的存在であった。現人神であることを信じ、「神聖ニシテ侵スヘカラス」存在として奉り、天皇への無償の奉仕を心に決めていた。政治権力者たちは「天皇」と言う言葉を頭に置いて、国家権力が望む方向に国民を誘導していった。
その典型的な例が井上毅や元田永孚らが起草して、天皇家と国家への奉仕を求めた『教育勅語』であろう。
要するに軍部を含めた政治権力者たちは天皇を神格化し、その神性によって国民を統一・統制する国民統治装置として利用したが、国策の場では大日本帝国憲法で規定した天皇像が実在することを許さず、お飾りとも言える名目的な存在にとどめておく権力の二重構造で巧みに国家を運営した。あるいはそのような権力の二重構造によって憲法が見せている天皇の絶大な権限は国民のみにその有効性を発揮し、国民統治装置として機能していたが、軍部を含めた政治権力層には天皇の絶大な権限は通用させず、そのような権限の埒外に常に存在させていた。
この二重の権力構造は律令の時代から日本の天皇制を覆って日本の歴史・伝統・文化としてきた。何度もブログに書いてきているが、物部氏から始まって、それ以降、歴代天皇を頭に戴いて権力を実質的に握ってきたのは蘇我氏、藤原氏、平家、源氏、足利、織田、豊臣、徳川、明治に入って薩長・一部公家、そして昭和の軍部であった。日本の歴史は常に権力の二重構造を描いていた。
安倍晋三は「日本では、天皇を縦糸にして歴史という長大なタペストリーが織られてきたのは事実だ」と言って、天皇を日本の歴史と文化の中心に据えているが、天皇は日本の歴史を通じて歴代の世俗的な権力者にとって国民を統治する影武者に過ぎなかった。
日中戦争を含めた太平洋戦争で日本軍の兵士は大日本帝国憲法に規定された天皇の姿が国民を統治するために拵えられた便宜的なものであり、軍部を含めた政治権力者たちは天皇を憲法どおりには扱っていなかったとは知らないままに、なおかつ陸軍も海軍も戦略を立案する満足な才覚もなしに仕掛けた戦争を通して「国のために戦い、尊い命を犠牲にした」。或いは「天皇陛下バンザイ」と叫んで死地に飛び込んでいった。
死後、安倍晋三がしてきたように靖国神社に祀られている「ご英霊に尊崇の念を表する」云々と参拝されたとしても、少なくとも歴史を学んでいるはずの現代の日本人は素直には受け取れず、矛盾を感じないわけにはいかないはずだ。
当然、安倍晋三のようにはその戦争を「戦い、尊い命を犠牲」にするにふさわしい戦争だったと肯定的に歴史認識することもできないなずだ。