インドの菩提樹という木は蔓性で、他の植物に絡みついて、栄養を奪いながら芯の木を締め付けて殺してしまう。だから菩提樹はシメゴロシノキと呼ばれる。お釈迦様はそんな菩提樹の木の下に座っていて悟りを開いたと言われる。
強靭で真っすぐな木には、安心して蔦が絡み付く。人の世でも、優しく強くあろうとした者が、他人に寄りかかられ重荷を背負わされることは起こりうる。罵倒され疵つけられ踏みつけられても、泣くことも歩みを止めることもできず、栄養を吸いつくされる。絞め殺されていく。枯れて腐って、朽ちていく。
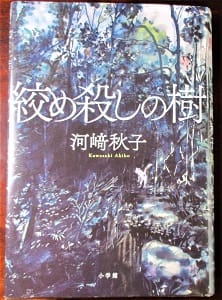
第ニ部の主人公・雄介の母ミサエはそういう人だった。
根室で生まれ4歳で母が死に、6年間新潟で暮らしたあと再び根室の農家・吉岡家に引き取られ、朝から晩までこき使われる。15歳で札幌の薬問屋で働く道が開けたが、24歳で「開拓保健婦」の資格をもって戦後の根室に戻る道を選んだ。人のために働き、養分を与え続け、気づけば、もう立っていることも億劫になっていた。だが気づかされた。自分の不幸に寄りかからず、最後までちゃんと生きなければ、と。
雄介は実母(ミサエ)も実姉も知らず、生後かつて母が下働きをしていた家に引き取られ育った。そして彼も大学卒業後は札幌から根室に戻り、家業を継ぐ決心をする。
根室の狭い集落の中でつながる糸。切れない糸がある。
「根をおろした場所で定められたような生き方をして、枯れていく。生まれたからには仕方ない。死にゆくからには仕方ない」
けれど、彼は思った。からからに乾いた根室の荒野に根を張り、風に耐えながら懸命に育ってきた木、実母も実姉も、自分と関わりを持った人たちみな、哀れな木だが弱くなどない、と。
「何にも脅かされることのない、静かで、暖かで、光差す場所を作るのだ」
雄介が宿した思いに、読んでいて心がいくらか緩んだ。
私は根室の地を知らないが、開拓農民の苦労、狭い社会のしがらみの中で、根を張り生きた人々が浮かぶ。スケールの大きな作品だ。
強靭で真っすぐな木には、安心して蔦が絡み付く。人の世でも、優しく強くあろうとした者が、他人に寄りかかられ重荷を背負わされることは起こりうる。罵倒され疵つけられ踏みつけられても、泣くことも歩みを止めることもできず、栄養を吸いつくされる。絞め殺されていく。枯れて腐って、朽ちていく。
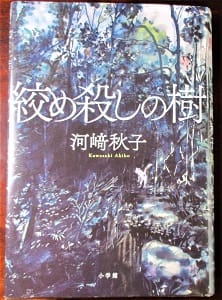
第ニ部の主人公・雄介の母ミサエはそういう人だった。
根室で生まれ4歳で母が死に、6年間新潟で暮らしたあと再び根室の農家・吉岡家に引き取られ、朝から晩までこき使われる。15歳で札幌の薬問屋で働く道が開けたが、24歳で「開拓保健婦」の資格をもって戦後の根室に戻る道を選んだ。人のために働き、養分を与え続け、気づけば、もう立っていることも億劫になっていた。だが気づかされた。自分の不幸に寄りかからず、最後までちゃんと生きなければ、と。
雄介は実母(ミサエ)も実姉も知らず、生後かつて母が下働きをしていた家に引き取られ育った。そして彼も大学卒業後は札幌から根室に戻り、家業を継ぐ決心をする。
根室の狭い集落の中でつながる糸。切れない糸がある。
「根をおろした場所で定められたような生き方をして、枯れていく。生まれたからには仕方ない。死にゆくからには仕方ない」
けれど、彼は思った。からからに乾いた根室の荒野に根を張り、風に耐えながら懸命に育ってきた木、実母も実姉も、自分と関わりを持った人たちみな、哀れな木だが弱くなどない、と。
「何にも脅かされることのない、静かで、暖かで、光差す場所を作るのだ」
雄介が宿した思いに、読んでいて心がいくらか緩んだ。
私は根室の地を知らないが、開拓農民の苦労、狭い社会のしがらみの中で、根を張り生きた人々が浮かぶ。スケールの大きな作品だ。















