
取り込もうとした干し物に、蝉が飛来していた。羽先が少し傷んでいる。放してやろうとつかんでも鳴かない。それがかえって少し寂しい気がした。
境内にある泰山木には毎年いくつもの抜け殻がしがみついている。虫取り網を持った子供たちの声がかわいかったものだが、何やらこの頃はとんと姿も見えない。
台風一過の折にはこの蝉たちはいかに。蟻たちのお掃除が始まるのだろう。
「管理責任などありませんよ。ただの寿命です」
「年をとって飲み込む力が落ちていた人が、物を詰まらせたんです。寿命以外の何物でもない」
限られた看護士の数に対して、田舎の小さな病院に入院する圧倒的な高齢者の人数。
高齢者医療の現実の中で、違和感や疑念、悩みを感じながら指導医のもとで研修医が成長していく姿が描かれていた。
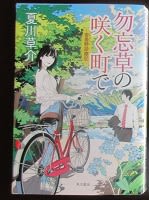
娘に送ろうと中古本で購入しておいたので、せっかくだし送る前に読んでみることにした
(『勿忘草の咲く町で 安曇野診療記』夏川草介)。
看護士と若い研修医。通俗小説か? か~ぁるい安っぽいドラマのようで面白くもなんともなくゲンナリ!
…していたのだが、著者が医師でもあるという独自性がもたらす医療問題に触れ出してからは、文章がどうのではなく、語ろうとするものに固有性を感じ、一気に読み通した。
生を奪う死はまた生きる意味を与える、とどこかで目にしたが…。
この手で
日々を
かきわけているようなれど
きづけば
仏の手のままに
念仏詩人 榎本栄一
何一つ 自力なし。お盆にはこんなことも考えてみたい。
















