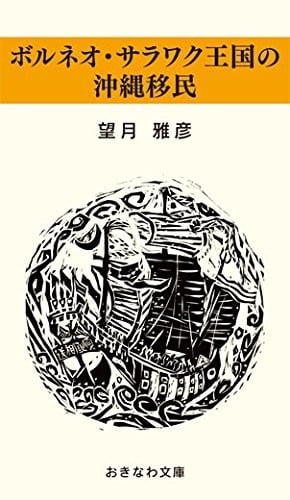マリア・グランド『Magdalena』(Biophilia Records、2018年)を聴く。

María Grand (ts, vo)
Jasmine Wilson (spoken word)
Amani Fela (spoken word)
Mary Halvorson (g)
David Bryant (p)
Fabian Almazan (p)
Rashaan Carter (b)
Jeremy Dutton (ds)
前作の『Tetrawind』と同様に、マリア・グランドのテナーは沈静し、落ち着いており、いわば艶消しである。その音色で(にもかかわらず)、特に「TI」から「TIII」までの3曲において、M-BASE直系のフレーズを水平垂直に広く繰り出してくる。このときのラサーン・カーターもまたM-BASE的なファンクであり、艶消しのサックスでのM-BASEトリオは聴いていけば快感になってくる。冷静にM-BASEの自分たちの世界を見せればいいのだと開き直っているような印象もある。
おもに後半での聴き所のひとつはデイヴィッド・ブライアントのピアノであって、華美に和音を使うでもなく、ここぞとばかりに不穏で傾いたフレーズを突きさしてくる。この人は、ルイ・ヘイズ、エイブラハム・バートン、ジョシュ・エヴァンスなどNYの「どジャズ」でも活き活きしているし(今度また来日してレイモンド・マクモーリンと共演する)、一方、ピーター・エヴァンス、ヘンリー・スレッギル、そしてこのM-BASEなど尖った方でもまた個性を発揮している。以前は「どジャズ」だけの人だと思っていたこともあり、次々に予想を裏切られ続けている。わたしとしては今後さらに大注目なのだ。
ピアノはもうひとり、ファビアン・アルマザンが参加している。2曲目の「Imani/Walk By」における煌びやかなフレーズか、これも愉しい。
それにしても、マリアのヴォイスが彼女のテナーと似たような味わいをもっていることが面白い。囁くようで、ちょっと神秘的でもクールでもあったりする。2曲でメアリー・ハルヴァーソンと共演しているのだが、そのときにはさらに世界に靄がかかって足場がぐらぐらする。
●マリア・グランド
マリア・グランド『Tetrawind』(2016年)
スティーヴ・コールマン『Morphogenesis』(2016年)