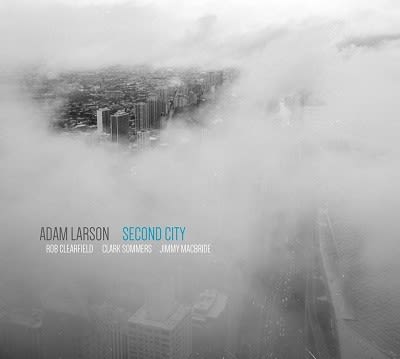マーク・リボーのセラミック・ドッグによる新譜『YRU Still Here?』(Northern Spy、-2018年)を聴く。

Marc Ribot (g, requinto, farfisa, b, e♭ horn, vocoder, vocals)
Shahzad Ismaily (b, Moog, perc, background vo, vo in Urdu)
Ches Smith (ds, perc, electronics, background vo)
予想を大きく上回る迫力のアヴァンロック・ノイズ・ジャズサウンド。ひたすら大音量で流しているだけでも頭が麻痺しカッチョいい。
しかしそれはそれとして、本盤は怒りを充満させたプロテストなのだ。「Pennsylvania 6 6666」では、シャザード・イズマイリーが生まれ育ったペンシルベニアの街の記憶を語る。白人のガキどもに囲まれて、かれらはグレン・ミラーを聴いていたりもして、そんな環境の狂気と疎外感。タイトル曲の「YRU Still Here?」では、中東的なコードに乗せて、「Why you still here?」「Why still here?」と繰り返す。もちろんどこに居てもいいのだ。その腹の中には鬱積した怒りがあっただろう。そして続く「Muslim Jewish Resistance」では、「Muslim Jewish, we say never again!」と、昔から繰り返し使われてきた常套句を。
リボーはこのように話している。排他的な動きのエスカレートに対する警戒とも言うことができる。「"Beyond being a disaster for those deported, imprisoned and living in fear, ICE is building a mass extra-legal prison system into which detainees may disappear without notice, and an armed force of agents who tear apart families and violate international human rights law on a daily basis,” Ribot said. “Does anyone believe that those carrying this out will suddenly refuse to follow orders just because the victims happen to be citizens?”」(『Downbeat』誌、2018/2/22)
同様の観点で、ヴィジェイ・アイヤー『In What Language?』(2003年)も参照できるのかな。
10曲目の「Freak Freak Freak On The Peripherique」では、それまでロック的にびしばし叩いていたチェス・スミスがさすがの小技も見せたりしてノリノリ。
できればブルーノート東京の公演に行こう。
●マーク・リボー
ロイ・ナサンソン『Nearness and You』(2015年)
マーク・リボーとジョルジォ・ガスリーニのアルバート・アイラー集(2014年、1990年)
ジョン・ゾーン『Interzone』 ウィリアム・バロウズへのトリビュートなんて恥かしい(2010年)
製鉄の映像(2)(ジョゼフ・コーネル『By Night with Torch and Spear』(1940年代))