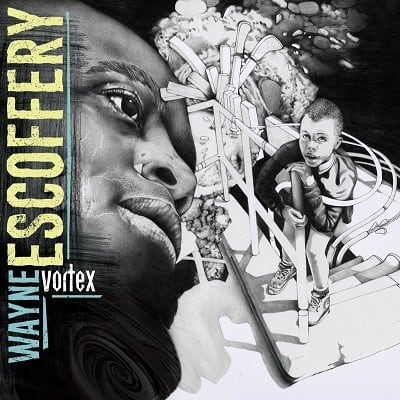CPユニット『Silver Bullet in the Autumn of Your Years』(clean feed、2017年)を聴く。

Chris Pitsiokos (as, wind controller, sampler, analog synthesizer, and other electronics)
Sam Lisabeth (g)
Tim Dahl (b) on 4, 6, 9, 10
Henry Fraser (b) on 1, 3, 5 ,7, 8
Jason Nazary (ds, electronics) on 4, 6, 9, 10
Connor Baker (ds) on 1, 3, 5, 7, 8
いや何というのか・・・。
CPユニットの前作(メンバーはティム・ダールのみ共通)を含め、最近のクリス・ピッツィオコスの作品で顕著だったことは、80-90年代のジョン・ゾーン的なペラペラな痙攣への回帰、そして機械への擬態といった過激な傾向のように思えた。それこそがキメラたるクリスの真骨頂だった。
本作ではさらに突き進み、音を発する他者や機械への擬態や変身などではなく、音そのものへの変身を遂げているようである。肉体を脱ぎ捨てるだけでは満足しないのだ。クリスはどこまで行くのか。
曲によってはフリーファンクが浮上してきて、それもまた面白い。ジョン・ゾーンの疾走先のひとつがオーネット・コールマンであったことも思い出すがどうか(『Spy vs. Spy』)。
●クリス・ピッツィオコス
フィリップ・ホワイト+クリス・ピッツィオコス『Collapse』(-2018年)
JazzTokyoのクリス・ピッツィオコス特集その2(2017年)
クリス・ピッツィオコス+吉田達也+広瀬淳二+JOJO広重+スガダイロー@秋葉原GOODMAN(2017年)
クリス・ピッツィオコス+ヒカシュー+沖至@JAZZ ARTせんがわ(JazzTokyo)(2017年)
CPユニット『Before the Heat Death』(2016年)
クリス・ピッツィオコス『One Eye with a Microscope Attached』(2016年)
ニューヨーク、冬の終わりのライヴ日記(2015年)
クリス・ピッツィオコス@Shapeshifter Lab、Don Pedro(2015年)
クリス・ピッツィオコス『Gordian Twine』(2015年)
ドレ・ホチェヴァー『Collective Effervescence』(2014年)
ウィーゼル・ウォルター+クリス・ピッツィオコス『Drawn and Quartered』(2014年)
クリス・ピッツィオコス+フィリップ・ホワイト『Paroxysm』(2014年)
クリス・ピッツィオコス『Maximalism』(2013年)