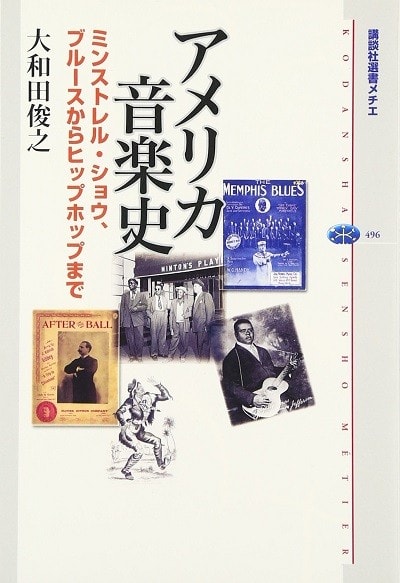テジュ・コール『オープン・シティ』(新潮クレスト・ブックス、原著2012年)を読む。
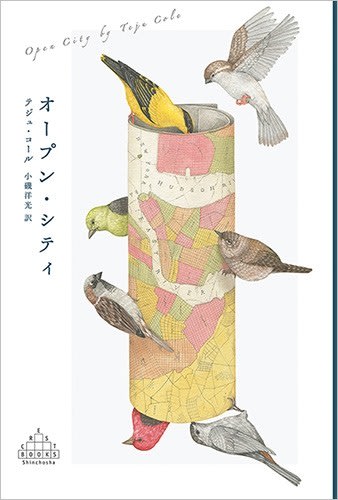
主人公はナイジェリア生まれ・NY在住の精神科医。アフリカ人であり有色人種である。そのことからも、世界が自分と隔たっている。かれはNYのアフリカ人と、かつて日系であるためにアメリカで収容された先生と、アメリカからベルギーに戻った老婦人と、誠実に、しかし自らの欺瞞を認識しながらも、話をし続ける。それはどうしたって摩擦と内省を生じる。
視るだけではない。かれは視られもする。世界に自分が溶け込んでいない、それはつねに視られていることでもある。公園の鳥にも視られる。世界からの疎外感は暴力でもあり、かれは自分に理不尽に与えられる暴力を受け容れているようでもある。しかし、暴力は受けるだけではなく、かれが他者に与えるものでもあった。しかも、自分自身が意識しないところで。
この静かで大きな驚きのまま、かれはマーラーのコンサートに出かける。そして、ついには世界の亀裂を視るのだ。読むべし。