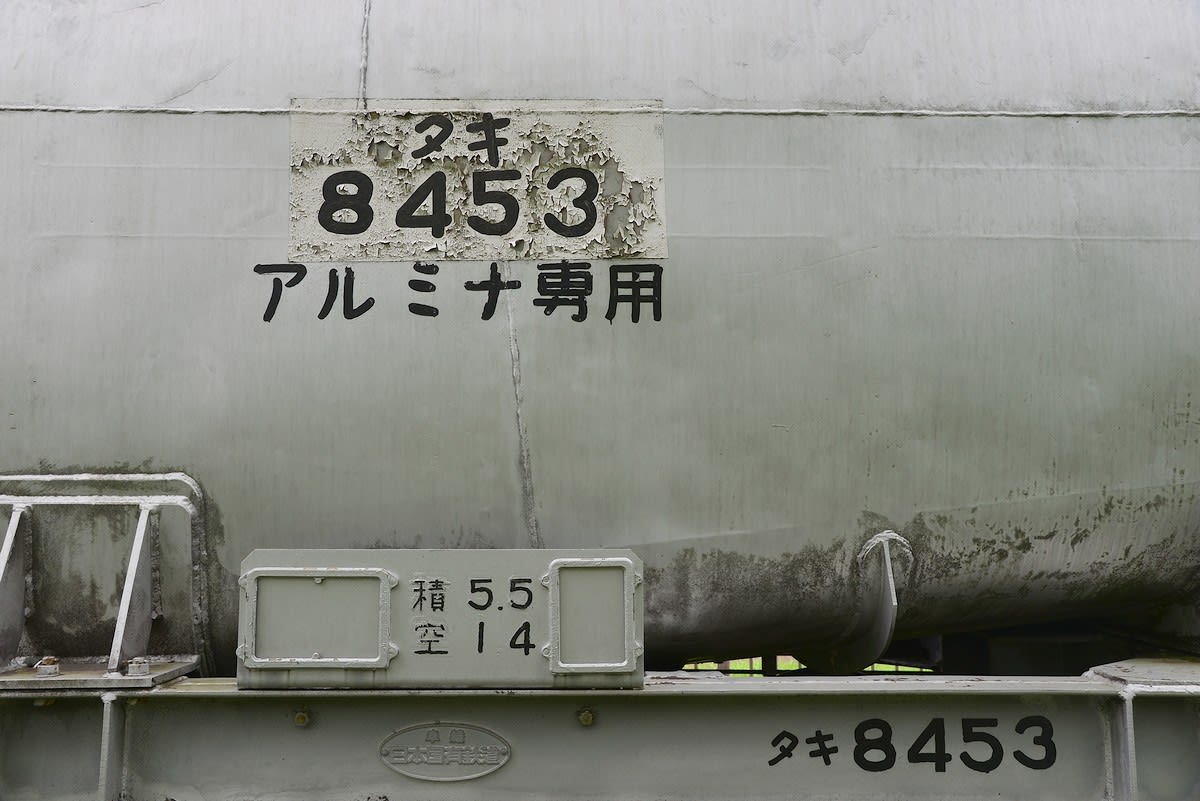(しとどに降る雨に濡れて@横江駅)
横江の駅は集落の中心部にはあるものの、立山へ向かう道からは一段下がった場所にあり、案内看板もないので初見では位置がちょっと分かりづらい。ただ、見ず知らずのヨソモノは知らなくとも、普段この駅を使う人間が知ってればそれで良いのかもしれない。以前は有人駅だったようですが、駅の左半分の居室部分には既に羽目板が打ち付けられていて、ツタが絡まり荒れるがまま。中を見る事は出来ませんでした。

駅舎をくぐってホームに出てみる。見た目で分かる通りかつては島式ホームの交換駅でしたが、既にレールは引っぺがされて棒線駅になっています。天気が良ければホームからは立山連峰の眺めが美しく見えるそうですが、この日のこの天気では望むべくもない。ちなみに初代の横江駅はここからもう少し600mほど立山寄りにあって、現在の横江駅は当初尖山(とがりやま)駅として開設。但しこちらの方が横江の集落に近かったので、昭和40年にかつての横江駅を上横江駅とし、尖山駅を横江駅と改称して今に至ります。んで、集落から離れていた上横江駅はその後どうなったかってーと、利用者減によって平成9年に廃駅となってしまいました。こんな過疎地に600m間隔で駅があっても仕方ないし、末期は利用者がゼロという状況だったそうで。跡地に行ってみたかったんだけど、工事中で入れんかった。

雨に煙る横江の駅。駅の先に見える坂道を、電鉄富山行きが降りて来ました。この辺りから常願寺川の刻む谷が立山に向かって狭まり、標高も高くなって行きますので、おのずと線路の勾配もきつくなって来る。線路脇に放置された古レールは、剥がされたかつての2番線側に敷かれていたものだろうか…。

今回の富山訪問、ファーストショットは14760系の第7編成。白をベースに灰色と赤のラインをきりっと締めた、地鉄トラディショナルとも言える雷鳥カラー(ダイコンカラー)が私は大好きなのですが、何故か14760系の中でもカボチャと呼ばれる橙と緑の塗り分けになっているハミ出しっ子がいます。横江の駅は、一日当たり50人程度の乗降客があるそうですが、この休日の雨の朝では流石に乗降客はなし。バスと違って電車はいいよね。乗降客がいなくても通過しないから。

駅の横の踏切の警報音と電車の音に静寂を破られた横江の駅ですが、電車が行ってしまえば再び傘を叩く雨音だけの静寂が訪れます。駅前広場に出来た水たまりに落ちる雨粒の輪を眺めながら、濡れ行く横江の駅の雰囲気に暫し浸ってみる。駅の開設を記念して植樹されたのか、駅前には立派な桜の古木がありまして、おそらく桜の時期はまたいい雰囲気になるのではないでしょうかねえ。
少し感傷的な気持ちを加速させるように、雨は降り続くのでありました。