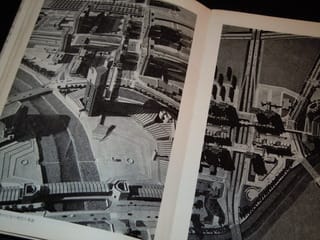■ TOTOギャラリー・間から徒歩で10分とかからない東京ミッドタウン。富士フィルムフォトサロンで写真展を観る。スターバックスでしばしコーヒータイム。地下鉄大江戸線で新宿へ。東京の友人と新宿駅で待ち合わせ、1年ぶりの再会。
すこし早目の食事。
会話。本のことに話題が及ぶ。
最近、記憶に残るような読書をしていない、というかそのような本がなかなかない、と友人。
同感。未読の名著を読みたい、SFの古典もいいかもしれないと話す。
加藤周一の全集のこと。
「自由からの逃走」って・・・、と振られて、著者のE・フロムをかろうじて思い出す。
最近読んだ漱石の「吾輩は猫である」のラストについて、酔っぱらって水甕に落ちた猫は生きることをあっさりとあきらめてしまうが、そこに漱石の願望に近い意識の反映があるのでは、と感じたことを話す。
川上弘美の「真鶴」に関して、長く会っていない知人・友人は「こちら側」にいても「あちら側」にいてもボクの場合、同じ存在感を持っていると話す。
倉橋由美子。この作家の作品として「パルタイ」がまず浮かぶ。が、友人は「大人のための残酷童話」にひかれているのでは、と思う。
松岡正剛。丸善で新刊を目にしたと話す。「松丸本舗」の書棚の魅力を今回も体験した。
20時発のスーパーあずさ33号に乗る。「龍宮」を鞄から取り出して、読み始める。川上弘美は昭和33年生まれ。「33」は共通する数字だ、と気がつく。
22時半過ぎ、あずさが松本駅に着いた。帰路を急ぐ。日帰り東京が終わった・・・。