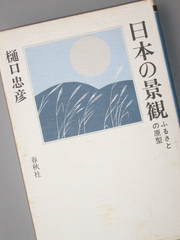■『風の盆恋歌』高橋治/新潮文庫を探していて、村上春樹していたとき(って、変な表現)に見つからなかった『ノルウェイの森』が見つかりました。書棚が既に満杯で全ての背表紙を見ることができる状態ではないので、手前の本に隠れた奥の本を探すのは困難なのです。書棚を増設するスペースと資金の余裕も無く・・・。
この『ノルウェイの森』のカバーデザインは赤と緑のクリスマスカラー(確か著者自らデザインした)で知られていますが、手元にある文庫のカバーデザインは違います。最初からクリスマスカラーではなかったんですね。
なんだか通俗的な小説だな、というのが当時の感想だったように思います。一通り村上春樹の長編小説を読み終えたいま、この小説を再読したら印象は違うでしょうが。
■ 東京の友人が、富山県八尾の「風の盆」を見てきたとブログに書いていました。小説『風の盆恋歌』によって「風の盆」はすっかり有名になって、9月のはじめには全国から見物客が押し寄せるんですね。先日テレビでちらっとその様子を見ました。
小説の解説を歌手の加藤登紀子さんが書いています。**胡弓の甘く悲しい音色、ゆったりとした低い音でリズムを刻む三味の苦みばしった音、そして踊る人たちの軽くてしなやかな、洗練された身のこなし、そしてとりわけ美しい指先。**
男と女の不倫の物語がこの「風の盆」の街を舞台に展開します。
**「風の盆」の静かな幽玄の世界をもし彼が見たら、何と思うだろう。静かさに陶酔するというこの境地、これはやっぱり、日本人の独特の美意識なのだろうか。八尾に残された神々しい程のこの幽玄の世界、いつまでも古めかしいままに、残ってほしいと思う。**
おときさんは解説文をこう結んでいます。小説の解説というよりも「風の盆」の観察記です。
友人のブログによると、どうやら観客のマナーがあまりよくなかったらしいのです。想像はつきます。節度を弁えないカメラマン、声高に会話する観光客・・・。
でもアップされた踊り手の後ろ姿の写真を見ると、行って見たいという思いに駆られます。