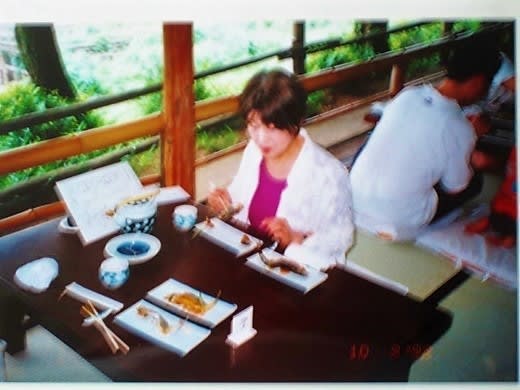小魚の食べ方は、人によってそれぞれ異なると思うが、小骨の付いたままの焼き魚は上手に食べるのに苦労する。私もその一人だ。短気が災いして我慢出来ず、まだ食べる部分があるにもかかわらず、途中であきらめてしまう。
家内は上手い。全くの骨だけにしてしまう。これには真似の出来ない何かがある様だ。
川魚で特に馴染みのある魚、それは鮎だ。その塩焼きは川魚の王様だと思っている。養殖の岩魚や鱒も塩焼きには趣があり美味いが、私は口にする機会が鮎ほどない。
これら小魚の料理の方法だが、大方頭の方から串を刺し魚全体に塩をまぶし、炭火でこんがり焼く。川で自然に泳いでいる姿をイメージして途中に曲がりを入れ、尻尾の手前をやはり一寸曲げて焼く。
一般には、焼きあがった鮎に打った串を抜き皿に移し、箸を使い骨を取りながら、「たで酢」などを漬けて食べる。当然「わた」の部分も食べるが、大方残してしまうことが多い。
鮎は、焼き立てを食べるのが一番美味いと思うが、それを串も取らずに背の部分から、かぶりつくのは、繊細な鮎を食べるには、あまりにも能のない食べ方で雰囲気がない。
もう随分と昔のことだが、父親が仕事の合間を利用して近所の川で鮎、うなぎ、かじかを獲っていた。だから鮎は中学時代から口にする機会があったので慣れていた。
一度焼いて数日空気に当てて乾燥したものを父親からは「風吹かす」と教わった。それを甘辛く煮つけておき、昼の弁当の「おかず」となっていた。その後可成りの年になって、違った食べ方を覚えた。
それは、平皿の上でまず串を抜き、尻尾の部分を手でちぎり離す。次に頭の部分を手で押さえ、鮎が川で自然に泳いでいる状態の縦にして、頭の部分から骨を残して肉部分をちぎる。そして肉の部分を箸で静かに押さえて左方向にゆっくり離して行く、つまり頭を持ち骨を引き抜くのだ。
頭と中心の骨と尻尾と真ん中の肉の部分に分けられるので、肉の部分を「たで酢」をつけて食べればよい。ただあくまで焼き立ての熱い間でないと外しにくい。
旅先の夜の食事に出される焼き物は、焼いてから時間が経過しており、この方法で食べることは無理の様だ。折角の「鮎の塩焼き」も美味い時に食べられないのは残念なことである。
=======終り==========================
上記の文章の著者の横山美知彦さんは終戦前後に家内が疎開した群馬県の下仁田小学校の同級生でした。
この6月初旬に同級会があり家内を下仁田まで送って行った時いつものように横山さんから文集を頂きました。
上の文章はその中の一編です。
尚、下仁田小学校のまつわる話は以下の記事にあります。
『茫々70年、群馬県の山の中、下仁田小学校物語り』
(2017年06月09日掲載)
そして鮎の塩焼きに関する記事は次の記事にあります。
『利根川の鮎料理、坂東簗の店仕舞いーある地方文化の終焉ー』
(2015年06月17日 掲載。)
毎年、6月になると利根川上流の坂東簗から今年も7月1日から9月30日まで営業を致しますのでお越しくださいと案内状が来ます。
それが今年の手紙は店仕舞いの挨拶状でした。何十年も家族とともに楽しんできたところが無くなるのです。しばし寂寞感にとらわれます。
これはある地方文化の終焉です。簗で鮎を捕り、見晴らしの良い川岸で鮎料理を楽しむのは、その地方の食文化です。時代が変わればその文化も終焉するのです。
坂東簗の発祥は江戸時代末期です。戦争の影響で一旦閉鎖されましたが、昭和29年に利根川の別名「坂東太郎」の名を冠して再び営業を始めました。そこは関東地方では有名な鮎料理の簗でした。
鮎を食べていると夏草の茂る利根川の広い川原が見渡せて、その向こうには榛名山や伊香保の山並みが見えるのです。その風情ある情景が忘れられません。
・・・・中略・・・・・・
このように利根川で取れた鮎を川風に吹かれながら食べる風習はもう無くなってしまうのです。夏の風物詩が一つなくなり、淋しくなります。(以下省略)
今日の挿し絵代わりの写真はこの記事の写真です。
今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)




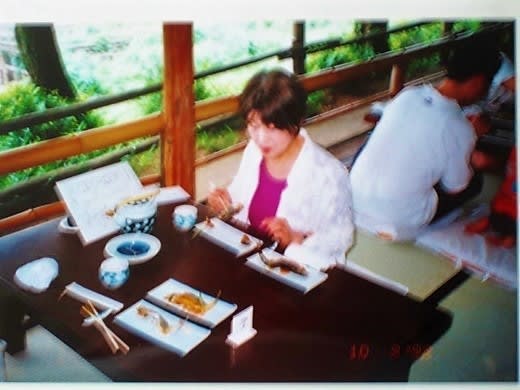
家内は上手い。全くの骨だけにしてしまう。これには真似の出来ない何かがある様だ。
川魚で特に馴染みのある魚、それは鮎だ。その塩焼きは川魚の王様だと思っている。養殖の岩魚や鱒も塩焼きには趣があり美味いが、私は口にする機会が鮎ほどない。
これら小魚の料理の方法だが、大方頭の方から串を刺し魚全体に塩をまぶし、炭火でこんがり焼く。川で自然に泳いでいる姿をイメージして途中に曲がりを入れ、尻尾の手前をやはり一寸曲げて焼く。
一般には、焼きあがった鮎に打った串を抜き皿に移し、箸を使い骨を取りながら、「たで酢」などを漬けて食べる。当然「わた」の部分も食べるが、大方残してしまうことが多い。
鮎は、焼き立てを食べるのが一番美味いと思うが、それを串も取らずに背の部分から、かぶりつくのは、繊細な鮎を食べるには、あまりにも能のない食べ方で雰囲気がない。
もう随分と昔のことだが、父親が仕事の合間を利用して近所の川で鮎、うなぎ、かじかを獲っていた。だから鮎は中学時代から口にする機会があったので慣れていた。
一度焼いて数日空気に当てて乾燥したものを父親からは「風吹かす」と教わった。それを甘辛く煮つけておき、昼の弁当の「おかず」となっていた。その後可成りの年になって、違った食べ方を覚えた。
それは、平皿の上でまず串を抜き、尻尾の部分を手でちぎり離す。次に頭の部分を手で押さえ、鮎が川で自然に泳いでいる状態の縦にして、頭の部分から骨を残して肉部分をちぎる。そして肉の部分を箸で静かに押さえて左方向にゆっくり離して行く、つまり頭を持ち骨を引き抜くのだ。
頭と中心の骨と尻尾と真ん中の肉の部分に分けられるので、肉の部分を「たで酢」をつけて食べればよい。ただあくまで焼き立ての熱い間でないと外しにくい。
旅先の夜の食事に出される焼き物は、焼いてから時間が経過しており、この方法で食べることは無理の様だ。折角の「鮎の塩焼き」も美味い時に食べられないのは残念なことである。
=======終り==========================
上記の文章の著者の横山美知彦さんは終戦前後に家内が疎開した群馬県の下仁田小学校の同級生でした。
この6月初旬に同級会があり家内を下仁田まで送って行った時いつものように横山さんから文集を頂きました。
上の文章はその中の一編です。
尚、下仁田小学校のまつわる話は以下の記事にあります。
『茫々70年、群馬県の山の中、下仁田小学校物語り』
(2017年06月09日掲載)
そして鮎の塩焼きに関する記事は次の記事にあります。
『利根川の鮎料理、坂東簗の店仕舞いーある地方文化の終焉ー』
(2015年06月17日 掲載。)
毎年、6月になると利根川上流の坂東簗から今年も7月1日から9月30日まで営業を致しますのでお越しくださいと案内状が来ます。
それが今年の手紙は店仕舞いの挨拶状でした。何十年も家族とともに楽しんできたところが無くなるのです。しばし寂寞感にとらわれます。
これはある地方文化の終焉です。簗で鮎を捕り、見晴らしの良い川岸で鮎料理を楽しむのは、その地方の食文化です。時代が変わればその文化も終焉するのです。
坂東簗の発祥は江戸時代末期です。戦争の影響で一旦閉鎖されましたが、昭和29年に利根川の別名「坂東太郎」の名を冠して再び営業を始めました。そこは関東地方では有名な鮎料理の簗でした。
鮎を食べていると夏草の茂る利根川の広い川原が見渡せて、その向こうには榛名山や伊香保の山並みが見えるのです。その風情ある情景が忘れられません。
・・・・中略・・・・・・
このように利根川で取れた鮎を川風に吹かれながら食べる風習はもう無くなってしまうのです。夏の風物詩が一つなくなり、淋しくなります。(以下省略)
今日の挿し絵代わりの写真はこの記事の写真です。
今日も皆様のご健康と平和をお祈りいたします。後藤和弘(藤山杜人)