【まくら】
香をたくと、使者の姿が現れるという迷信が、この噺の中核となっている。
【あらすじ】
カーンカーン…カーンカーン…。
夜中に響く鐘の音。最近、相長屋へ越してきた浪人者が夜通し鉦をたたくので、八五郎は不眠症に悩まされいた。
「もう我慢できねぇ!」
ある晩、とうとう頭に来た八五郎は浪人の長屋へ怒鳴り込む。話を聞いた浪人は、自分の非を詫びると事情を説明し始めた。
「私は元、因州鳥取の藩に属していた、島田重三郎という者でございます。ある日、江戸勤番の話の種に、仲間数人と吉原遊廓へ行き、かの三浦屋高尾太夫に一目ぼれをしました」
高尾も重三郎の愛を受け入れ、二人は「末は夫婦に」という契りを立てる。その証として、重三郎は高尾に家宝の短刀を、高尾は重三郎に香箱を贈った。
「このお香は、魂を反すと書いて反魂香、またとない名香です」
ところが、重三郎が勤番明けで江戸を離れているうちに、高尾は時の仙台公・伊達綱宗に身受けされてしまったのだ…。
「私との操を守ろうとするあまり、高尾は綱宗公になびきません。とうとう頭にきた公は、高尾を三叉の船中で斬り殺してしまいました」
世の無常を感じた重三郎は、自ら脱藩して浪人となり、残りの人生を高尾の供養に費やそうと決意した…。
「なるほど、そんな訳があったんですかい…」
ジーンとなる八五郎。実は彼も、最近女房のお熊を病で亡くしたばかりで、重三郎の苦悩はよーく解る。
「で…その『反魂香』っていう奴なんですが、そいつを焚くと、本当に高尾が現れるんですかい?」
重三郎はそうだと言う。興味を持った八五郎は、一度目の前で焚いてくれと重三郎に頼み込む。香炉に香をくべると、なんだか妙な雰囲気がしてヒュードロドロ…!
『おまえは…島田重三さん…』
立ち上る煙の中に、高尾の姿が現れた。
「そちは女房、高尾じゃないか」
『取り交わせし反魂香、余り焚いて下さんすな…香の切れ目が、縁の切れ目…』
「焚くまいとは思えども、そなたの顔が見たき故。俗名、高尾。頓生菩提、南無阿弥陀仏ナムアミダブツ…」
一陣の風ともに、高尾の姿は掻き消えて…。
「物は相談なのですが、そのお香…、少し譲ってはくれませんか?」
「できません。これは高尾が現世に残した形見であって…」
「そうでしょうね。…ところで、そのお香、なんていうんでしたっけ?」
「反魂香です」
「ありがと!!」
自分で買えばいいんだ。そう思った八五郎は重三郎の長屋を飛び出した。そのまま薬屋へと駆けて行き、店じまいをしていた親父を捕まえると「アレをくれ!」。
当然、薬屋は何の事だか分からない。
「ワカラネェ? えーと…あれだなぁ、あれだ…あら?」
あんまり慌てていたせいで、八五郎は肝心の品物の名を忘却していたのだ。
「仕方がねぇ。そこの棚に並んでいる奴を、右から順に読んでくんねぇ」
並んでいるのは伊勢浅間の『万金丹』に、越中富山の…。
「反魂丹!? それだ!!」
…本当は反魂香である。だが、八五郎はそれに気づかず、反魂丹をしこたま買い込むと店を飛び出した。
「ありがてぇ、ありがてぇ!」
戸を突き破るようにして家へ飛び込み、火鉢を持ってくると炭をくべて団扇でバタバタ…。
「これでかかぁに会える! うれしいねぇ、かかぁはなんて言うかな?」
『おまえは、島田』…じゃない、それは隣だ。『おまえは、やもめの八五郎さん』かな。俺は「そちは女房、高」…それも隣だ。「そちは女房、お熊じゃないか」かな?。
楽しい想像をめぐらせ、火鉢のケツを一生けん命バタバタ…火種を入れるのを忘れた。
「いけね」
慌てて火種を入れ、十分に火が起こったところで、八五郎は薬を一つまみくべてみる。
「ゴホゴホ…! 煙りは出てくるけど、なかなか女房が出てきやがらねぇ。量が少ないのかな?」
とうとう自棄になった八五郎。薬を袋ごと放り込むと、途端に火事場まがいに煙がドーッ!!
「ゴホ…ゴホ…!!」
むせていると、裏口で戸をたたく音がする。
「あの野郎…恥ずかしいってんで裏口から来やがった。『そちゃ、女房。お熊じゃないか?』」
「違うよ、隣のお崎だよ。さっきからきな臭いのは、お前の家じゃないのかい?」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
【オチ・サゲ】
途端落ち(終わりの一言で話全体の結びがつくもの)
【噺の中の川柳・譬(たとえ)】
『忘れかね反魂丹を焚いてみる』
【語句豆辞典】
【反魂香】漢の孝武帝の故事から、死んだ人の魂を呼び戻し、その姿を煙の中に現わす香。
【反魂丹】 江戸時代から明治にかけて、よく知られた薬。解毒と。かくらんをなおす。特に越中富山のものが有名だった。
【この噺を得意とした落語家】
・八代目 三笑亭可楽
・八代目 林家正蔵

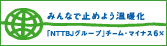
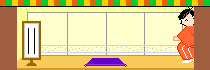
香をたくと、使者の姿が現れるという迷信が、この噺の中核となっている。
【あらすじ】
カーンカーン…カーンカーン…。
夜中に響く鐘の音。最近、相長屋へ越してきた浪人者が夜通し鉦をたたくので、八五郎は不眠症に悩まされいた。
「もう我慢できねぇ!」
ある晩、とうとう頭に来た八五郎は浪人の長屋へ怒鳴り込む。話を聞いた浪人は、自分の非を詫びると事情を説明し始めた。
「私は元、因州鳥取の藩に属していた、島田重三郎という者でございます。ある日、江戸勤番の話の種に、仲間数人と吉原遊廓へ行き、かの三浦屋高尾太夫に一目ぼれをしました」
高尾も重三郎の愛を受け入れ、二人は「末は夫婦に」という契りを立てる。その証として、重三郎は高尾に家宝の短刀を、高尾は重三郎に香箱を贈った。
「このお香は、魂を反すと書いて反魂香、またとない名香です」
ところが、重三郎が勤番明けで江戸を離れているうちに、高尾は時の仙台公・伊達綱宗に身受けされてしまったのだ…。
「私との操を守ろうとするあまり、高尾は綱宗公になびきません。とうとう頭にきた公は、高尾を三叉の船中で斬り殺してしまいました」
世の無常を感じた重三郎は、自ら脱藩して浪人となり、残りの人生を高尾の供養に費やそうと決意した…。
「なるほど、そんな訳があったんですかい…」
ジーンとなる八五郎。実は彼も、最近女房のお熊を病で亡くしたばかりで、重三郎の苦悩はよーく解る。
「で…その『反魂香』っていう奴なんですが、そいつを焚くと、本当に高尾が現れるんですかい?」
重三郎はそうだと言う。興味を持った八五郎は、一度目の前で焚いてくれと重三郎に頼み込む。香炉に香をくべると、なんだか妙な雰囲気がしてヒュードロドロ…!
『おまえは…島田重三さん…』
立ち上る煙の中に、高尾の姿が現れた。
「そちは女房、高尾じゃないか」
『取り交わせし反魂香、余り焚いて下さんすな…香の切れ目が、縁の切れ目…』
「焚くまいとは思えども、そなたの顔が見たき故。俗名、高尾。頓生菩提、南無阿弥陀仏ナムアミダブツ…」
一陣の風ともに、高尾の姿は掻き消えて…。
「物は相談なのですが、そのお香…、少し譲ってはくれませんか?」
「できません。これは高尾が現世に残した形見であって…」
「そうでしょうね。…ところで、そのお香、なんていうんでしたっけ?」
「反魂香です」
「ありがと!!」
自分で買えばいいんだ。そう思った八五郎は重三郎の長屋を飛び出した。そのまま薬屋へと駆けて行き、店じまいをしていた親父を捕まえると「アレをくれ!」。
当然、薬屋は何の事だか分からない。
「ワカラネェ? えーと…あれだなぁ、あれだ…あら?」
あんまり慌てていたせいで、八五郎は肝心の品物の名を忘却していたのだ。
「仕方がねぇ。そこの棚に並んでいる奴を、右から順に読んでくんねぇ」
並んでいるのは伊勢浅間の『万金丹』に、越中富山の…。
「反魂丹!? それだ!!」
…本当は反魂香である。だが、八五郎はそれに気づかず、反魂丹をしこたま買い込むと店を飛び出した。
「ありがてぇ、ありがてぇ!」
戸を突き破るようにして家へ飛び込み、火鉢を持ってくると炭をくべて団扇でバタバタ…。
「これでかかぁに会える! うれしいねぇ、かかぁはなんて言うかな?」
『おまえは、島田』…じゃない、それは隣だ。『おまえは、やもめの八五郎さん』かな。俺は「そちは女房、高」…それも隣だ。「そちは女房、お熊じゃないか」かな?。
楽しい想像をめぐらせ、火鉢のケツを一生けん命バタバタ…火種を入れるのを忘れた。
「いけね」
慌てて火種を入れ、十分に火が起こったところで、八五郎は薬を一つまみくべてみる。
「ゴホゴホ…! 煙りは出てくるけど、なかなか女房が出てきやがらねぇ。量が少ないのかな?」
とうとう自棄になった八五郎。薬を袋ごと放り込むと、途端に火事場まがいに煙がドーッ!!
「ゴホ…ゴホ…!!」
むせていると、裏口で戸をたたく音がする。
「あの野郎…恥ずかしいってんで裏口から来やがった。『そちゃ、女房。お熊じゃないか?』」
「違うよ、隣のお崎だよ。さっきからきな臭いのは、お前の家じゃないのかい?」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
【オチ・サゲ】
途端落ち(終わりの一言で話全体の結びがつくもの)
【噺の中の川柳・譬(たとえ)】
『忘れかね反魂丹を焚いてみる』
【語句豆辞典】
【反魂香】漢の孝武帝の故事から、死んだ人の魂を呼び戻し、その姿を煙の中に現わす香。
【反魂丹】 江戸時代から明治にかけて、よく知られた薬。解毒と。かくらんをなおす。特に越中富山のものが有名だった。
【この噺を得意とした落語家】
・八代目 三笑亭可楽
・八代目 林家正蔵

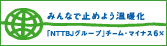
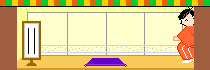














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます