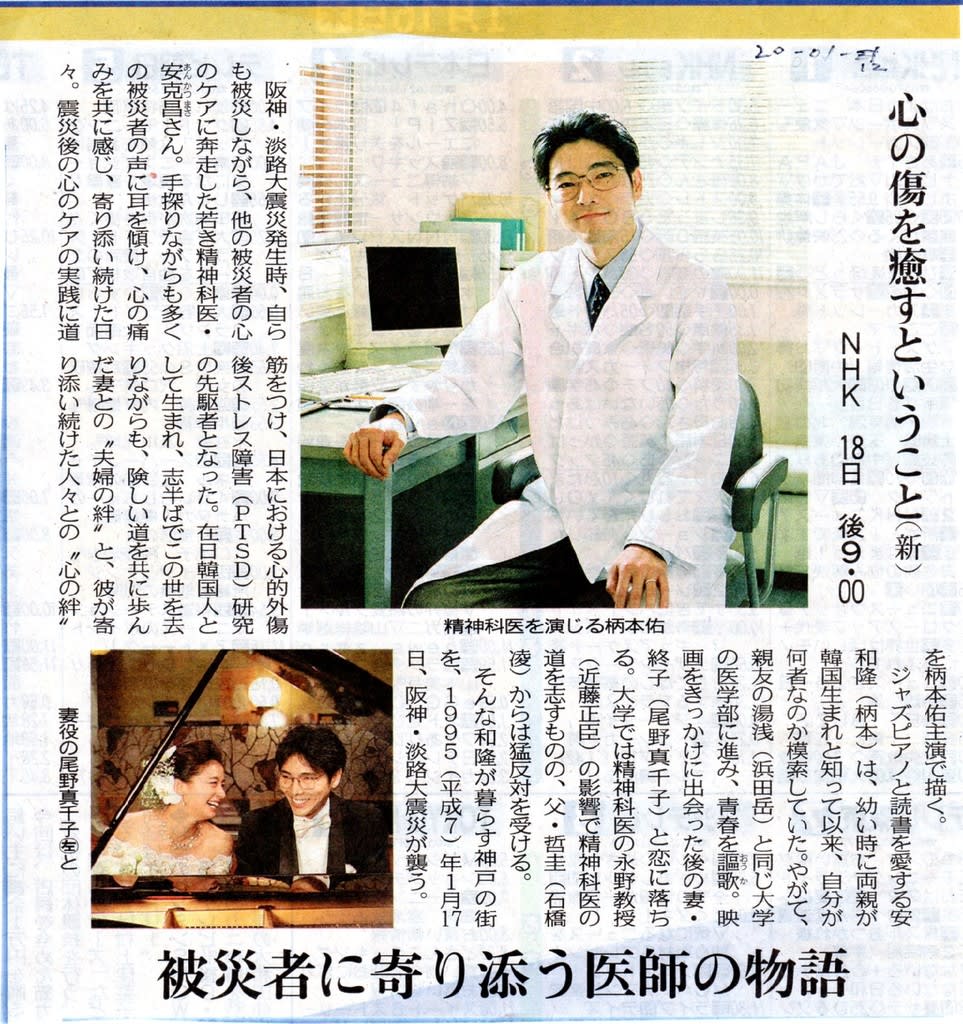予約していた本の準備が出来たと図書館からメールが来たので借り出してきた。今回の本も訳者あとがきや最終章だけを読んで返却ということになりそうだが、
最長一カ月期間延長して、中身の理解はさておいて速読の術(飛ばし読みのワザには自信がある(笑))を使って最後までをトライしてみる。
本屋の棚の前で立ち読みはしても、今の世の中の大変化についてやあるいは歴史を紐解いたあとの現代とこれからを著した
まず自分では買わない大部の外国の最新刊の翻訳書を、図書館から借り出すことにより、最短でも2週間は手元に置いておけるのはありがたい。
(次の予約者がいると2週間後に借出し延長手続きを図書館のインターネットサイトでしても、別の予約者がいるので延長不可と表示される)
スクエアー・アンド・タワー
世界を動かすのは、垂直に延びる階層制組織の頂点に立つ権力者か?
あるいは、水平に延びる草の根のネットワークをもつ革命家か?
「人的ネットワーク(スクエア)」と「階層制組織(タワー)」の視点から歴史を捉え直した、比類なき試み。
フリーメイソンからジョージ・ソロス、トランプ大統領まで
「いま最もすぐれた知性」による文明を見る眼
ルネサンス、印刷術、宗教改革、科学革命、産業革命、ロシア革命、ダヴォス会議、アメリカ同時多発テロ、リーマン・ショック、フリーメイソン、イルミナティ、メディチ家、ロスチャイルド家、スターリン、ヒトラー、キッシンジャー、フェイスブック、トランプ……
社会的ネットワークが世界を変えたと言ったならば、一握りの集団が世界を動かしているといった陰謀論を思い浮かべることだろう。
だが、歴史にネットワーク理論をもちこめば、さまざまな人物のつながりが、どのように世界を動かしてきたのかが明らかになる。
人類の歴史におけるさまざまな変化は、階層制の秩序に対する、社会的ネットワークに基づく挑戦とも言える。
イノベーションは異なる組織に属する人々のネットワークから生じ、アイデアはネットワーク内の弱いつながりを通して、水平方向に広がる。近代文明はそのネットワークの力によって、爆発的に発展したのである。
しかし一方で、国家に見られるような垂直にそびえ立つ階層制がなければ、ネットワークが内包する脆弱性ゆえに、社会は崩壊しかねない……
タイム誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれ、「いまもっとも優れた知性」と目される歴史学者が、ネットワークと階層制というかつてない視点で世界を読み解く!
暴力と不平等の人類史
本文600頁(ページ)に及ぶ大著。
著者は、ジニ係数と資産や所得の総額に対する割合とを用いて、人類史上経済的な不平等がどんな時に抑えられたかを浩瀚(こうかん)かつ克明に調べ上げる。その結果「4人の騎士」と称して、戦争、革命、国家の破綻、疫病(ペストの流行)の4つが不平等を軽減したという結論を得る。しかも古代アテナイを例外として、前近代における戦争や革命は、平等化に大して貢献しなかったと説く。2度の世界大戦とロシア革命や中国革命だけが不平等を抑える大きな力を示したというのだ。しかしこれらの力もそう長くは続かなかった。
近代以後の戦争や革命が恐るべき犠牲や破壊を伴ったことは自明だから、著者は、平等の達成と膨大な死や破壊とは後者が前者の条件をなすと言っているに等しい。雑駁(ざっぱく)に言えば、平等化の実現とは、みんなが豊かになったのではなく、みんなで貧しくなったことを意味する。ということは、裏を返せば、曲がりなりにも「平和な秩序」が保たれている時期には、資産や所得の格差は一貫して増大していたことになる。著者の筆致はあくまで冷静で、いろいろなケースに慎重な配慮を巡らしてはいるが、論理的にはどうしてもそうならざるを得ない。
そしてこの指摘は、自由貿易や金融資本の自由化が進み、グローバル化が行きつくところまで行った今日、私たちに明確な思い当たり感を与える。グローバル化が進むのは平和な時期に限られるからだ。事実、アメリカに代表される極端な富の集中という現実がグローバリズムによってもたらされたことは、否定しようがないのである。
読者の中にはかつてトマ・ピケティが『21世紀の資本』を著して、資本収益率が経済成長率を上回る場合には常に貧富の格差が開くと説いた事実を思い起こす人も多いだろう。これも踏まえて議論すべきは、巨大な暴力なしに「1%対99%」問題を解決する道はありうるかという1点なのだ。著者シャイデルは多くの社会改良案を紹介しつつ、それらに懐疑的なまなざしを注ぐ。評者もこの懐疑に暗澹(あんたん)たる気持ちとともに共感する。
ちなみに日本の場合には、「大災害」を「騎士」の仲間に加えてもらうべきだろう。(ウォルター・シャイデル著、鬼澤忍、塩原通緒訳/東洋経済新報社・5400円+税)
評・小浜逸郎(評論家)