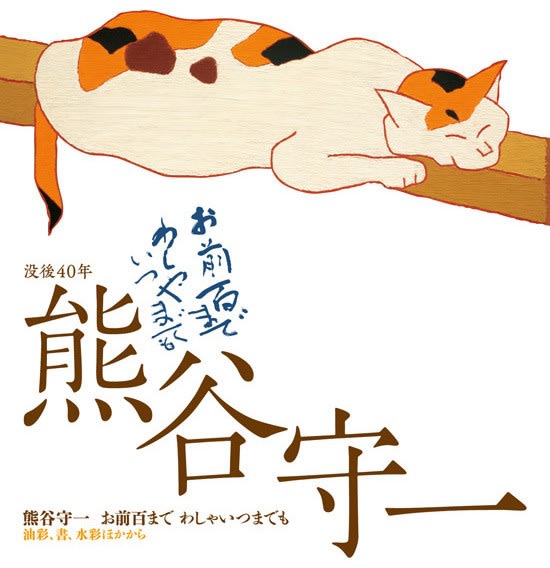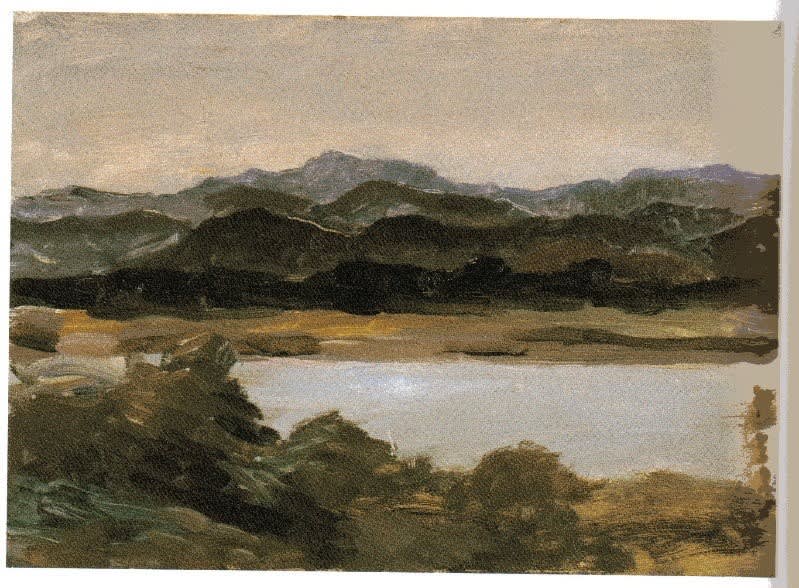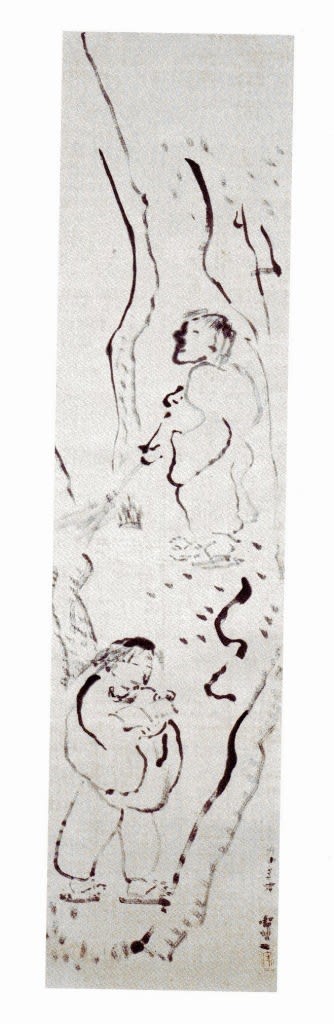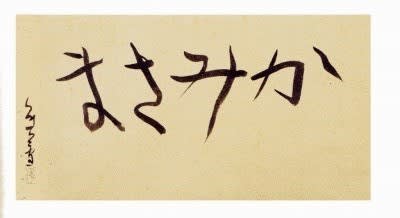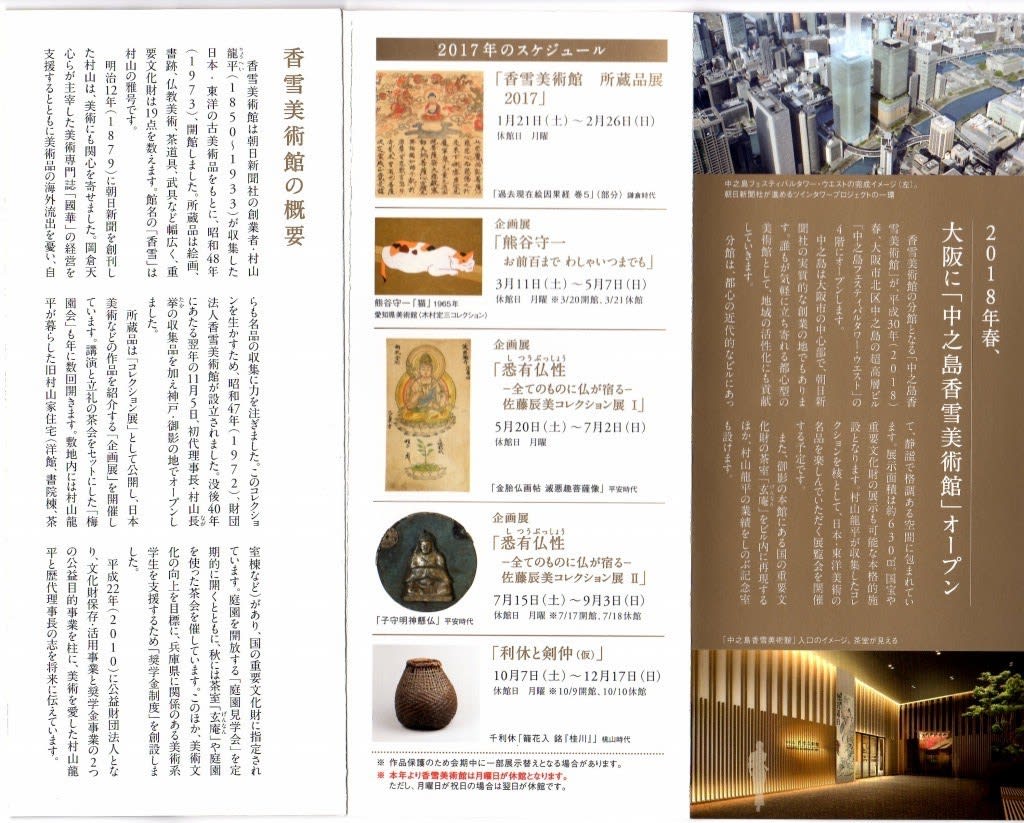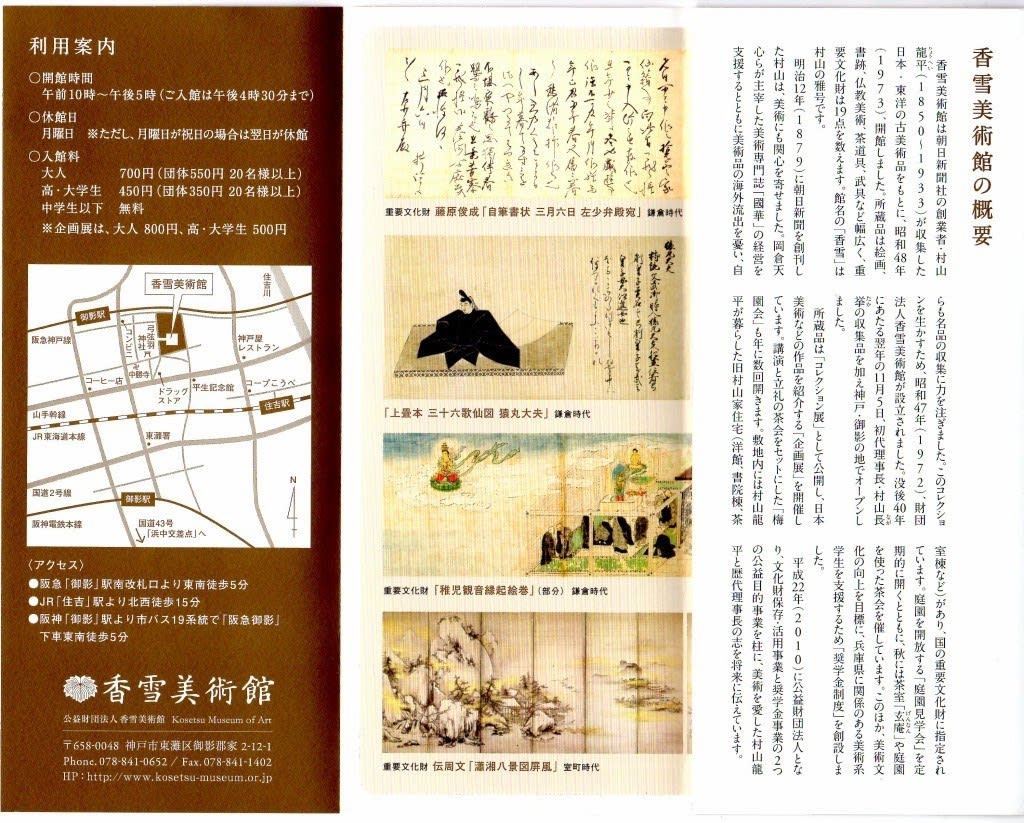|
大前研一 『 ニュースの視点 』
2012/12/21 #445
反省した東京電力。真実を語らせない周囲とのしがらみに問題
東京電力は14日、原子力部門の改革案を発表しました。
原子力部門から独立して安全対策を指導、徹底する社内組織の設置などを柱に据え、
過酷事故につながりかねない「負の連鎖」を断つ組織づくりを急ぎ、
早期の信頼回復を目指す考えとのことです。
私自身原子力改革監視委員会の一員として、改革案をまとめる作業を指示しました。
このプロジェクトの最終報告は来年の2月ということになっていますが、私が担当する範囲はすでに全て終了しています。
では、具体的に何をまとめたのか?
まず、私が東京電力に求めたことは、「全ての記者会見」の内容を
書き出して、今振り返ってみて正しかったのか否か総括することです。
その上で正しくないものについては、
1.能力不足のため
2.知っていたが言えなかった
3.外部からの圧力のため
のいずれかに分類させました。
そして、それぞれの場合どのように対応するべきかを指示しました。
同様に45年前に福島第一原発の安全性を地元住民に説明した資料を持ち寄らせ、それはどこまで正しかったのかを検証させました。
原因と今後の対策については、昨年10月私が発表した「福島第一原子力発電所事故から何を学ぶか」というレポートと全てを比べてもらい、
合意できない部分だけを個別に議論するという形を取りました。
議論の対象となったのは5つくらいのテーマだけでした。私はかなり明確に指示・依頼をするので、
プロジェクトとして取りまとめるのは相当早く終了したと自負しています。
改めて調べあげて分かったことは、当時は誰もが「嘘をついていた」ということです。
東電、保安院、官房長官はもちろん、真実を伝える役割を担うはずの大手マスコミも同様です。
3月11日の大地震の後、2日後には炉心溶融していたのに、3ヶ月経過しても燃料ピンの損傷などと報道していました。
結局、昨年の11月まで事実を認めることはありませんでした。
「当時は(自分たちも)嘘をついていた」とは言えないでしょうから、今回の東京電力の改革案について、
大手マスコミで取り上げられることはないと思います。
ある大手新聞社は「恐ろしくて“メルトダウン”という言葉は使えなかった」という類のことを言っていたそうですが、
私に言わせれば冗談ではありません。国が大変なときに何を言っているのかと思います。
ただ今回の改革案をまとめるにあたり、東京電力が自身の過ちを認め、しっかり反省したのは良かったことだと思います。
その意味で「改革監視」委員会としての役目も果たせたと感じます。
また、参画した東電のチーム員の働きも素晴らしいものでした。
事実を浮かび上がらせ、分析する能力は非常に高かったと思います。
結局、彼らに真実を語らせない外部のしがらみが大きな問題だったのです。
太字は管理人
☆この論考をどう読むかは人それぞれだが、外部から人間が参加する『外圧』のせいで、東電の内部が変化したことは事実のようだ。
外圧が入ってそれまでの上部の指示にメスが入って、溜まりにたまった膿が多少なりとも体外に出て、
一番ほっとしたのは、東電の普通の一般社員ではないだろうか。
それにしても人事権を握った会長、社長の「嘘をついてでも中を守れ」という指示を「逆命利君」の考えで反論し、
行動する社員がいなかった故に、福島県民の放射線被ばくは拡大した。
しかも福島第一、第二原発で生産された製品である電力を、福島県民は誰も使うような仕組みではなかった。
東電と関電が原発を稼動するなら、現存の所有原発を廃炉にして、東電は東京湾内に、関電は大阪湾内に新設しなくてはいけない。
それは人間として当然のことだろう。
生産者、消費者が共に製品リスクをもち、部外者には迷惑をかけないのは人間として最低守るべきことだ。
現状のままで原子力発電をやるのは禽獣にも悖る行いだし、平たく言えば『後ろめたい思いを持ちながら』毎日暮らすのは嫌だ。
|