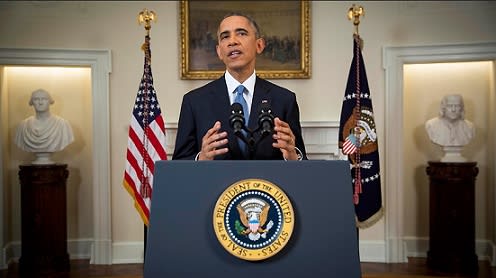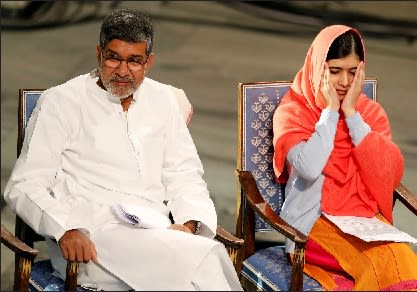(惨劇のあとに残された靴 “flickr”より By scrolleditorial https://www.flickr.com/photos/115313787@N08/15860525370/in/photolist-qaxkBY-qs1A2F-qsWewW-qaFcPz-qrUYNe-qrs6Gn-qs2nnS-qbsBsY-pvyLCt-qaDTzm-qaD7jG-qakcki-qrEXrA-pwkuuY-pwdQmL-qbGGBr-qbod1s-qqDqG1-qsVB4Z-qsKzen-qsS2vE-qbePiu-pw2Q7P-pvNkgQ-pw2Q5p-pw2Q4x-qsBcRt-pvsmMf-qaY5Y8-qaLFLi-qrUcgc-qrEbyt-puNCkf-qabhGm-q9ToMj-pusLEb-qrh57p-qpaZxo-qpaZso-qrotQW-q9TnPY-qrotrE-qrh4sZ-qa1vRX-qrh4iv-qpaYJ9-puGbj8-q9TndN-qrot3J-q9Tn3Y)
【「人間のすることではない」】
パキスタン北西部ペシャワルの学校で起きたイスラム武装勢力「パキスタンのタリバン運動(TTP)」による学校襲撃事件については、12月16日ブログ「血なまぐさい1日 シドニー、フィラデルフィア、そしてパキスタン・ペシャワル」(http://blog.goo.ne.jp/azianokaze/d/20141216)でも取り上げました。
死者は生徒132人を含む計148人、負傷者約120人に達したとのことで、死者数は2007年に同国のカラチで起きたベナジル・ブット元首相暗殺事件の139人を上回り、パキスタンでも最悪の事件となっています。
また、生き残った者の証言で、残忍なテロの有様が報じられています。
****教室で女性教師をイスに縛り火つける…武装集団****
・・・・「国境警備隊」の制服姿でカムフラージュしていた武装集団は、「神は偉大なり」と叫び、発砲しながら教室や講堂に向けて廊下を移動。
応急処置の講義などのために約400人が集まっていた講堂に入ると、至近距離から次々と生徒を撃った。
武装集団の1人が「ベンチの下にたくさん隠れているぞ」と叫ぶと、ベンチの下を乱射して回ったという。
教室を襲った武装集団の1人は、女性教師をイスに縛り付けて火をつけた。その後、生徒たちに向けて銃を乱射した。・・・・【12月18日 読売】
*****************
****「大切な人が死ぬのを見ろ」 一列に並ばされ撃たれる****
・・・・(ペシャワルの病院で治療を受けた14歳の)カーンさんによると、男は8人解放すると言い、「解放してほしい者は手を挙げろ」と言った。クラスのほぼ全員が手を挙げた。
「男たちは生徒8人を選び、クラスの前の黒板のそばに壁側を向いて立たせて、私たちに8人の方を見るように命令した」とカーンさんは振り返る。
屈強な男が教師を椅子に座らせ、教師にこう言った。「大切な人が死ぬのを見ろ。われわれの愛する人たちも同じやり方で殺されているんだ」
武装した男らは並んでいた生徒たちに発砲し、生徒たちは地面に崩れ落ちた。死んだ人もいたが、痛みにうめき声をあげてもだえ苦しんでいる人もいた。・・・・【12月18日 AFP】
*****************
「人間のすることではない」(軍の担当者)という惨劇ですが、もちろんTTPの犯人たちは異常者でもなければ、殺戮を楽しんでいる訳でもありません。
「大切な人が死ぬのを見ろ。われわれの愛する人たちも同じやり方で殺されているんだ」という言葉にもあるように、彼らが暮らす地域における掃討作戦において、TTPメンバーの家族らが政府軍によって殺害されているという現実もあり、今回の襲撃事件はそのことへの復讐でもあります。
【「今は国家が団結する時だ」】
しかし、このような残忍な、一般市民・子供を対象にしたテロ行為が許されるものでないことは言うまでもありません。
おそらくテロの頻度では世界でも最悪の状況にあるパキスタンでも、今回事件は衝撃をもってとらえられています。
パキスタン政府は16日、3日間の服喪期間を設けると発表し、就任当時はTTPとの和平交渉を模索していたシャリフ首相も「きょう流された私たちの子供たちのあらゆる血の一滴のため、報復する」、「われわれはテロ掃討のため、命をかけてきた。これからもテロリストに容赦はしない」と述べて、TTPへ強い姿勢で臨むことを表明しています。
首都イスラマバードの首相府、議会、最高裁などが立ち並ぶ「憲法大通り」の一角を100日余りにわたって占拠したていたイムラン・カーン党首率いる野党「愛国運動(PTI)」の反政府デモ隊も、「今は国家が団結する時だ」(カーン氏)と、抗議行動を中止しました。(抗議運動の長期化に伴う混迷に区切りをつけたという側面もありますが)
隣国アフガニスタンの“本家”タリバンも、TTPによる今回テロを批判しています。
****タリバーン系、非難声明 パキスタン学校襲撃「教えに反する」****
パキスタン北西部ペシャワルで学校が襲われ、児童生徒ら140人以上が殺害された事件で、犯行声明を出した反政府勢力パキスタン・タリバーン運動(TTP)に対する包囲網が狭まっている。
共闘関係にあるアフガニスタンの反政府勢力タリバーンも異例の非難声明を出した。
アフガン・タリバーンの声明は、報道担当者名で16日付で出された。犠牲者に哀悼の意を示し、「罪のない女性や子どもを殺すことはイスラム教の原則に反する。いかなるイスラム勢力もこの原則を守らなければならない」と、TTPへの名指しは避けつつ、強い調子で事件を批判した。
TTPはパキスタン側の組織だが、アフガン・タリバーンの指導者オマール最高幹部に忠誠を誓っている。
アフガン・タリバーンはTTPの支配地域で潜伏場所を確保し、アフガン側でのゲリラ戦に兵力を出してもらうなど密接な関係を保ってきた。
今回、同じ「タリバーン」を名乗るTTPが凶悪事件を起こしたことで、アフガン・タリバーンの幹部の一人は朝日新聞の電話取材に「我々への支持に影響が出なければいいが」と懸念を口にした。
パキスタン国内でも、今回のテロを機にTTP寄りだったイスラム原理主義政党からさえ、非難が出ている。シャリフ首相は17日、ペシャワルで各政党を招いた会議を開き、TTPに対する軍の掃討作戦への全面的な支持を取り付けた。
アフガン側でも事件後、TTPの最高幹部らの潜伏情報がある東部で米国の無人機攻撃があった。パキスタン軍トップのラヒル・シャリフ陸軍参謀長は17日、アフガンの首都カブールを訪れ、ガニ大統領にテロ対策での協力を要請した。【12月18日 朝日】
********************
「罪のない女性や子どもを殺すことは・・・」 男性の大人なら一般人でも殺していいのか?という話は今はやめておきましょう。
こうした反TTP機運を受けて、パキスタン政府・軍はTTPへの強硬な姿勢・行動をすでにとり始めています。
****テロ死刑囚の刑執行へ=一時中止措置を解除―パキスタン首相****
パキスタンのシャリフ首相は17日、過去にテロ事件に関与した死刑囚に対する刑執行を再開するよう関係当局に命じた。北西部ペシャワルの学校襲撃事件を受け、より強い姿勢でテロリストに臨むことを示した形だ。
シャリフ政権は野党や人権団体などからの批判を受けて死刑執行を中止しており、政府内の強硬派から「テロを助長する」と批判されていた。
今後はテロ事件に関与したとして死刑が確定した死刑囚に限り、執行を認めるという。
地元メディアによると、パキスタンの死刑囚は約8000人に上る。【12月17日 時事】
****************
実際、19日、パキスタン中部のファイサラバードの収容施設で、過去のテロ事件にかかわった死刑囚2人に絞首刑が執行されました。
“「パキスタン・タリバン運動」は19日、死刑執行に先立ち新たな声明を出し、死刑が執行された場合は報復すると宣言しており、さらなるテロや襲撃への懸念が高まっています。”【12月20日 NHK】
****タリバンに空爆20回「テロリスト57人殺害」****
パキスタン北西部ペシャワルで、反政府武装勢力「パキスタン・タリバン運動」(TTP)が学校を襲撃し、子供ら140人以上が死亡した事件を受けて、同国軍報道官は17日夜、事件発生後にTTPなどを標的とした空爆を20回行ったと発表した。
空爆は、隣国アフガニスタンとの国境沿いにある部族地域内で行われた。パキスタン軍は「テロリスト57人を殺害した」と説明している。(後略)【12月18日 読売】
*******************
【掃討にはアフガニスタンの協力が不可欠】
軍関係者は、TTPの最高指導者ムラー・ファズルラー師が、潜伏先の隣国アフガニスタンから今回襲撃を指揮していたとの見方を示しています。【12月19日 読売】
また、軍が傍受した通話記録によれば、犯行グループの「講堂にいた子供は全員殺しました。今度は何をしましょうか」と問いに、指示役が「軍人を殺して、自爆しろ」と命じたとのことですが、TTP関係者によると、この指示役は、アフガニスタン東部に潜伏し、ペシャワル周辺を担当するマンスール司令官だと言われています。【12月19日読売より】
いずれにしても、TTP幹部は隣国アフガニスタンに潜伏し、一方、アフガニスタンのタリバンはパキスタンのTTP支配地域に逃げ込む・・・という連携関係があり、TTPへの対応はアフガニスタンとの協調が必要になります。
****<パキスタン>テロ掃討機運高まる アフガン協力が不可欠****
パキスタン北西部ペシャワルで140人以上が死亡した学校襲撃事件を受け、国内でテロ組織掃討に向けた機運が高まっている。
だが、犯行を認めた武装勢力「パキスタン・タリバン運動(TTP)」は隣国アフガニスタンに潜伏しているとされ、掃討にはアフガンの協力が不可欠だ。自国もテロの脅威にさらされているアフガンとどう連携できるかが鍵となりそうだ。
「タリバンに『良い』も『悪い』もない。最後のテロリストを掃討するまで戦いは続く」。パキスタンのシャリフ首相は17日、全政党の代表者と協議後、テロ組織の掃討作戦継続を宣言。7日以内にテロ対策の国家行動計画を策定することを明らかにした。
また、2008年から続けてきた死刑の一時停止措置(モラトリアム)を「テロリスト」については解除する方針を決定。テロに対して改めて強硬姿勢を示した。
一方、首都イスラマバードでは、8月からシャリフ首相辞任を求めて反政府デモを続けていた野党「正義のための運動」が17日、「国家の結束が必要だ」としてデモの収束を宣言。挙国一致でテロ対策に取り組む姿勢を見せた。
パキスタンのシンクタンクCRSSのジーシャン・サラフディン上級研究員は「TTPは初めて子供を標的とし、一線を越えた。事件は国家の安全保障政策の転換点になるだろう」と話す。
TTPは北西部・北ワジリスタン管区を拠点としていたが、6月に始まった軍の掃討作戦でアフガンに逃走。最高指導者ファズルラ師もアフガンに潜伏しているとされる。
パキスタン軍トップのシャリフ陸軍参謀長は17日、カブールでアフガンのガニ大統領と会談し、テロ対策での協力を求めた。
だが、アフガンでは旧支配勢力タリバンのテロ攻撃が相次いでいるうえ、駐留外国軍の規模縮小も進む。アフガン軍は情報収集能力に欠けるとの指摘もあり、実効性のある作戦を遂行できるかは不透明だ。
サラフディン氏は「パキスタン軍は合同作戦や共同訓練などあらゆる手段を取ろうとするだろう」と指摘する。【12月18日 毎日】
********************
事件を機に、両国の協調が進み、イスラム過激派によるテロが沈静化するのであれば、せめてもの救いと言えます。
“今ようやく、パキスタンの軍人や政治家は、スンニ派過激主義者が自国の存続を脅かしていることをはっきり意識し始めたのかもしれない。”【12月17日付 英フィナンシャル・タイムズ紙】ということですが、一方で、パキスタン国軍の一部、特に諜報機関ISIがアフガニスタンでタリバンを支援している(というか、指示している)ということもあります。
このあたりの関係を整理しないと、パキスタンとアフガニスタンの協調というのは形だけのものになってしまいます。
【新たな襲撃事件が起きる可能性も】
ただ、当面は軍の掃討作戦が激化すれば、それへの報復テロもまた激化することが予想されます。
****パキスタン学校襲撃の武装勢力、他校も標的か****
パキスタン北西部ペシャワルの軍営学校を襲撃した反政府武装勢力「パキスタン・タリバン運動」(TTP)が、さらにテロを展開する構えを見せている。
他の学校を攻撃対象にしているとみられ、テロ続発の懸念が高まっている。
米ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、TTP幹部は18日、「さらに多くの学校や他の民間の標的を襲撃する」「我々は無差別攻撃をする」などと、ビデオメッセージで述べたとされる。
パキスタンには、襲撃された学校と同様に軍が運営する教育施設が140か所以上あり、新たな襲撃事件が起きる可能性がある。(後略)【12月19日 読売】
*****************
掃討作戦を進めれば、現実には不可避的に家族・関係者などの犠牲者も増大します。
「大切な人が死ぬのを見ろ。われわれの愛する人たちも同じやり方で殺されているんだ」・・・TTPのテロは断じて容認できませんし、話し合いが成立するような状況になく、軍による掃討しか道がないとも思います。ただ、ないものねだりかもしれませんが、それに伴う犠牲者の増大は受け入れざるを得ないのか・・・整理しきれない部分も残ります。