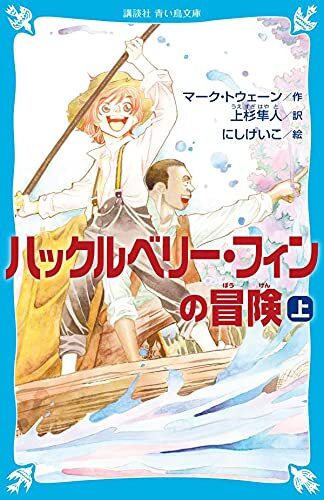昨日、一昨日とF・スコット・フィッツジェラルド、上岡伸雄訳『ラスト・タイクーン』(作品社)を紹介したが、もう一か所どうしてもご紹介したいところがあり、本日のGetUpEnglishもこの作品から取り上げてみたい。
エピソード12の冒頭に、歳を取りつつある主人公の感慨が表現された、味わい深い描写がある。
As Stahr walked back from the commissary, a hand waved at him from an open roadster. From the heads showing over the back he recognized a young actor and his girl, and watched them disappear through the gate, already part of the summer twilight. Little by little he was losing the feel of such things, until it seemed that Minna had taken their poignancy with her; his apprehension of splendor was fading so that presently the luxury of eternal mourning would depart. A childish association of Minna with the material heavens made him, when he reached his office, order out his roadster for the first time this year. The big limousine seemed heavy with remembered conferences or exhausted sleep.
このhis apprehension of splendorについて、訳者上岡伸雄は「編訳者解説」で次のように述べている。
エピソード12の最初の段落、「華美なるものを味わう心」という一節があるが、これは元の原稿ではhis apprehension of splendorであり、訳すすれば「華美なものへの不安である。しかし、これでは意味が通らないと考えたウィルソンはapprehensionはappreciationの間違いであると推測し、そのように直した。それをケンブリッジ版は元に戻したわけだが、私もそれでは意味が通らないように思う。そこで、この部分はウィルソン版にしたがうことにした。
ウィルソンとはアメリカの著名は作家、批評家のEdmund Wilson(1895-1972)だ。フィッツジェラルドの畏友であったこの人物はフィッツジェラルドの手書き原稿とタイプ原稿、さらにはメモ書きなどを入手して、そこから取捨選択、編集する形で、『ラスト・タイクーン』を小説の形に整えて1941年にスクリブナーズ社から刊行したのだ。
訳者上岡伸雄はこのあたりの事情を十分に理解したうえで、フィッツジェラルドの遺稿を再現した版からの翻訳を仕上げている。
この訳者の語学力と文学に関する知識だからこそできることだ。
翻訳者として実に誠実な姿勢であるし、すべての翻訳者が見習うべきことである。
この部分、上岡はどう訳しているか? ぜひ作品社の上岡伸雄訳『ラスト・タイクーン』でご確認いただきたい。
なお、appreciationであるが、このように使われる。
○Practical Example
Finally, I feel that I cannot conclude my message without showing my intense appreciation for your work once again. Thank you very much for allowing me the opportunity to translate your tour de force. It was a great honor for me.
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/d85a02611a01e0c099a470b85b8d3db7
覚えておこう。
F・スコット・フィッツジェラルド
上岡伸雄編訳
本体2,800円
46判上製
ISBN978-4-86182-827-0
発行 2020.10
【内容】
ハリウッドで書かれたあまりにも早い遺作、著者の遺稿を再現した版からの初邦訳。映画界を舞台にした、初訳三作を含む短編四作品、西海岸から妻や娘、仲間たちに送った書簡二十四通を併録。最晩年のフィッツジェラルドを知る最良の一冊、日本オリジナル編集!
(…)本書に収めた「監督のお気に入り」、「最後のキス」、「体温」の三作など、フィッツジェラルドはハリウッドを舞台にした短編の執筆を試みている。これらは生前出版されなかったが、並行して一九三九年秋から長編『ラスト・タイクーン』を書き始め、短編で扱った素材を長編のほうに投入している。この久々の長編に対して彼がいかに情熱を傾けていたかも、手紙を通して伝わってくるだろう。なにしろ【あの:傍点】フィッツジェラルドが酒を断って取り組んでいたのだ。
本書は、このように手紙から彼のハリウッドでの生活をたどりつつ、その生活から生まれ出た作品を味わえるように構成されている。(「編訳者解説」より)
【内容目次】
ラスト・タイクーン
ハリウッド短編集
クレージー・サンデー
監督のお気に入り
最後のキス
体温
ハリウッドからの手紙
スコッティ・フィッツジェラルド宛 一九三七年七月
テッド・パラモア宛 一九三七年十月二十四日
ジョゼフ・マンキーウィッツ宛 一九三八年一月二十日
ハロルド・オーバー宛 一九三八年二月九日
デヴィッド・O・セルズニック宛 一九三九年一月十日
ケネス・リッタウアー宛 一九三九年九月二十九日
シーラ・グレアム宛 一九三九年十二月二日
マックスウェル・パーキンズ宛 一九四〇年五月二十日
ゼルダ・フィッツジェラルド宛 一九四〇年七月二十九日
ジェラルド&セアラ・マーフィ宛 一九四〇年夏
(ほか全24通)
編訳者解説
F・スコット・フィッツジェラルド(Francis Scott Fitzgerald)
1896年生まれ。ヘミングウェイ、フォークナーらと並び、20世紀前半のアメリカ文学を代表する作家。1920年、24歳のときに『楽園のこちら側』でデビュー。若者の風俗を生々しく描いたこの小説がベストセラーとなって、若い世代の代弁者的存在となる。同年、ゼルダ・セイヤーと結婚。1922年、長編第二作『美しく呪われた人たち』を刊行。1925年には20世紀文学を代表する傑作『グレート・ギャツビー』を発表した。しかし、その後は派手な生活を維持するために短編小説を乱発し、才能を擦り減らしていく。1934年、10年近くをかけた長編『夜はやさし』を発表。こちらをフィッツジェラルドの最高傑作と評価する者も多いが、売り上げは伸びず、1930年代後半からはハリウッドでシナリオを書いて糊口をしのぐ。1940年、心臓発作で死去。享年44。翌年、遺作となった未完の長編小説『ラスト・タイクーン』(本書)が刊行された。
上岡伸雄(かみおか・のぶお)
1958年生まれ。アメリカ文学者、学習院大学教授。訳書に、アンドリュー・ショーン・グリア『レス』、ヴィエト・タン・ウェン『シンパサイザー』(以上早川書房)、F・スコット・フィッツジェラルド『美しく呪われた人たち』(作品社)、ジョージ・ソーンダーズ『リンカーンとさまよえる霊魂たち』(河出書房新社)、シャーウッド・アンダーソン『ワインズバーグ、オハイオ』(新潮文庫)などがある。著書、編書も多数。
F・スコット・フィッツジェラルド、上岡伸雄訳『ラスト・タイクーン』(作品社)、とてもすばらしい。興奮して読み進めている。
当時の絢爛豪華なハリウッドの様子が実にドラマチックに描かれている。
エピソード6の以下の描写を見てみよう。
Under the moon the back lot was thirty acres of fairyland — not because the locations really looked like African jungles and French chateaux and schooners at anchor and Broadway by night, but because they looked like the torn picture books of childhood, like fragments of stories dancing in an open fire. I never lived in a house with an attic, but a back lot must be something like that, and at night of course in an enchanted distorted way, it all comes true.
月光の下、野外撮影場(バックロット)は三十エーカーのおとぎの国だった――この場所が本当にアメリカのジャングルのように見えるとか、フランスのお城や錨を下ろしたスクーナー船、夜のブロードウェイのように見えるからというわけではない。むしろ子供時代の絵本が破れて散らばり、野外の炎のなかでたくさんの物語の断片が踊っているように見えるからだ。わたしは屋根裏部屋のある家に住んだことはないが、住んだことがあるとしたら、野外撮影場(バックロット)はそのようなものに違いない。もちろん、夜になれば魔法によって歪みが生じ、そのすべてが本物になる。
in an enchanted distorted wayとenchanted のdistorted形容詞がふたつ-edで韻を踏んで出てくるあたりが文学作品という感じがするが、上岡訳では実に見事に処理されている。
動詞enchant(うっとりさせる、魅了する、魔法にかける)は次のように使われることもある。
○Practical Example
Vision was enchanted with the young, charmingly Wanda.
「ヴィジョンは若くて初々しいワンダに魅せられた」
『ラスト・タイクーン』、驚きの発見がいっぱいの作品だ。ぜひご覧いただきたい。
F・スコット・フィッツジェラルド
上岡伸雄編訳
本体2,800円
46判上製
ISBN978-4-86182-827-0
発行 2020.10
【内容】
ハリウッドで書かれたあまりにも早い遺作、著者の遺稿を再現した版からの初邦訳。映画界を舞台にした、初訳三作を含む短編四作品、西海岸から妻や娘、仲間たちに送った書簡二十四通を併録。最晩年のフィッツジェラルドを知る最良の一冊、日本オリジナル編集!
(…)本書に収めた「監督のお気に入り」、「最後のキス」、「体温」の三作など、フィッツジェラルドはハリウッドを舞台にした短編の執筆を試みている。これらは生前出版されなかったが、並行して一九三九年秋から長編『ラスト・タイクーン』を書き始め、短編で扱った素材を長編のほうに投入している。この久々の長編に対して彼がいかに情熱を傾けていたかも、手紙を通して伝わってくるだろう。なにしろ【あの:傍点】フィッツジェラルドが酒を断って取り組んでいたのだ。
本書は、このように手紙から彼のハリウッドでの生活をたどりつつ、その生活から生まれ出た作品を味わえるように構成されている。(「編訳者解説」より)
【内容目次】
ラスト・タイクーン
ハリウッド短編集
クレージー・サンデー
監督のお気に入り
最後のキス
体温
ハリウッドからの手紙
スコッティ・フィッツジェラルド宛 一九三七年七月
テッド・パラモア宛 一九三七年十月二十四日
ジョゼフ・マンキーウィッツ宛 一九三八年一月二十日
ハロルド・オーバー宛 一九三八年二月九日
デヴィッド・O・セルズニック宛 一九三九年一月十日
ケネス・リッタウアー宛 一九三九年九月二十九日
シーラ・グレアム宛 一九三九年十二月二日
マックスウェル・パーキンズ宛 一九四〇年五月二十日
ゼルダ・フィッツジェラルド宛 一九四〇年七月二十九日
ジェラルド&セアラ・マーフィ宛 一九四〇年夏
(ほか全24通)
編訳者解説
F・スコット・フィッツジェラルド(Francis Scott Fitzgerald)
1896年生まれ。ヘミングウェイ、フォークナーらと並び、20世紀前半のアメリカ文学を代表する作家。1920年、24歳のときに『楽園のこちら側』でデビュー。若者の風俗を生々しく描いたこの小説がベストセラーとなって、若い世代の代弁者的存在となる。同年、ゼルダ・セイヤーと結婚。1922年、長編第二作『美しく呪われた人たち』を刊行。1925年には20世紀文学を代表する傑作『グレート・ギャツビー』を発表した。しかし、その後は派手な生活を維持するために短編小説を乱発し、才能を擦り減らしていく。1934年、10年近くをかけた長編『夜はやさし』を発表。こちらをフィッツジェラルドの最高傑作と評価する者も多いが、売り上げは伸びず、1930年代後半からはハリウッドでシナリオを書いて糊口をしのぐ。1940年、心臓発作で死去。享年44。翌年、遺作となった未完の長編小説『ラスト・タイクーン』(本書)が刊行された。
上岡伸雄(かみおか・のぶお)
1958年生まれ。アメリカ文学者、学習院大学教授。訳書に、アンドリュー・ショーン・グリア『レス』、ヴィエト・タン・ウェン『シンパサイザー』(以上早川書房)、F・スコット・フィッツジェラルド『美しく呪われた人たち』(作品社)、ジョージ・ソーンダーズ『リンカーンとさまよえる霊魂たち』(河出書房新社)、シャーウッド・アンダーソン『ワインズバーグ、オハイオ』(新潮文庫)などがある。著書、編書も多数。
F・スコット・フィッツジェラルドのあまりに早い遺作となってしまったThe Last Tycoonが著者の遺稿を再現した版から上岡伸雄訳で作品社より初邦訳刊行された。
今読んでいるが、大変読み応えのあるすぐれた訳なので、今日と明日のGetUpEnglishはこの作品の読みどころを紹介してみる。
第1章でモンロー・スターについて語られる場面だ。
He had flown up very high to see, on strong wings, when he was young. And while he was up there he had looked on all the kingdoms, with the kind of eyes that can stare straight into the sun. Beating his wings tenaciously— finally frantically — and keeping on beating them, he had stayed up there longer than most of us, and then, remembering all he had seen from his great height of how things were, he had settled gradually to earth.
彼は若いときに強い翼を羽ばたいて、とても高く飛んだのだ。そして太陽をまともに見つめられる目で、あらゆる王国を見下ろした(新約聖書ルカ伝5~6節、悪魔がキリストに世界中の国々を見せ、「この国々の権力と栄光をあげよう」と言った話より)。粘り強く――最後は死に物狂いに――翼を羽ばたき続け、私たちの誰よりも長く空にとどまった。そして、その高所から物事の仕組みについて見たことをすべて記憶し、ゆっくりと地上に降りてきたのである。
このあたりの訳文に、モンロー・スターがいかにして冷徹な経営者となり、利益に対する鋭い嗅覚を磨いていくかがよく表れている。
franticallyはぜひ覚えておきたい。
次のように使われる。
○Practical Example
Avengers were frantically searching for Thanos and the infinity stones and finally found he was in a farm on the planet.
「アベンジャーズはサノスとインフィニティ・ストーンを必死に探し、彼がその惑星の農園にいることをつかんだ」
『ラスト・タイクーン』はこのあとの描写が実にすばらしい。
The motors were off, and all our five senses began to readjust themselves for landing. I could see a line of lights for the Long Beach Naval Station ahead and to the left, and on the right a twin-kling blur for Santa Monica. The California moon was out, huge and orange over the Pacific. However I happened to feel about these things — and they were home, after all — I know that Stahr must have felt much more. These were the things I had first opened my eyes
on, like the sheep on the back lot of the old Laemmle studio; but this was where Stahr had come to earth after that extraordinary illuminating flight where he saw which way we were going, and how we looked doing it, and how much of it mattered. You could say that this was where an accidental wind blew him, but I don’t think so. I would rather think that in a “long shot” he saw a new way of measuring our jerky hopes and graceful rogueries and awkward sorrows, and that he came here from choice to be with us to the end. Like the plane coming down into the Glendale airport, into the warm darkness.
ぜひ上岡訳でお楽しみいただきたい。
F・スコット・フィッツジェラルド
上岡伸雄編訳
本体2,800円
46判上製
ISBN978-4-86182-827-0
発行 2020.10
【内容】
ハリウッドで書かれたあまりにも早い遺作、著者の遺稿を再現した版からの初邦訳。映画界を舞台にした、初訳三作を含む短編四作品、西海岸から妻や娘、仲間たちに送った書簡二十四通を併録。最晩年のフィッツジェラルドを知る最良の一冊、日本オリジナル編集!
(…)本書に収めた「監督のお気に入り」、「最後のキス」、「体温」の三作など、フィッツジェラルドはハリウッドを舞台にした短編の執筆を試みている。これらは生前出版されなかったが、並行して一九三九年秋から長編『ラスト・タイクーン』を書き始め、短編で扱った素材を長編のほうに投入している。この久々の長編に対して彼がいかに情熱を傾けていたかも、手紙を通して伝わってくるだろう。なにしろ【あの:傍点】フィッツジェラルドが酒を断って取り組んでいたのだ。
本書は、このように手紙から彼のハリウッドでの生活をたどりつつ、その生活から生まれ出た作品を味わえるように構成されている。(「編訳者解説」より)
【内容目次】
ラスト・タイクーン
ハリウッド短編集
クレージー・サンデー
監督のお気に入り
最後のキス
体温
ハリウッドからの手紙
スコッティ・フィッツジェラルド宛 一九三七年七月
テッド・パラモア宛 一九三七年十月二十四日
ジョゼフ・マンキーウィッツ宛 一九三八年一月二十日
ハロルド・オーバー宛 一九三八年二月九日
デヴィッド・O・セルズニック宛 一九三九年一月十日
ケネス・リッタウアー宛 一九三九年九月二十九日
シーラ・グレアム宛 一九三九年十二月二日
マックスウェル・パーキンズ宛 一九四〇年五月二十日
ゼルダ・フィッツジェラルド宛 一九四〇年七月二十九日
ジェラルド&セアラ・マーフィ宛 一九四〇年夏
(ほか全24通)
編訳者解説
【内容目次】
F・スコット・フィッツジェラルド(Francis Scott Fitzgerald)
1896年生まれ。ヘミングウェイ、フォークナーらと並び、20世紀前半のアメリカ文学を代表する作家。1920年、24歳のときに『楽園のこちら側』でデビュー。若者の風俗を生々しく描いたこの小説がベストセラーとなって、若い世代の代弁者的存在となる。同年、ゼルダ・セイヤーと結婚。1922年、長編第二作『美しく呪われた人たち』を刊行。1925年には20世紀文学を代表する傑作『グレート・ギャツビー』を発表した。しかし、その後は派手な生活を維持するために短編小説を乱発し、才能を擦り減らしていく。1934年、10年近くをかけた長編『夜はやさし』を発表。こちらをフィッツジェラルドの最高傑作と評価する者も多いが、売り上げは伸びず、1930年代後半からはハリウッドでシナリオを書いて糊口をしのぐ。1940年、心臓発作で死去。享年44。翌年、遺作となった未完の長編小説『ラスト・タイクーン』(本書)が刊行された。
上岡伸雄(かみおか・のぶお)
1958年生まれ。アメリカ文学者、学習院大学教授。訳書に、アンドリュー・ショーン・グリア『レス』、ヴィエト・タン・ウェン『シンパサイザー』(以上早川書房)、F・スコット・フィッツジェラルド『美しく呪われた人たち』(作品社)、ジョージ・ソーンダーズ『リンカーンとさまよえる霊魂たち』(河出書房新社)、シャーウッド・アンダーソン『ワインズバーグ、オハイオ』(新潮文庫)などがある。著書、編書も多数。
すでにGetUpEnglishで何度か紹介したが、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の1枚と言われる『サルバトール・ムンディ』について詳細に論じたBen Lewis, The Last Leonardo The Secret Lives of the World’s Most Expensive Paintingが、昨年発刊された。
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/50faf1933375ca88c86444cc2b9976e2
その本のペーパー版がこの度、副題を‘A Masterpiece, A Mystery and the Dirty World of Art’として刊行された。
本日のGetUpEnglishはその本に関するニュースの一部を読んでみよう。
https://www.harpercollins.co.uk/9780008313449/the-last-leonardo-a-masterpiece-a-mystery-and-the-dirty-world-of-art/
Ben Lewis’s book The Last Leonardo, subtitled ‘A Masterpiece, A Mystery and the Dirty World of Art’, has now appeared in paperback after its publication in hardcover last year. It makes a riveting read, no less so because the painting itself, an image of Christ as the Salvator Mundi, has yet again vanished. Some people say it is currently locked away in duty-free storage in Switzerland. Others, a tad less plausibly, assert that it is on display in the private yacht of Crown Prince Mohammed bin Salman, the de facto ruler of Saudi Arabia.
ベン・ルイスの『最後のダ・ヴィンチ』は昨年ハードカバー版が刊行されているが、このたび「傑作、神秘、汚れた美術界」の副題を添えてペーパー版が発売された。本書を非常に刺激的な読み物にしているのは、ほかでもなくここで扱われている救世主キリストを描いた『サルバトール・ムンディ』がふたたび消えてしまったからだ。スイスの非課税の倉庫に保管されているという者もいれば、ちょっと信じられないが、サウジアラビアの実質上の指導者であるムハンマド・ビン・サルマーン皇太子の個人のボートに展示されていると力説する者もいる。
no lessは「ほかならぬ、まさしく」。no less so becauseで、「まさしくそうであるのは、…であるからだ」
yet againは「もう一度, またしても (once more) 《強めた言い方》」(『研究社ルミナス英和』)
『ルミナス』の次の用例を参照。
I begged him yet again not to go. 私は彼にもう一度行かないでくれと頼んだ.
a tadは「[a ~ として普通は副詞的に] 少量, 少し (a bit)」(『ルミナス』)
これだけの英文のなかにも、勉強になる表現がたくさんある。
ベン・ルイスのこの本のハードカバーとペーパー版を読み比べてみたが、この度刊行されるペーパー版には膨大な加筆と修正が施されていて、別物といってもいいくらいだ。
ハードカバー刊行以後、多くのことが明らかになったので、それにあわせてあらゆる加筆、修正が施されたのだと思う。
lethargicは「無気力な、不活発な」
今日のGetUpEnglishはこの語を学習する。
○Practical Example
"I feel so lethargic today. I don't want to do anything."
"You don’t have to do anything today. I can do everything, Today is Mother’s Day."
「今日は何となくだるくて何もしたくない」
「何もしなくていいよ。わたしが全部やる。今日は母の日」
●Extra Point
ロックダウンのあいだ、新しい本の企画を練るにあたって、購読しているAsahi Weekly, The Japan Times Alpha, English Journal, CNN English Expressなどに前よりよく目を通している。English Journal 6月号の「今月のEJ単語帳」にこの語が取り上げられていた。
◎Extra Example
I feel lethargic when I sleep to long.
「わたしは寝すぎるとけだるさを感じる」
English Journalがありがたいのは、各月号のcontentsに使われている語や表現をこうしてまとめてくれていることだ。このlethargicも出てきたページが記されていて、その使い方が音声とあわせて確認できるようになっている。
自分の知らない語を覚えると同時に(わたしの場合は絶対どこかで見て、聞いているが、忘れてしまっている語をふたたび覚えるということになる)、使えるようにすることが大事だ。そしてみなさんも経験があると思うが、一度覚えると、それが使いたくて何度も使ってしまうので、そうではなく、類義語とあわせて書いて話せるレベルに持っていきたい。
lethargicであれば、dull, languid, weary, drowsyあたりとあわせて覚えておきたい。
coronavirus関連の記事がつづいたので、今日のGetUpEnglishはこのニュース記事から表現を紹介する
Led Zeppelinは1971 年のヒット曲 “Stairway to Heaven“は盗作であると訴えられていたが、やり直し審でふたたび勝訴した。
○Practical Example
A federal appeals court on Monday restored a jury verdict that found Led Zeppelin did not steal “Stairway to Heaven.”
「米連邦控訴裁判所は月曜日、レッド・ツェッペリンの『天国への階段』は盗作でないとする(2016年の裁判の)陪審員の評決を支持した」
restoreは「支持する」。
●Extra Point
ニュースは次のようにつづけている。
◎Extra Example
The 9th U.S. Circuit Court of Appeals in San Francisco handed the major win to guitarist Jimmy Page and singer Robert Plant and dealt a blow to the estate of Randy Wolfe of the band Spirit. The estate claimed that the 1971 mega-hit “Stairway to Heaven” violated the copyright of the 1968 song “Taurus.”
「サンフランシスコの第9巡回区控訴裁は、ギタリストのジミー・ペイジとボーカリストのロバート・プラントを支持し、スピリットのランディ・ウルフの相続管財人を退けた。同管財人は1971年の大ヒット曲『天国への階段』はスピリットが1968年に発表した『タウラス』の盗作であるとしていた」
The 9th U.S. Circuit Court of Appeals in San Franciscoは上のA federal appeals courtのこと。
deal a blow to...は「打撃を与える」だが、この状況では試訳くらいに処理すればよいだろう。
今はこの言葉がいちばん人々の話題に出ているかもしれない。
lockdownは「封鎖」
今日のGetUpEnglshはこの語を学習する。
○Practical Example
Wuhan has been on lockdown since late January.
「武漢は1月下旬から封鎖状態にある」
●Extra Point
もう一例。
◎Extra Example
Italy expanded a lockdown to cover the entire country to contain the spread of the virus.
「イタリアはウィルスの蔓延を封じ込めるために、全土を封鎖した」
暗い、大変な時ですが、希望を持ちましょう。
この週末は外に出られないので、花見にも行けませから、大好きなお花屋さん飯田橋花楽里で花を買って帰りました。
https://ja-jp.facebook.com/karakuri.tokyo/
ガーベラが好きなので、それにしました。
gerbera, インターネットでチェックしてみたら、こんなことが書かれていました。
The gerbera flower symbolizes happiness and joy. These colorful flowers are perfect reminders for us to seize the day and do something fun and adventurist. The Gerbera flower will bring in sunshine and warmth into your home no matter how dark your day might seem.
The Gerbera flower will bring in sunshine and warmth into your home no matter how dark your day might seem.--今の時代にぴったりのお花です。
loyalは「忠実な」ですが、状況によっていろんな訳し方ができるので注意しよう。
今日のGetUpEnglishはこの表現を学習する。
○Practical Example
Natasha had told her sister Yelena to stay back at home, but of course, she had refused. Yelena was, above all else, stubbornly loyal.
「ナターシャは妹エレーナに家にいるように言った。もちろん妹はしたがわなかった。頑固なほど忠実なのだ」
Black Widow, コロナウィルスの影響により、封切が延期されたとのこと。すごく残念ですが、ノベライズは予定通りDVD発売に合わせて出版予定です。
https://theriver.jp/black-widow-postponed/
●Extra Point
もう一例。状況によっては「信頼できる」と訳せる。
◎Extra Example
Because Emi is a loyal editor, I can defer everything to her judgment.
「えみは信頼できる編集者だから、すべて彼女の判断に任せることができる」
この映像を見たら、とても元気が出ました。
https://www.youtube.com/watch?v=L9pUP3es63w
Bon Joviの“Livin’ On A Prayer”(1986), こんないい曲だったのですね。
本日のGetUpEnglishはこの曲のサビの部分を学習しましょう。
She says: We've got to hold on to what we've got
'Cause it doesn't make a difference
if we make it or not
We've got each other
and that's a lot for love
We'll give it a shot
彼女は言う
つかんだものを離すわけにはいかないの
うまくいくかどうかはどっちでもいい
わたしたち、おたがいを手に入れた
愛のためにはそれで十分
やるしかない
Wooh
We're half way there
Woh-oh
Livin' on a prayer
Take my hand and we'll make it I swear
Woh-oh
Livin' on a prayer
まだ道の途中
希望を支えに生きていく
この手を取ってちょうだい、そしたらきっとうまくいく
希望を支えに生きていく
give something [doing] a shotは「~に挑戦する、(むずかしいこと)を試みる、やってみる」
○Practical Example
I don't think I can get the job, but I've decided to give it a shot anyway.
「その仕事がもらえるとは思わないけど、とにかく挑戦することにした」
『サルバトール・ムンディ』 (Salvator Mundi 世界の救世主の意) は、イタリアの美術家レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた油彩画。青いローブをまとったイエス・キリストの肖像画。
2017年11月15日にクリスティーズのオークションにかけられ、手数料を含めて4億5031万2500ドル(当時のレートで約508億円)で落札された。この額は、2015年に落札されたパブロ・ピカソの「アルジェの女たち バージョン0」の1億7940万ドル(約200億円)を抜き、これまでの美術品の落札価格として史上最高額となった。(Wikipediaより)
この話題の絵について深く分析した話題書がある。
https://www.amazon.co.uk/Last-Leonardo-Ben-Lewis/dp/0008313415
今日のGetUpEnglishも10月4日、5日、6日、11月2日、12月8日につづいて、この本にある表現を紹介する。
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/2203ac6af0af22d8f8fb301b8714412a
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/b64c8d0b72903b49ebb3d1582b9b7f3d
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/74dbed6d575d95180c4ce11fe666beec
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/2bdae04794ff4967e50725290f71f78e
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/1d403cad1413d5b14b249eac7db5552c
この絵を一時期所有したロシア大富豪ドミトリー・リボロフレフ(Dmitry Rybolovlev)はこの絵をニューヨークで初めて目にして、次のように語っている。
‘The first time I saw Salvator Mundi,’ says Rybo, ‘I felt a very special, bright, positive energy. It was a remarkable feeling. I couldn’t take my eyes off the Christ. To see the wider context we need to return several years back. My family and I lived in Russia and I had been focused exclusively on my business. Russia was going through difficult and turbulent times in the 1990s. We had no time to enjoy art.’
「初めて『サルバトール・ムンディ』を見たとき」とリボは言う。「とても特別な、光り輝く、肯定的なエネルギーを感じました。驚くような気持でした。あのキリストから目を逸らすことができませんでした。状況を広げて考えてみるために、数年前に戻ってみなければなりませんでした。ロシアに家族と一緒にいたときは、仕事一途の人間でした。ロシアは一九九〇年代にむずかしい混乱の時代を迎えます。僕らに美術を楽しむ時間はありませんでした」
Ben LewisのThe Last Leonardoには、リボロフレフのコメントを含め、『サルバトール・ムンディ』をめぐる興味深い事実が満載されている。
この部分などは上質のミステリー小説を読んでいるように興奮する。
はたして『サルバトール・ムンディ』はほんとうにダ・ヴィンチの作品なのか? 当初予定されていたルーブル美術館の「ダ・ヴィンチ大回顧展」にもいまだ出展されていない。
https://news.artnet.com/exhibitions/salvator-mundi-louvre-1687114
そしてこの絵に大幅な修正を施したと言われる著者たちが自分たちの考えと意見を記した本も今月刊行された。
Martin Kemp, Robert B. Simon, and Margaret Dalivalle, Leonardo's Salvator Mundi and the Collecting of Leonardo in the Stuart Courts
https://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198813835.001.0001/oso-9780198813835
謎は深まるばかりだが、Ben LewisのThe Last Leonardoでその一部が解けるはず。
for the life of oneは否定文で使われて、「(人が)どうしても(…ない)」
for the life of oneは文字どおりには「…の命と交換しても」「…の命を賭けても」だが、「どうしても(…できない)」の意の強調表現として使われる。at all(全然、まったく)などよりずっと強い。
本日のGetUpEnglishはこの表現を学習する。
○Practical Example
Would you explain me the meaning of this phrase and how to translate it? I can't understand it for the life of me.
「この表現の意味と、どう翻訳したらいいか教えてもらえませんか? どうしても理解できません」
●Extra Point
次のような言い方もするので注意しよう。
◎Extra Example
I want to see her so much I could die, but I am afraid I couldn't for the life of me think of anything to say when I meet her.
「彼女に死ぬほど会いたいが、会ったら何を言っていいかわからないかも」
『サルバトール・ムンディ』 (Salvator Mundi 世界の救世主の意) は、イタリアの美術家レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた油彩画。青いローブをまとったイエス・キリストの肖像画。
2017年11月15日にクリスティーズのオークションにかけられ、手数料を含めて4億5031万2500ドル(当時のレートで約508億円)で落札された。この額は、2015年に落札されたパブロ・ピカソの「アルジェの女たち バージョン0」の1億7940万ドル(約200億円)を抜き、これまでの美術品の落札価格として史上最高額となった。(Wikipediaより)
この話題の絵について深く分析した話題書がある。
https://www.amazon.co.uk/Last-Leonardo-Ben-Lewis/dp/0008313415
今日のGetUpEnglishも10月4日、5日、6日、11月2日につづいて、この本にある表現を紹介する。
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/2203ac6af0af22d8f8fb301b8714412a
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/b64c8d0b72903b49ebb3d1582b9b7f3d
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/74dbed6d575d95180c4ce11fe666beec
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/2bdae04794ff4967e50725290f71f78e
この絵を2008年にロンドンのナショナル・ギャラリーに持ち込み、レオナルドの作品としてのお墨付きを得た(とされる)美術商ロバート・サイモン(Robert Simon)は、次のように述べている。
It’s been called the male Mona Lisa. This is not just hype, I think, because of the similarities in the way the two paintings are painted. Mona Lisa is a somewhat androgynous woman and the Salvator Mundi is a somewhat androgynous man. I see [Leonardo] trying to create a universal figure, man and God and with female and male characteristics.
この絵は『男性版モナ・リザ』と呼ばれています。ふたつの絵の描かれ方は似ていますから、大げさな言い方ではないと思います。『モナ・リザ』はどこか半分女性半分男性のような女性ですし、『サルバトール・ムンディ』半分男性半分女性のような男性です。「レオナルドは」女性と男性の特徴を備えた、人間と神の普遍的な姿を生み出そうとしたのではないでしょうか。
Ben LewisのThe Last Leonardoには、このマイケル・サイモンのコメントを含め、『サルバトール・ムンディ』をめぐる興味深い事実が満載されている。
はたして『サルバトール・ムンディ』はほんとうにダ・ヴィンチの作品なのか? 当初予定されていたルーブル美術館の「ダ・ヴィンチ大回顧展」にも出展されていない。
https://news.artnet.com/exhibitions/salvator-mundi-louvre-1687114
謎は深まるばかりだが、本書でその一部が解けるはず。
『サルバトール・ムンディ』 (Salvator Mundi 世界の救世主の意) は、イタリアの美術家レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた油彩画。青いローブをまとったイエス・キリストの肖像画。
2017年11月15日にクリスティーズのオークションにかけられ、手数料を含めて4億5031万2500ドル(当時のレートで約508億円)で落札された。この額は、2015年に落札されたパブロ・ピカソの「アルジェの女たち バージョン0」の1億7940万ドル(約200億円)を抜き、これまでの美術品の落札価格として史上最高額となった。(Wikipediaより)
この話題の絵について深く分析した話題書がある。
https://www.amazon.co.uk/Last-Leonardo-Ben-Lewis/dp/0008313415
今日のGetUpEnglishも10月4日、5日、6日につづいて、この本にある表現を紹介する。
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/2203ac6af0af22d8f8fb301b8714412a
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/b64c8d0b72903b49ebb3d1582b9b7f3d
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/74dbed6d575d95180c4ce11fe666beec
Overall, as much as 60 per cent of the painting could have lost Leonardo’s top layer of paint. Perhaps only 20 per cent of Leonardo’s final layer of paint – the picture as he intended it and as he finished it – has survived. Another 20 per cent is completely lost.* The greatest damage had been done in the areas of greatest importance. The Salvator Mundi is a portrait, and the face – particularly the eyes – are of the essence. And the face and eyes were the two most damaged areas of the painting. ‘It was shocking,’ says Dianne Modestini. The condition of the Salvator raises a new question about attribution: if this had once been a Leonardo, is it still now a Leonardo?
絵全体のうち、ダ・ヴィンチが最後に手を入れた部分の損壊は六割におよぶと思われた。彼がそのように意図した、そう仕上げたと思われるおそらく二割はかろうじて残っている。残りの二割は完全に失われてしまっている*。いちばん大きな損壊が最重要部に刻まれていた。『サルバトール・ムンディ』は肖像画であるから、顔が、特に両目が重要だ。その顔と二つの目の損壊がいちばん激しかったのだ。「ショックでした」とダイアン・モデスティニは言う。この『サルバトール』の制作者は誰であるか、新たな問題が生じた。もしこれがレオナルド・ダ・ヴィンチの作品であったとしても、今もそう言えるか?
はたして『サルバトール・ムンディ』はほんとうにダ・ヴィンチの作品なのか? 当初予定されていたルーブル美術館の「ダ・ヴィンチ大回顧展」にも出展されていない。
https://news.artnet.com/exhibitions/salvator-mundi-louvre-1687114
謎は深まるばかり。
least of allは「最も…でない、とりわけ…ない」。
今日のGetUpEnglishはこの語を学習する。
主に否定文で用いる。
○Practical Example
"I would do nothing to cause her worry. Least of all, would I leave without telling her."
「彼女に心配をかけるようなことはしない。特に黙って立ち去るなんてことは絶対にしない」
●Extra Point
現在、鋭意翻訳中の本に、この表現がある。
◎Extra Example
At that point, no one in the room, least of all Robert Simon, thought they might be looking at a genuine Leonardo. Would the Modestinis accept the task of restoring the painting, Simon asked. Dianne’s first response was to suggest one of her former pupils, but Simon replied, ‘I think this needs a grown-up.’2 Mario had been retired for several years, so Dianne agreed to take the job.
その時点では部屋にいる者は誰も、特にロバート・サイモンは、自分たちが目にしているものがダ・ヴィンチのものだとは思わなかった。ダイアンとマリオのモンデスティニ夫妻に、絵の修復を引き受けてもらえないか彼は尋ねた。ダイアンは以前ついていた自分の弟子のひとりに任せたらどうかと言ったが、サイモンは答えた。「ベテランでないとできないと思います」。マリオは数年前に引退しているので、ダイアンが引き受けることにした。
『サルバトール・ムンディ』 (Salvator Mundi 世界の救世主の意) は、イタリアの美術家レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた油彩画。青いローブをまとったイエス・キリストの肖像画。
2017年11月15日にクリスティーズのオークションにかけられ、手数料を含めて4億5031万2500ドル(当時のレートで約508億円)で落札された[4]。この額は、2015年に落札されたパブロ・ピカソの「アルジェの女たち バージョン0」の1億7940万ドル(約200億円)を抜き、これまでの美術品の落札価格として史上最高額となった。(Wikipediaより)
この話題の絵について深く分析した本がある。
https://www.amazon.co.uk/Last-Leonardo-Ben-Lewis/dp/0008313415
今日のGetUpEnglishも、一昨日、昨日につづいて、この本のなかの表現をご紹介しよう。
Such successes are far from guaranteed. Like any other industry to which people are drawn by the glow of fame and fortune emanating from those at the top, the art world has a very narrow peak of achievement and a wide base of footsoldiers, bottom-feeders and also-rans.
こうした成功はまったく保証の限りではない。最高位の者たちから発せられる富と栄光の輝きに人々が引き寄せられるほかの業界と同じで、美術の世界でも成功を収める者たちはごくわずかであり、あとは最下層の者たちや敗者を含む無数の下々の者たちがひしめきあっている。
footsoldierは「歩兵、 (会社などでの)下働き」
bottom-feederは「最低の地位[ランク]の者」
also-ranは「(競走で)等外馬; 等外になった人, 落選者; 落後者」
この3語が並んでいるので、上に訳したような処理でよいと思う。翻訳書を出すにはもちろん正確さも大事だが、すっと読ませる技術、そして請け負った仕事を期日までに仕上げるスピードが大切だ。