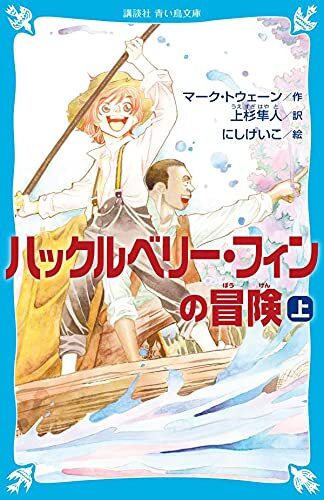Keikoさま、
アージェさま、
Yukaさま、
eiji tanakaさま、
すばらしいコメントをありがとうございます。
そしてお返事が遅れてしまいまして、ごめんなさい。
みなさまの質問にすぐにお答えしたいのですが、調査もしたく、しばらくお待ちいただけますでしょうか?
GetUpEnglishをご覧いただき、誠にありがとうございます。
毎日更新するのはなかなか大変なのですが、気になる表現もたくさんありますので、「毎日更新」のペースを崩さずにつづけたいと思っております。
どうか今後ともGetUpEnglishをよろしくお願いします。
上杉隼人 Uesugi Hayato
2011/01/27
かすみさまのご質問に対するコメント、ここにも載せておきます。
かすみさま、すばらしいコメント、ほんとうにありがとうございました。今後ともGetUpEnglishをどうぞよろしくお願いします。
*******************************************************************************************************
かすみさま、 大変すばらしいコメントを誠にありがとうございます。
「自分の言いたいことを述べるために、今後どのように英語に取り組むべきか?」ということですが、うーん、これはとてもむずかしいですね。
「自分の言いたいことを述べる」となると、一方的に自分の意見をひたすらしゃべるのではなく、相手の言いたいことをすべて理解したうえで、こちらの考え方をわかりやすく伝えるということに最終的にはなると思います。
そうなると、やはり総合的な英語学習が必要なのではないでしょうか?
そしてわれわれ日本人は、「とにかく英語をたくさん読んでみる」ということが一つには大事なように思います。
でも、自分が興味の持てない題材について書かれた英文を無理に読むのは、決して楽しいことではありません。(これは日本語でも同じですよね?)
ですから、とにかく最初は、「自分が興味のあることについて書かれた英文」をしっかり読んでみましょう。インターネットをチェックすれば、自分の興味のあることについて書かれた英語の記事が必ず見つかるはずです。音楽の好きな人は音楽について書かれた記事を、スポーツの好きな人はスポーツについて書かれた記事を、文学に関心のある人は文学について書かれた記事を、料理の好きな人は料理について書かれた記事を、旅行の好きな人は旅行について書かれた記事を、ぜひ読んでみてください。
自分が関心のあることには、ほかの人よりも「知識」が豊富にあるはずです。それがその記事を読むための「背景知識」になります。それさえあれば、その記事を読むのがだいぶ楽になるはずです。そして1本の記事を読んで、ほぼ100%理解できたとなれば、大変な自信になるでしょう。
よく書けた英語の文章は、その背景にある英語圏の文化を伝えてくれます。わたしたちが英語を読むのは、英米の文化を十分に理解するためである、と言っていいかもしれません。英語を勉強して、英米の文化をしっかり吸収することによって、英語のネイティヴスピーカーの気持ちや意識がしっかり理解できます。それによって、ネイティヴスピーカーとのコミュニケーションもうまくいくはずです。
最近は「とにかく何でもいいから英語で話してしまおう」というoutput(こちらから話す)重視の指導が盛んなようですが、「英語をしっかり読んで聞いて、英語と英語圏の文化と情報を十分に吸収する」というinput(入力)学習も絶対に必要だと思います。
そしてそれと平行して、英語を聴く力(listening能力)を鍛えることも必要だと思います。わたしは、映画の字幕を英語にして観たり、あるいは最近はアメリカの名演説を聴いて、リスニング学習をしています。ただ聴き流すのではなく、集中して聴くことが大事だと思います。そして聴き終えたあとで、一体何を言っていたのか、それを確認することが必要ではないでしょうか?
そのために、これまでGetUpEnglishでは、名演説を使った英語学習を紹介してきました。 GetUpEnglishでも何度か紹介した『名演説で学ぶアメリカの文化と社会』(上岡伸雄編著、研究社)には、正確なスクリプトがついていますので、このあたりを使って学習してみたらいかがでしょう?
http://webshop.kenkyusha.co.jp/book/978-4-327-45226-1.html
http://www.amazon.co.jp/dp/4327452262
お役に立てたかどうか自信がありませんが、どうか今後もGetUpEnglishをよろしくお願いします。
かすみさまには、今後もGetUpEnglishをチェックしていただけますと、とてもうれしいです。
UH
Dear Taroさん、
GetUpEnglishの2006/06/30のSAY WHENに書き込みをありがとうございます。
一つ、このブログにちょっと問題があるとすれば、英語の表現の説明をなるべく短くしようとしていることかもしれません。言うまでもないことですが、それによって、要点を手短に説明しなければなりませんし、大事なことが伝えられないということが出てきてしまいます。 Taroさんがレストランでのご体験を報告してくれたことで、その問題がはっきりわかってしまいましたね。
Taroさんを迎えてくれたウェイターは、ジョークを言ったわけでも、何かのパロディを表現したわけでもありません。"Say when."はもともとは飲み物を注ぐ時に用いた表現だったかもしれませんが、ほかのものを話題にするときも用いられます。ウェイターは「コショウをどこまでおかけしましょうか?」という意味で"Say when."と言ったのです。これは"Say when."がほかのことに対しても使われることを示すよい例です。
さて、次の状況も考えてみましょう。誰か友人からお金を借りたいとします。友人があなたの前に分厚い札束を持って現われると、目の前でそのお札を数え始めます。あなたはそれをじっと見ています。そして友人は、"Say when."と言います。どのくらい貸してもらえるとありがたいか、借りたい枚数のところで、あなたは"When."と言えばいいのです。つまり、このように"Say when."と"When."は、お金を話題にするときも使えるのです!もちろん、中には、お金なんて、水みたいなものさ、という人もいるでしょうが、それはまた別の話ですね。
ほんとうにありがとうございました。
As ever,
ロジャー
2006/07/01 10:53
**************************************************************************
Dear Gobroncoさん、
GetUpEnglishの2006/06/30のSAY WHENに書き込みを誠にありがとうございます。
おっしゃるとおり、"Say when."と聞かれたら、次のような答え方もできます。
"Stop"
"Okay"
"Fine"
"That's fine"
"That's enough"
"There"
要するに、意味が通じるのであれば、どんな表現も使えるということです。
All best wishes to you!
ロジャー
2006/07/05 07:12
**************************************************************************
matsukawa 1971さん、
"Looking forward"という表現は、特に若者言葉というわけでありません。年齢、社会的地位を問わず、今ではほとんど誰もが言ったり書いたりします。
Looking forward to your future comments,(matsukawa 1971さんの今後のコメントが楽しみです)
ロジャー
2006/07/06 07:53
Dear Hiroさん、
GetUpEnglish2006/06/18のNO WAYに書き込みをありがとうございます。
"Go figure!"をGetUpEnglishに喜んで紹介いたします。
この短い表現は、最近よく使われるようになりました。特にアメリカではよく使われます。これは"Go figure it out!"を縮めた言い方です。
"Go figure!"も、"Go figure it out!"も、「信じられない、わけわかんない、どうなってんの?」、あるいは「いや、びっくりした、まったく思いがけないことだな、参ったな」といった意味で用いられます。
例を挙げます。
"Rex started up a business with only $3000 last year, and now it's worth over a million. Go figure! And he failed economics at university!"
「レックスは昨年たった3000ドルで会社を興したんだけど、それが今じゃ時価総額100万ドルの企業に成長したんだ。信じられないよ! それにあいつは大学で経済の科目を落としてるんだよ」
Hiroさん、そしてぼくもたぶんラッキーだと思います。このGetUpEnglishを4月に立ち上げましたが、2006年6月18日現在で3万6000を超えるアクセスがありました。
信じられません!(Go figure!)
Best,
ロジャー
***************************************************************************
Dear matsukawa 1971さん、
GetUpEnglish2006/06/21のTO GO ONをmatsukawa 1971さんのブログ「matsukawa1971の英語のお勉強の記録」にトラックバックしていただき、誠にありがとうございます。
その後も何度もGetUpEnglishをご紹介いただき、心より感謝いたします。どうか今後もGetUpEnglishをよろしくお願いします。
もし何か英語の語彙や言い回しで何かご要望などありましたら、ぜひお知らせ下さい!お待ちしております!(Bring 'em on!)この"Bring 'em on!は、2004年の大統領選挙で大変よく用いられました。
With all best wishes to you,
ロジャー
***************************************************************************
Dear AZさん、
GetUpEnglish2006/06/22のWHO CARES?にコメントをありがとうございます。今朝シドニーに着いたばかりですが(こちらは冬です)、コメントを拝読しました。
ぼくが知る限り、「注文の多い料理店」は英訳が二つあります。一つはジョン・ベスター氏の翻訳で、もう一つはぼくの翻訳です。そしてどちらも"The Restaurant of Many Orders"となっています。 ここに使われているorderという語で、日本語の「注文」ということばが持つ曖昧な意味を表現できると思います。
どの言語でもタイトルを付けるのはとてもむずかしいですから、そんなに落ち込まないで下さい。
ほんとうにありがとうございます。どうかよろしくお願いします。
Thanks again, and all the best,
ロジャー
**************************************************************************
Dear Thuyさん、
GetUpEnglish2006/06/22のWHO CARES?にご質問をありがとうございます。
"I couldn't care less."も、今日紹介した"I could care less."とまったく同じで、「まったく[全然]気にしない」(I do not care at all.)という意味になります。
例を挙げます。
"I couldn't care less about Dick's opinion of me. I can't stand him. So what if he hates me?"
「ディックが何を言おうが、まったく気にしない。やつにはまったく我慢できないよ。ディックに嫌われたって、どうでもいいさ」
もう一つ例を挙げます。
"I couldn't care less how much the new Toyota costs. I want it and I'm prepared to pay anything for it."
「トヨタの新型車がどれだけ高くても構わない。それが出るまで待つつもりだし、手に入るならいくらでも払うつもりだ」
どちらの表現も、「無関心」や「どうでもいいという気持ち」を示します。
Take care,
ロジャー
Dear Scottさん、
GetUpEnglishにコメントをありがとうございます。興味深い問題をご指摘いただき、誠にありがとうございます。
まず、accent(なまり)とdialect(方言)を区別しなければならないと思います。
確かに、ロンドンのアナウンサーが、例えば未成年の飲酒運転を報道する際に、「"the tyke had a wee dram before gettin' behind the wheel."(スコットランドの英語で、「未成年者がハンドルを握る前に、少し酒を飲んだ」)などとはまさか言わないと思います。ご指摘の通り、世界中のどのことば(方言)にも、ほかの地域のことばにはあまり使われない単語が用いられています。ですので、今紹介したような言い方でニュースを報道してしまえば、ふざけて言うのでもない限り、ちょっとおかしな話し方に聞こえてしまいますね。
しかし、BBCのテレビニュースなどを観ていると、話し方になまりのあるアナウンサーがニュースを報道していたりします。Orla Guerinなどはそうだと思います。 http://news.bbc.co.uk/newswatch/ifs/hi/newsid_3230000/newsid_3234100/3234164.stm
NHKでは、まずこのようなことはありえません。日本語の標準語は、「なまりのない日本語」であり、アナウンサーたちは地方のなまりを一切排除した話し方をします。この意味では、例えばBBCなどでは、報道されるニュースと、実際に読み上げられるニュースは、まったく別物です。その結果、BBCでは、イギリス国内のいろいろななまりをたくさん耳にすることができます。
「ですから、NHKもいろんな地方のなまりを交えてニュースを報道することはできますが、一つの共通のことばを使わないと、視聴者は理解できないと思います」とスコットさんは書かれています。しかし、現実にはNHKが地方のなまりを交えてニュース報道をすることはありません。NHKでは、なまりのない日本語だけでニュースが報道されていますから。 そのNHKついてですが、スコットさんがご指摘されていることの答えになるようなことを、ぼくは『ジャパン・タイムズ』に書きました。以下をご覧いただけますと、ぼくの考え方をはっきりわかっていただけるかと思います。 http://www17.ocn.ne.jp/~h-uesugi/openinguptodifference.htm
「NHKは何の改革も進めていないように思える。ニュース番組では、いまも明らかに標準語が全面的に押し出されていて、地方のなまりは一切排除される」とその記事にぼくは書きました。
ぼくがこの記事で言いたかったのは、ニュース報道においては、地方のなまりはできるかぎり排除される、ということです。2006/06/12のGetUpEnglisのACCENTでは方言について論じましたが、ぼくが問題にしたのは音声上の「なまり」(accent)であって、「××弁」のような地方の「方言」(dialect)やことばについてではありません。(スコットさんがお書きになったように、当然イギリスでも日本でも、ニュース報道で「方言」が使われることはありません。それはありえません。しかし、イギリスのニュースでは「なまり」を使って報道されることはあるものの、日本ではそれもありません。その違いがあると思います。)
明らかになまりと方言は関連性がありますし、だから混乱も生じます。ひょっとすると、2006/06/12のACCENTの記事では、その違いを明確にできなかったかもしれません。
とにかく、すてきなコメントをありがとうございます。今後もGetUpEnglishを読んでいただけますことを願っておりますし、またコメントも頂戴できますように。
ぼくの妻のリバープールのおばさんがいつも言っていた挨拶でお別れします。
Taraa!(サイナラ!)
ロジャー
**************************************************************************
AZさん、
GetUpEnglishにコメントをありがとうございます。
"Check it out!"はよく歌の歌詞に使われます――そして会話でも使われます――が、基本的はぼくがGetUpEnglishの2006/06/14に書いた言い方と同じです。ラッパーやパフォマーたちが"Check it out!"と言うときは、日本語の「やってみな!」に近い意味で使っていると思います。これを英語のほかの表現で言えば、"Look into it!", "Do it!"あたりになるでしょうか。でも、この"Check it out."はなかなかカッコいい言い方ですよ。
例を挙げますね。
"The gig tonight is awesome. Check it out."
「今夜のライヴはすげえよ。観に行きなよ」
そしてGetUpEnglishもどうかお忘れなく! 毎日見てね!(Check it out!)
Yo, (いや、どうも)
ロジャー
Dear Phongさん、
ご親切なコメント(2006/06/07のRUBBISHに対して)をありがとうございます。
Phongさんのご質問はとても興味深いです。
to patronise(アメリカスペルでは、to patronizeです)には、意味が3つあります。
しかし、どれもto rubbish(酷評する、けなす、くず扱い[呼ばわり]する)とは違います。
to patroniseには、まず「(店などを)ひいきにする、しばしば訪れる」という意味があります。
"I like to patronize that shabu-shabu restaurant in Ikebukuro. Their food is really great."
「ぼくは池袋のシャブシャブの店によく行くんだ。あそこの料理はほんとうにおいしいよ」
ほかに、「保護[守護]する、(芸術家などを)後援[支援]する (support)、奨励する」という意味があります。
"Mr. Powers, who is very rich, patronizes a number of musicians by giving them money to buy instruments."
「パワーズ氏はとてもお金持ちで、何人かの音楽家たちにお金を出して楽器を買ってあげたりしているんだ」
そして、もう一つ、ちょっと否定的な意味があります。「……に対して上位者[上役, 庇護者]ぶってふるまう」という意味で、多くは「誰かをからかう」という感じで使われます。
"Stop patronizing me by saying, 'You're not a bad dancer for someone who is so fat.'"
「ちょっとバカにしないでよ。『君はほんとに太っているけど、踊りはそんなに悪くないよ』なんて言わないで」
to patroniseはむずかしいですね。興味深い語について考えさせてくれて、ほんとうにありがとうございます。
All best wishes to you,
ロジャー
**************************************************************************
Dear Azさん、
またまたGetUpEnglishにコメント(2006/06/08のTO BE TAKEN WITHに対して)をありがとうございます。
Asさんがご指摘の通り、to fall forには、「……が好きになる、……にほれ込む」と、「……を信じ込む、……にだまされる、ひっかかる」の二つの意味があります。
マックスは真美にゾッコンになってしまいました。だから何でも彼女に買ってあげたいと思いました。(He wanted to buy her the moon.)けれども、真美は明らかにマックスがお金もちだから近づいたのであって、彼を愛していたわけでありません。マックスはそれがわかりませんでした。真美は彼に嘘をついていました。マックスはだまされていたのです。(Max fell for it.)
しかし、その後マックスは真理というほかの女の子を好きになりました。マックスと真理はこのあいだ結婚して、結婚式のバックミュージックにビートルズの"Can't Buy Me Love"をかけました。
一方、真美はどうなったでしょうか? 今後のGetUpEnglishでお知らせしますね。
Take care,
ロジャー
Miwsさん、
GetUpEnglishにコメントを誠にありがとうございます。おっしゃるとおり、「折り返し電話する」の意味で、"Can I have her call you back?"も確かに大変よく使われますね。そして、ぼくは、「to phone backは『折り返し電話する』と言いたいときに、いちばんよく使われると言い方」と書いてしまいましたが(ちょっと訂正しました。ごめんなさい)、これも含めまして、一つの表現がほかの表現よりよく使われるということは言えないと思います。おっしゃるとおり、それは使う人たちの習慣によりますね。
例えば、"Would you like her to call you back?"もあらゆる地域で使われるのではないでしょうか?
大変貴重なコメントをいただき、誠にありがとうございます。
そして混乱させてしまって、申し訳ございません。
Best wishes,
ロジャー
AZさん、
メールをありがとうございます。
GetUpEnglishのUP/DOWN(2006/05/27)にコメントをありがとうございます。
to walk down the aisle, あるいはto walk up the aisleは、確かにちょっと古い言い方ですが、日本語の「お嫁に行く」のように、現在は使われなくなりつつあるということはありません。現在は、男女平等の時代ですから、「お嫁さん」とか、「お嫁に行く」という言い方はもはや時代遅れだと思います。
教会で結婚式を挙げなくても、「結婚する」の意味でto walk down the aisleという表現を使います。この場合、比喩的に用いられます。
GetUpEnglishを毎日読んでくださっているとのこと、ほんとうにありがとうございます!
With best wishes,
ロジャー
Mostafaさん、
GetUpEnglishの BIG ON(2006/05/20)にコメントをありがとうございます。
big on somethingは、「何かを非常に好きである」(You like it a lot.)という意味です。「何かが得意である」(You are good at it.)の意味はありません。
例を挙げます。
"Helmut is really big on tennis. He plays every week, but he's absolutely hopeless."
「ヘルムートは、テニスが大好きだ。毎週やっているよ。でも、全然うまくない」
気の毒なヘルムート! やっぱり「好きこそ物の上手なれ」といきたいところですね。
Mostafaさん、ありがとうございます。
All the best to you,
ロジャー
**************************************
AZさん、
GetUpEnglishのGUY(2006/05/21)にコメントをありがとうございます。
****************************************
Boy, yesterday's football game was fantastic!
****************************************
AZさんが書いてくださったこの用例のboyには、「少年」という意味はありません。これはその意味では使われていません。このboyは、愉快・驚き・落胆などを表わす発声です。(“Oh, boy.”という表現もよく使われます。)
日本語の「よう、ほんとに、無論、やれやれ、あーあ、おっ、すごい、ワー、ワーイ、すてき、うまいぞ」といった意味を示します。
例を挙げます。
"Boy, it's hot in here. Will somebody please turn on the air conditioner?"
「ああ、暑いね。誰かエアコン入れてくれない?」
でも、もしある部屋にいる男の人たちに呼びかけたいときは、boysで呼びかけることができます。boyは普通は15歳以下ぐらいの男性を指しますが、大人の男性を指すときも使われます。
しかし、AZさんが用例に示してくれたboyは男性をさしているわけではありませんので、どうかご注意ください。
Warm wishes,
ロジャー
**************************************
AZさん、
またGetUpEnglish(GUY[2006/05/21])にコメントをありがとうございます。
AZさん、一人の大人の男性に呼びかけるときは、boyを使わないほうがいいです。boyを大人の人に対して使うときは、あくまでちょっとふざけた感じで、そして複数の人に呼びかけるときだけしか使えませんから、どうかご注意ください。昔は人種差別的な意識を持った人たちが、白人以外の人種・民族の男性をさして、boyと言ったりしました。
しかし、これは軽蔑的な言い方ですし、今では絶対に使われるべきではありません。でも、複数の、いろんな男性に対してであれば、boyと呼びかけてもOKですよ。
ああ、英語って、やっぱり複雑ですね。(Boy, that's complicated, no?)
Yours,
ロジャー
Dear Goroさん、
GetUpEnglishのup to itにコメントをありがとうございます。
Goroさんはまったく正しいです。"What are you up to?" で、「あなたは何を企んでいるだろうか?」という意味を表現することができます。
例を挙げます。
I wonder what Cheney is up to when he makes such aggressive speeches?
チェイニーはあんなに攻撃的なことを言うが、何か企んでいるのだろうか?
Some people are up to no good.
悪いことを考える人もいるんだ。
それから、2006/05/14には、このコメントもありがとうございます。 ******************************************************************************** リクエストをしても良いものかわかりませんが、もし機会があったら、DARE という単語を取り上げてもらえないでしょうか? I dare you .....、 Don't you dare?、 How dare you? などの意味はわかってもニュアンスがしっくりきません。 ********************************************************************************
このto dareの用法については、『ほんとうの英語がわかる 51の処方箋』(新潮選書)に詳しく書きました。どうかそちらをご覧いただけますと、とてもうれしいです。
http://www17.ocn.ne.jp/~h-uesugi/hontouda.htm
http://www17.ocn.ne.jp/~h-uesugi/52.htm
よろしくお願いします。
Be good.
ロジャー
***********************************
Dear サトシさん、
GetUpEnglishのseriouslyにコメントをありがとうございます。
数年前まではseriouslyが「超……」とか「メチャクチャ……」の意味で使うことはあまりありませんでしたし、使われるとしてもちょっとくだけた状況に限られました。しかし、今ではかなり広く用いられますし、改まった状況でも使われます。
例を挙げます。
Mr. Umeda's report on the latest IT devices was seriously interesting.
梅田氏の最新IT機器に関する発表は、メチャクチャ興味深い。
このような意味で、seriously(「超……」「メチャクチャ……」)はおそらくかなり広く使われつつあると思います。
しかし、最近「超急カーブ」と書かれた道路標識を目にしました。そのあたりをよくバイクに乗った若い人たちがすごいスピードで流しています。こんな調子であれば、「超……」といった言い方が公で使われる日もそう遠くないかもしれませんね。
Cheers,
ロジャー
Rickyさん、
GetUpEnglishに書き込みをありがとうございます。そしてジョージ・ハリスンの"You Like Me Too Much"の歌詞を教えてくださって、どうもありがとうございます。Rickyさんはまったく正しいです。ジョージのこの歌の歌詞に出てくるwhich is all that I deserveは、it serves me right(無理はない、当然の報いだ)という意味です。ジョージは、自分を卑下するというか、自分はだめなやつで、まったく男らしくないと認める男性の気持ちを歌っています。この男性は、自分は彼女にやさしくできなかったし、もし彼女が自分から離れていってしまうのであれば、それは「当然の報いだ」と思っています。でも、GetUpEnglishを読んでくださっているみなさんは、どうかそんなことは言わないでくださいね!
Rickyさん、すばらしいコメントをほんとうにありがとうございます。
As ever(いつもお世話になります),
ロジャー
Goroさん、
5月11日の"You said it!"にコメントをありがとうございます。
"You said it!"は、「日本語の『良くぞ言ってくれた!』」って感じですかね?」とのことですが、ちょっと違うように思います。英語のイディオムは表面上の意味とは必ずしも一致しないと認識することがとても大切です。 「良くぞ言ってくれた!」は、"You said it!"(まったくだ、まさにそのとおり)とは、やはりちょっと意味がずれると思います。
状況によりますが、「良くぞ言ってくれた!」は、ぼくは"I'm really glad you told me!"とか、"Thanks a lot for saying it!"と訳します。
"You said it!"は、"That's right!"や"I agree with you!"の意味であり、あくまで相手に賛同を示す言い方です。「よく言ってくれたね!」というように、それによってその人を賞賛するとか、それに対して快哉を叫ぶという感じではありません。
idiomという単語は、idiot(大ばか、まぬけ;白痴)から来ています。idiomはidiotic(白痴の; 大ばかな)です。イディオムそのものの意味と、それを構成する各単語の意味は、必ずしも一致しません。
Goroさん、ほんとうにすばらしい書き込みを誠にありがとうございます。おかげで日英語の興味深い比較ができました。またぜひGetUpEnglishにコメントをお願いします。
ロジャーより ************************************************************************
garyuさん、
5月12日の"It serves you right."にコメントを誠にありがとうございます。
"You deserve it."は、否定的な意味で使われるのであれば、"It serves you right."とまったく同じです。
例を挙げます。
"Arthur was driving at 120 km. an hour, the police caught him for speeding and fined him $300. He deserved it!"
「アーサーのやつ、120キロで車を飛ばして、警察にスピード違反で捕まって、300ドルの罰金を科せられた。自業自得だよ」
この場合、”He deserved it!"のitは罰金です。つまり、「罰金を科せられても当然(の報い)だ」という意味になります。
しかし、"You deserve it."と"It serves you right."は、一つ違いがあります。"It serves you right."は常に否定的な意味でしか使われませんが、"You deserve it."は肯定的な意味でも用いられます。
例を挙げます。
"Alison worked harder than anyone cleaning the park, and everyone really praised her and said how wonderful she was. She really deserved it."
「アリソンは、誰よりも公園の清掃を一生懸命やった。みんな彼女をほめたし、彼女はほんとにすばらしいと誰もが言った。アリソンは実際みんなにほめられるようなことをしたんだ」
この場合、"She really deserved it."のitは、「みんなの賞賛」(their praise)です。つまり、アリソンは「みんなにほめられるようなことをした」ということです。ここでは、"It serves her right."は使えません。
garyuさん、ほんとうに書き込みありがとうございます。
ロジャーより