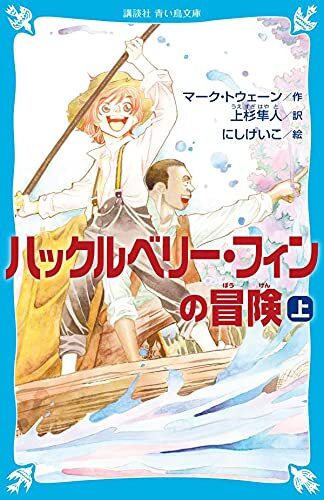A Journey to the Ends of the Biggest Story Ever Told
By Douglas Wolk
https://www.penguinrandomhouse.com/books/549063/all-of-the-marvels-by-douglas-wolk/
マーベルの原点がわかるすごい1冊だ。
すでにこの本のすごさについて書いたが、
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/e/44d9b5f6185ef32ab64712fb0a660bd8
https://blog.goo.ne.jp/getupenglish/c/1d6a6ce5dd158fcdcbd8fd5f26bcb2ba
本日のGetUpEnglishも途中報告を込めて本書のごく一節を紹介したい。
How did I read them? Any way I could. I read them on couches, in cafés, on treadmills. I read them as yellowing issues I’d bought when they were first published, or scored at garage sales as a kid, or snagged from a dollar bin at a convention as an adult. I read them in glossy, bashed-cornered paperbacks borrowed from the library. I read them as bagged-and-boarded gems borrowed from friends. I read them as expensively “remastered” hardcover reprints, and as .cbz files of sketchy provenance, and as brittle stacks of pulp that had been lovingly reread until they’d nearly disintegrated. I read a few from a stack of back issues somebody abandoned on the table next to mine as I was working at a Starbucks one day; it just happened to include an issue of Power Man and Iron Fist I’d been looking for. I read a hell of a lot of them on a digital tablet. I read them in the economical black-and-white “Essential” collections Marvel pumped out between 1996 and 2013, and in ragged British pulp weeklies from the ’70s. I read them from the peculiar CD‑ROM collections Graphic Imaging Technology published in the mid-2000s, with hundreds of indifferently scanned issues of Amazing Spider-Man or Ghost Rider.*
それだけの本をどうやって読んだか? どこにいても何をしていてもありとあらゆるものを読んだ。ソファでもカフェでも読んだし、ランニングマシンの上でも読んだ。すでに黄ばんだ初版本にも、子供の頃にガレージセールで手に入れたものにも、大人になってから何かの集会の1ドルセールで手に入れたものにも目を通した。図書館で借りたピカピカしてはいるが角が折れたペーパーバックも読んだ。プラスチック袋と厚紙に大事に包まれた友達の貴重なコミックブックも見せてもらった。高価な「新装版」ハードカバーも、CBRファイルにざっくり保存されたイメージも、何度も何度も読んでいて束が崩壊して何枚かページの飛んでいるものも確認した。ある日スターバックスで仕事をしていると隣の席にコミックの山が置き去りにされていたから、その中の何冊かも読ませてもらったこともある。その時探していた『パワーマン&アイアンフィスト』の号がたまたま目についたのだ。デジタルタブレットで電子版も何冊も目を通した。1996年から2013年にかけてマーベルが出版していた廉価版のモノクロ「エッセンシャル」コレクションにも、激しく痛んだ1970年代刊行のイギリスのパルプ週刊誌にも目を通した。2000年代中盤にグラフィック・イメージ・テクノロジーから発行されたCD-ROMコレクションも手に入れて、機械的にスキャンされていた数百冊の『アメイジング・スパイダーマン』」や『ゴーストライダー』も読み漁った*。
パラグラフが長く、情報量が多い上に、凝った言い方もしているので油断ならない。
「パラグラフ・レベルで訳す」、すなわちまずは英文をよく読み込んで、「パラグラフごとに日本語に書き換えていく」という方法で臨んでいる。
わたしは本業があるから一日の翻訳時間は限られているし、弟子や下訳者にお願いできるエラい翻訳者ではないから、すべてひとりでこなす必要があるし、それが楽しい。
著者自身がほぼ毎ページに次のような注をつけているので、さらにきびしくなる。
*I didn’t intend to read any at the Burning Man art festival in the Nevada desert in the summer of 2019; the only comics I had brought with me were a few copies, to give away, of 1998’s X‑Force #75, in which the team attends the same event, transparently disguised as the “Exploding Colossal Man” festival. But somebody had set up a little memorial shrine for Stan Lee, and at its base there was a box labeled read me, containing some battered but intact fifty-year-old issues of Amazing Spider-Man and Thor and Tales of Suspense, and what was I going to do, not read them?
*2019年の夏にネバダ砂漠で開催されたバーニングマン・アート・フェスティバルでは読むつもりはなかった。そこには1988年刊行の「Xフォース」75号しか持ってきていなかった。バーニングマン・アート・フェスティバルでは最後に、「ザ・マン」と呼ばれるイベントのシンボルである巨大な像が燃やされる「爆発する大巨人」のイベントがあるが、「Xフォース」75号にはこのイベントにXフォースのメンバーが参加する様子が描かれているのだから、現地でこの号を配ろうと思った。ところが、誰かがその前の年に亡くなったスタン・リーの小さな記念碑を作り、「ここにあるものを読んでください」と記されたラベルの張られた箱を置いているのではないか。その中には痛んではいるものの、まだ十分きれいなマーベル・コミックが何冊かあった。なんと、50年前に刊行された『アメイジング・スパイダーマン』や『ソー』や『テイルズ・オブ・サスペンス』があるではないか。もちろん手に取って読まずにいられなかった。
注に訳注をつけるのはなかなかむずかしいので、必要があれば訳文に情報を補いつつ訳している。
All of the Marvels A Journey to the Ends of the Biggest Story Ever Toldは作品社から2024年刊行予定。
毎日少しずつ訳して、年内訳了をめざしたい。
「普通」ってなんなのかな――自閉症の僕が案内するこの世界の歩き方
ジョリー・フレミング/リリック・ウィニック 著、上杉隼人 訳
文藝春秋
「図書新聞」 No.3589 ・ 2023年04月29日
■「自閉症でない人が、自閉症について理解できるとは思えません。不可能です。同じように、僕も自閉症でない人たちのことがわからない。自閉症でない人が自閉症でないことを一生懸命説明して、自閉症の人が自閉症のことを一生懸命に説明しても、おたがい『わからないよ』と首をかしげたり肩をすくめたりするだけじゃないかな」(本書7ページ)。
ジョリー・フレミング(二十八歳)は五歳で自閉症と診断され、普通の小学校には受け入れてもらえなかった。毎日の生活でもさまざまな困難をずっと抱えてきた。そんなジョリーが高校に進学して卒業し、大学を四年で卒業した。そしてイギリスの名門オックスフォード大学のローズ奨学金を得てオックスフォード大学の修士号(地理環境学)を得た。今は母校サウスカロライナ大学の研究員をしている。ジョリー本人も含めて、誰にも考えられないことだった。
「本書はあなたをインスパイアし、あなた自身と周りの人々の精神をより深く省みさせてくれるだろう」。
『スティーブ・ジョブズ』や『レオナルド・ダ・ヴィンチ』で知られるベストセラー作家、ウォルター・アイザックソンは、『「普通」ってなんなのかな』の推薦文にそう記している。
ジョリーの物語は、定型発達者の頭脳を持たない人が定型発達者の頭脳のために構築された世界に住むのは一体どんな感じか、わたしたちに窓を開いて見せてくれる。われわれが「人間らしい」「普通」と思いこんでいる精神とちょっと違う精神や考え方はどんなものか、実際に示してくれるのだ。本書につづられたジョリーの人生の旅を通して、ウォルター・アイザックソンが言うように、読者は自分たちの心の中をのぞき込み、考えさせられることになる。
わたしたちは自分たちと障がい者の違いを見出すことで、自分たちが「普通」であると考えているだけではないだろうか?
「僕がみんなについて知らないことがあるのと同じように、みんなも僕について知らないことはある。でも、だからと言って、僕たちが同じヴィジョンを持ったり、団結して同じ目標に向かって突き進むことができない、というわけじゃない」(本書203ページ)。
だが、この言葉からわかるように、ジョリー・フレミングは定型発達者と自閉症の人たちがともに支えあうよりよい社会を作り出したいと考えている。
二〇一六年七月、神奈川県相模原市でおそろしい事件が起こった。自閉症の人を含む障がい者の福祉施設で、十九人が死亡し、二十六人が負傷し、十三人が重傷を負った。容疑者の「意思疎通のとれない障がい者は安楽死させるべきだ」などというおそろしい発言の数々に日本中が強い怒りを覚え、深い悲しみに包まれた。
ジョリー・フレミングは日本版に特別収録された「『日本版附章』ジョリーは今」で、このおそろしい事件についてコメントしている(このインタビューはYouTube動画でも観られる。https://www.youtube.com/watch?v=hpZwF7pivCo)。
「僕は願っています。将来、あらゆるものを取り込める社会の建設が進められて、より多くの愛とケアが注ぎ込まれる。そうすれば、今言及されたような恐ろしい事件は少なくなるはずです」。ジョリーはそんな社会において、誰もが役割を担うとする。「一緒によりよい社会を作り出せるはずです。人間の歴史の一部である愛とケアにあふれ、これまで僕らの周りで起こってしまい、今も世界のどこかで起こっている悪いことはほとんど見られない社会。そんなすばらしい社会を僕らは一緒に作り出せるのです」(本書243ページ)。
この美しき驚くべき青年(ウォルター・アイザックソンはジョリー・フレミングをこのように言っている)は、笑顔が障がい者と定型発達者の関係において緩衝材として機能し、よりよい社会を作り上げると信じている。四月二日の世界自閉症啓発デーに向けて、ジョリー・フレミングは日本の読者にメッセージを送ってくれた。
「意識して笑顔を作ったり、やさしい言葉をかけたりすることで、いろんな関係にすごくいいものが広がっていきます。そんなふうに心に留めていれば、もしかしたら愛を持って人を受け入れるのがちょっとだけ楽になるかもしれません」。
※本稿は『朝日ウィークリー』2558号(二〇二三年四月二日)に英文で寄稿した記事を筆者が日本語に翻訳したものである。
(編集者/翻訳者/英文ライター・インタビュアー/英語講師)
「図書新聞」No.3589 ・ 2023年04月29日(土)に掲載。 http://www.toshoshimbun.com/books_newspaper/index.php
「図書新聞」編集部の許可を得て、投稿します。
今日のGetUpEnglishはこれについて考えてみよう。
not too hardで表現できる。
"Don't be too hard on me, please."
「お手柔らかにお願いします」
●Extra Point
「~を照らす、明るくする」の意味でも表現できる
◎Extra Example
"Our teacher is too strict. I wish she would lighten up."
「私たちの先生は厳しすぎる。もう少しお手柔らかにしてくれるといいのに」