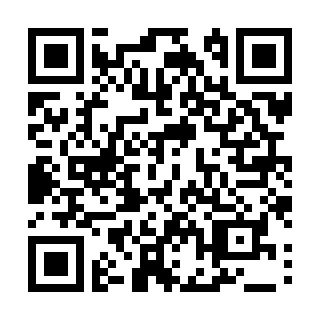コロナ以前に書かれた、コロナ時代を予見する短篇集
アレグザンダー・ワインスタインの『新世界の子供たち』
語り手の男性(僕)は大学教員で、妻のアンと思春期を迎えた十代の息子マックスと3人で暮らしている。世界の人々は家の中から出ずに生活している。「僕」は大学教員としてオンラインで授業をし(デートもセックスもオンラインの仮想世界で行っている)、妻は仮想世界のランドスケープデザイナーとしてそれぞれ自分の部屋で働いている。夫婦仲は悪くないが、バーチャルの世界でアバターを介してのセックスしかしていない(ゴーグルをつけて、スーツを着て、バーチャルの世界で行う)。息子は部屋で授業を受けたりゲームをしたりしているが、最近挙動におかしなところがあり、バーチャルドラッグをしているのではないかと夫婦は疑っている。「僕」はもう何年もの間、現実世界では家族以外と接触していない。
そんなある朝、マックスが家からいなくなった。自転車で外に出て行ったようだ。「僕」はマックスを追う。そして廃墟となったショッピングモールでマックスを見つける。これからドラッグのディーラーに会うのではないかと様子を見ていたが、マックスはテニスボールを壁に打ち付けて遊んでいるだけだった……。
アレグザンダー・ワインスタインの『新世界の子供たち』(Alexander Weinstein, Children of the New World, 2016)収録の短篇「移動」(“Migration”)はこんなストーリーだ。一部訳してみる。
Max puts his foot down onto the ground and steps off his bicycle. “Wow,” he whispers.
“I know,” I whisper back.
The world is quiet except for the hooves on the concrete and Max’s breathing. Between the jigsaw of houses, another herd is migrating past the rotten swing set of an English Tudor. Above us, a V of birds crosses the sky, their honking close. I shut my eyes and imagine the grid of streets where my son and I stand, visualize beyond to our house where Ann is waiting for us, alone and worried, and farther still, far beyond our subdivision, to where the geese head toward warmth and herds make their way beneath the arc of evening sky. I want to tell Max that I love him; that he’ll always be my son; that somehow everything will be okay again. But maybe that’s too far from the truth. So, instead, I put my arm around him, and we stand together in the falling snow, watching the deer return to their migration.
マックスは足を地面につき、自転車から降りる。
「わあ」と息子はつぶやく。
「すごいな」と僕も応える。
世界は静かで、コンクリートに響く蹄の音とマックスの息遣いしか聞こえない。別の群れがさまざまな家が立ち並ぶ通りを進み、イギリスのチューダー様式の家の庭に置かれた朽ち果てたブランコを通り過ぎる。Ⅴ字型を形成して上空を横切る鳥たちの鳴き声が近くに聞こえる。目を閉じ、マックスとともに街路に立つ自分を想像し、この先の僕らの家でひとり心配してマックスと僕を待っていてくれるアンを思い浮かべる。そのずっと向こう、僕らの家の区域をはるか越えて、ガチョウの群れは暖かい場所に向かい、シカの群れは夕空の弧の下を移動していく。マックスに、おまえを愛している、おまえはいつまでも僕の子供だ、どうにかすべて元通りになるさ、と伝えたい。だが、それはあまりにも真実からかけ離れているかもしれない。だから代わりに腕をまわして息子を抱き寄せ、降りしきる雪の中、ふたりしてシカの群れがふたたび移動するのを見守る。
※
I know: わかっている。マックスが“Wow”という理由はわかるし、自分もシカの群れを見てWow”と思っているということ。「僕」はマックスの感じていることを理解し、同じ気持ちであると伝えている。
the hooves on the concrete: コンクリートの上をコツコツと響くシカの蹄の音。
the jigsaw of houses: 何軒もの家のジグソーパズル。異なる形やサイズの家々がいくつも並んでいる様子を表現している
English Tudor: チューダー朝時代(1485年から1603年)の建物を指す。イギリスのチューダー様式は歴史を感じさせる外観と独特の雰囲気を備えていて、伝統的な英国の住居を思わせる。
their honking close: 彼ら(鳥たち)の鳴き声は近い。their honking is close to usということ。
the grid of streets: 街路の配置、配列。道路が水平方向と垂直方向に交差していて、碁盤の目のように整然と配置されている様子。
migration: 鳥や動物たちの移動。
わが子マックスはただ外に出たかった、自転車に乗りたかったのだ。「僕」は息子の顔をひさしぶりにしっかりと見ることができた。
このまま人は他人と出会わず、子供も作らず、いずれみんな死に絶えてしまうんだ、というマックスの言葉を聞き、「僕」はその事実に目をつぶっていたことに気づく。
家に帰る途中、ふたりは百頭ほどのシカの群れに出会う。空には鳥が群れをなして飛んでいる。移動する鹿の大群に感動するふたり。「僕」は息子に対する愛情と未来への希望を口はできないが、息子を抱き寄せてシカの群れがふたたび移動していくのを見守る。
アレグザンダー・ワインスタインの短篇集『新世界の子供たち』は、本短篇「移住」のほか、2022年公開の映画『アフター・ヤン』(After Yan)の原作となった「ヤンにさよなら」( “Saying Goodbye to Yang”)をはじめ、表題作「新世界の子供たち」を含む全13編からなる。近未来の世界を舞台に、現在存在する技術の延長線上にあるが、現在ではあり得ないと思われる技術や設定が取り巻く世界における人々の交流を描く。ここに紹介した「移住」のように世界から離れて外部とオンラインで交流をはかるなど、2016年に発表されたにも関わらず、どれも新型コロナウイルスの世界的大流行(パンデミック)後の世界を予見していたと思われる作品ばかりで驚いてしまう。
本短篇集が上杉訳でこれから翻訳刊行されるというわけではない。翻訳刊行したいと思い、本書の内容をまとめて、一部訳してレポートにまとめてすでに複数の出版社に見てもらっているが、まだどこからもいい返事がもらえていないのだ。
こうしたことはよくあるから、必要以上にがっかりしてはいけない。常にアンテナを張り巡らして「これは多くの読者をつかめそうだ、訳してみたい」という本を探せばよい。幸いなことにわたしは英語講師でもあるので、翻訳講義の課題に使える題材を探しながら、翻訳してみたい本を常時チェックしている。
Alexander Weinstein, Children of the New World
上杉隼人(うえすぎはやと)
編集者、翻訳者(英日、日英)、英文ライター・インタビュアー、英語・翻訳講師。桐生高校卒業、早稲田大学教育学部英語英文学科卒業、同専攻科(現在の大学院の前身)修了。訳書にマーク・トウェーン『ハックルベリー・フィンの冒険』(上・下、講談社)、ジョリー・フレミング『「普通」ってなんなのかな 自閉症の僕が案内するこの世界の歩き方』(文芸春秋)など多数(日英翻訳をあわせて90冊以上)。2024年は現時点で話題書を含めて英日翻訳7冊刊行予定、日英翻訳も1点。