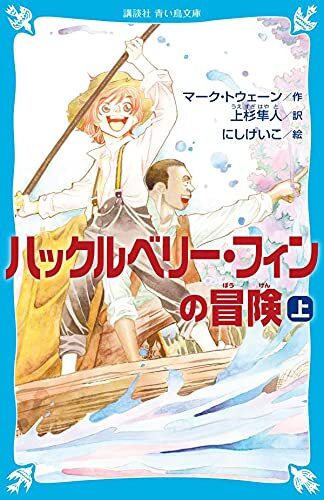overの付く言い方は、2007/02/22のOVER MY DEAD BODYや2007/09/30のOVER THE HILL, OVER THE MOON, あるいは2006/07/21のGET OVER ITなど、GetUpEnglishでいくつか紹介した。今日はoverが「……中、……の間、……の終わりまで」の意味で使われる用例を紹介する。
○Practical Example
“When do you want to check those English examples, Uematsu?”
“Let’s do it over our morning break, okay?”
「植松、例の英語の用例、いつチェックするの?」
「午前中の休み時間にチェックしないか? いいかな?」
●Extra Point
over coffee(コーヒーを飲みながら)やover breakfast(朝食を取りながら)など、「……しながら」という意味でもよく使われる。
◎Extra Example
“Elizabeth helps me with my English over coffee.”
“That’s nice, Erika. And you teach her Japanese over lunch.”
「エリザベスはコーヒーを飲みながらわたしの英語をみてくれるのよ」
「それはいいわね、絵理香。そしてあなたは昼食を食べながら彼女の日本語をみてあげるのね」
under pressureで、「圧迫されて、急がされて、せかされて」。
○Practical Example
“Mum, help me with my homework tonight, okay?”
“I can’t, Miho. I’m under a lot of pressure now. Leave me alone.”
「ママ、今夜宿題を手伝ってくれない?」
「美穂ちゃん、ごめんできないの。いますごく大変なの。ママを一人にして」
●Extra Point
to put someone under pressure(誰かに圧力を加える、プレッシャーをかける)も使われる。
◎Extra Example
“Look Miho, you’re putting me under a lot of pressure. I’ve got to make dinner for daddy and his clients.”
“Sorry, mum. Can you help me after dinner?”
「ねえ、美穂、あなたはママに無理ばっかり言う。ママはパパとパパのお客さんのお食事を作らないといけないんだから」
「ごめん、ママ。お食事のあと、手伝ってくれる?」
budgetは、「予算(額)」の意味で使われる。
○Practical Example
“Do we have a budget for trips?”
“No, Cooke. Trips are not in the budget. You have to pay for travel yourself.”
「旅行に行く予算はあるの?」
「いや、ないよ、クック。旅行は予算に入っていない。行きたければ、自分で出さないといけない」
●Extra Point
動詞(to budget)としてもよく使われる。「(……のために)[ある金額を]予算として計上する[組む]」の意味で用いられる。
◎Extra Example
“I didn’t budget for those repairs on the car.”
“But you have to fix the car, Ed. Just find the money somewhere.”
「車のこの部分の修理は予算にいれていなかったよ」
「でも、エド、車は直さないといけないわ。なんとか修理代を工面しないと」
to dreadは、「(これからの事を)ひどく怖がる、恐れる」。かなり強い意味で使われる。
○Practical Example
“Have you studied for the astronomy test, Ms. Star?”
“I have, but I really dread it. Astronomy is so hard.”
「スターさん、天文学の試験勉強はしました?」
「しました。でも、とても心配です。天文学はとてもむずかしいです」
●Extra Point
形容詞dreadful(恐ろしい、こわい、ものすごい)もよく使われる。状況によっては、「ひどい」という意味になる。
◎Extra Example
“Hey, Chuck, how was the steak?”
“It was dreadful, Buster. It was as tough as old shoe leather.”
「やあ、チャック、ステーキはどうだった?」
「ひどかったよ、バスター。靴の革と同じぐらいかたかったよ」
日本語は「捨ててください」を「捨てちまえ」のように文末を変化させることで、言い方を変えることができる。それに対して英語で言い方を変えるときは、表現そのものを変える。たとえば「捨ててください」は“Throw it out.”だが、「捨てちまえ」は“Chuck it.”となる。 to chuck itは、「やめる、投げ出す」という意味もある。
○Practical Example
“Are you still taking those English conversation courses, Miyako?”
“No, I chucked them. They were expensive and worthless.”
「美也子、まだあの英会話の講座を受けているの?」
「いや、あれはやめちゃったよ。高いし、全然役に立たないから」
●Extra Point
to chuckにoutをつけて、to chuck outの形でも用いる。「放棄する、よす」といった意味で使われる。
◎Extra Example
“Hey, Bob, what did you do with that old video machine?”
“I chucked it out, Chuck. The tapes were getting stuck in it all the time.”
「ボブ、あの古いビデオレコーダーはどうした?」
「チャック、捨てちまったよ。テープがいつも詰まってしまっていたから」
dispensableはものは、「なくても済む、必ずしも必要でない」。
○Practical Example
“Do you need this computer, Bill?”
“No, Steve, it’s dispensable now. Chuck it.”
「ビル、このコンピュータは必要かい?」
「いや、スティーヴ、もういらない。処分してくれ」
to chuckは、「捨てる、処分する」。明日はこの表現を学習しましょう。
●Extra Point
反意語は、indispensable(絶対必要な、なくてはならない、欠くことのできない)。人に対して使うことが多い。
◎Extra Example
“Ms. Biswas is leaving the company.”
“Oh my God, we can’t do without her. She’s absolutely indispensable.”
「ビスワスさんが退社する」
「ええ、なんてことだ。あの人がいなくちゃ、困るよ。ビスワスさんは会社に絶対必要な人だ」
attainableは、「達成[到達]できる、遂げられる」。attainable goal(到達できる目標、達成できる目標)という言い方もよくする。
○Practical Example
“Do you really think you can get into graduate school at Handai?”
“Sure I do, Prof. Koyama. It’s an attainable goal. I just need to study a bit more.”
「阪大の大学院に入れるとほんとうに思っているの?」
「小山先生、絶対に入れます。それは実現できる目標です。もう少し勉強すればいいだけです」
●Extra Point
反意語は、unattainable(達成[到達、成就]できない).
◎Extra Example
“You’ll never get into graduate school at Handai. It’s unattainable.”
“Unattainable for who, Prof. Koyama? Not for me. I’ll show you.”
「阪大の大学院には入れないよ。無理だ」
「誰が入れないのですか、小山先生? ぼくじゃないですよね。ぼくは入ってみせますよ」
よく使われる表現で、「(……を)(……だと)みなす、考える」。
○Practical Example
“I regard Yoko as a friend. But she’s trying to steal my sweetheart from me.”
“A friend? She pretends to be a friend and takes what she wants.”
「ヨーコは友だちだと思っている。なのに、わたしの彼を取っちゃおうとしている」
「友だち? あの女は友だちのふりをして、ほしいものはみんな取っちゃうのよ」
●Extra Point
「人」だけでなく、to regard something asと、「ある物を……と見なす、考える」という意味でもよく使われる。
◎Extra Example
“Why didn’t you phone the doctor back, Yoshio?”
“Because I regard the problem as unimportant. I’m fine. There’s nothing wrong with me.”
「ヨシオさん、お医者さんに折り返し電話すればよかったのに」
「そんなに重症じゃないと思っているから。ぼくは大丈夫。どこも悪いところはない」
愛する人たちには、sweetheart(いとしい人)と呼びかける。honeyやdarlingと似た言い方で、とてもよく使われる。(ぼくは妻のことをいつもsweetheartと呼んでいます。)
○Practical Example
“Oh, sweetheart, would you make me a cup of coffee?”
“Not right now, darling. I’m on the phone.”
「ねえ、コーヒーを入れてくれないかな?」
「いまはだめよ、あなた。電話に出ているの」
●Extra Point
呼びかけでなく、自分のsweetheartといえば、「恋人、愛人」となる。状況によっては、「彼氏」「彼女」ということになると思う。
◎Extra Example
“Who’s that gorgeous guy at the counter?”
“That’s my sweetheart. Watch it, Risa, he’s mine.”
「カウンターにいるあのすてきな男の人、誰?」
「わたしの彼よ。変なことしないでね、リサ。彼はわたしと付き合っているんだから」
addressの意味は「住所、所在地、あて名」であると、誰もが知っている。しかし、addressには、「(聴衆に向かっての公式の)あいさつの言葉」や「演説、講演」という意味もある。そしてよくto give an address, あるいはto deliver an addressという言い方で、「あいさつする」とか「講演を行なう」という意味を表現する。これは状況によっては、「発表する」という意味になると思う。
○Practical Example
“Did you hear the address that the foreign minister gave last night?”
“Yeah, he said that Japan is going to send soldiers to other countries.”
「外務相の昨夜の発表を聞いたか?」
「ああ。日本は海外派兵するそうだ」
●Extra Point
to addressと動詞としてもよく使われる。to address someoneで、「(人に)話しかける」という意味になる。また、「(正式な呼び方・正しい敬称で)(人を)……と呼ぶ」という意味でも用いられる。次の例を見てみよう。
◎Extra Example
“How would you like to be addressed, Mr. Srelup?”
“Not as Mr., please. I am Dr. Srelup, and don’t you forget it!”
「スリラップさん、なんとお呼びしたらよいですか?」
「スリラップさんとは呼ばないでくれ。ぼくはスリラップ博士だ。それを忘れるな!」
「いいじゃん!」とか「すごいじゃん!」とか「やった!」という言い方を英語にしたらどうなるか、と時どき尋ねられる。今日紹介するこの“How good is that!”がそれに近いと思う。“How good is that!”という言い方も日常会話でよく使われるし、「いいじゃん!」とか「すごいじゃん!」とか「やった!」という感じをうまく伝えられるのではないだろうか。
○Practical Example
“I just won two free tickets to the Led Zeppelin concert. I mean, how good is that!”
“Wow, Julie, that’s awesome.”
「レッド・ツェッぺリンのコンサートのタダ券が2枚手に入った。やった!」
「わあ、ジュリー、それはすごいよ」
Led Zeppelinは2007年11月26日に、ロンドンのO2アリーナで再結成ライヴを行なうようですね。
●Extra Point
“How X is that!”の構文は、Xの部分にさまざまな形容詞が挿入されて、日常会話でもよく用いられます。
◎Extra Example
“Alexander is bragging about how he’s got three girl friends at once.”
“How weird is that! What an asshole that guy is.”
「アレクサンダーのやつ、3人の女の子と同時に付き合っているって自慢していやがる」
「なんて嫌なやつ! とんでもないクソ野郎だ」
to spell outは、「(語を)1 字 1 字読む[書く]」「1 字 1 字つづる」「(省略せずに)完全につづる」。
○Practical Example
“Did you understand what I said, Ms. Yoshino?”
“Not everything. Could you spell out that long word starting with ‘r’ please?”
「吉野さん、わたしが言ったことはお分かりですか?」
「全部はわかりません。rで始まるその長い単語をつづっていただけますか?」
●Extra Point
to spell outは、「(……を)はっきり[詳細に]説明する」「(……かを)詳細に説明する」という意味もある。
◎Extra Example
“Do you understand what I want you to do on this job, Robert?”
“Not really, Mr. Coophandle. Could you spell it out for me, please?”
「ロバート、ぼくが君にこの仕事で何をしてほしいか、わかる?」
「クープハンドルさん、よくわかりません。詳しく説明していただけますか?」
to stumbleは、「つまずく、よろめく」。
○Practical Example
“What happened to your knee, Lance?”
“I stumbled in the bath. But it’s not bad. I can still ride a bike.”
「ランス、その膝どうしたの?」
「お風呂でつまずいてしまったんだ。でも、重症じゃない。自転車には乗れる」
●Extra Point
日本語の「つまずく」と同じように、英語のstumbleも「とちる、へまをやる、やりそこなう」というように比喩的な意味でも用いられる。
◎Extra Example
“How did the oral test go, Nellie?”
“Awful, Joan. I stumbled badly when the teacher started asking questions in English.”
「ネリー、口頭試験はどうだった?」
「ジョーン、最低だったよ。先生に英語で質問されて、ひどくとちってしまった」
何かをするのに、flexible(「(物事が)融通のきく、柔軟な」「(人が)順応性のある、柔軟に対応できる」)であるのは好ましいいことだ。
○Practical Example
“Omar’s really flexible. He’s a great guy to work with.”
“He has great ideas, and he’s willing to compromise, too.”
「オマールはほんとうに融通のきくひとだ。とても仕事がしやすい」
「すごいアイデアも持っているし、こちらを立ててくれたりもする」
●Extra Point
反意語はinflexible(「がんこな、強情な、融通のきかない」「(規則など)曲げられない、変更できない」「しゃくし定規の」).
◎Extra Example
“Homer’s really inflexible. He never changes his mind.”
“I think you should fire Homer, Mr. Simpson. He’s a burden on all of us.”
「ホーマーは強情だ。絶対に心を変えない」
「シムソンさん、彼を首にするべきです。みんなの重荷になっています」
to winkは「ウィンクする」。誰もがどういうことは知っているはず。
○Practical Example
“Are you winking at me?”
“No, I’m sorry. I’ve just got something in my eye.”
「わたしにウィンクしているの?」
「ごめん。目に何か入っただけだよ」
●Extra Point
in the wink of an eye, あるいは in the blink of an eyeは、慣用句で、「瞬く間に、瞬時に」。
◎Extra Example
“Was Clark here?”
“He was, but he was gone in the wink of an eye, Kent. Who is that guy anyway?”
「クラークはここにいた」
「いたけど、あっという間にどこかに行ってしまったよ、ケント。彼は一体何者?」