事例紹介コラムです。
先週の土曜日にNHKで、「鯉昇れ、焦土の空へ」というドラマが放送されました。広島局の製作で再放送されたものです。初代監督の石本秀一氏を通した広島カープの誕生秘話を追った内容ですが、その前告知を観ていて、「後援会」というキーワードが出てきたので、これは観ないといけんという事で、録画してしっかり観ました。以下、ドラマ内容を抜粋して紹介。


「カープを救えという石本の叫びに応え、立ち上がったのは名もなき市民たちだった。これはカープ存続に人生を捧げた男と、広島市民が起こした奇跡の物語」というセリフから始まりました。
終戦4年後の昭和24年晩夏。日本プロ野球界はセ・パ2リーグ制で再出発という大改革を行い、それまでの8球団から15に増設。これを機に広島にプロ野球団創設の行動を起こしたのは谷川元代議士。㈱廣島野球倶楽部創立準備委員会の委員長に就任して、広島カープが誕生。従来のプロ球団が経営資金を大企業に頼るのが常識である中、それを地元自治体の出資で賄う計画を打ち出した。
「県民みんなのチームを作りたい」という谷川氏の熱い思いが、オーナー企業を持たない日本で唯一の市民球団を広島に誕生させた。チーム名は「カープ」。鯉は広島市を流れる太田川の名産であり、滝を上る姿から生命力の象徴とされる。原爆の悲劇から立ち上がろうとする広島にピッタリのネーミング。

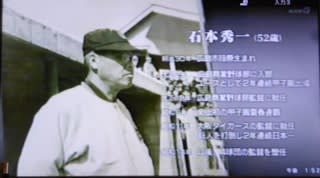
初代監督は石本秀一氏(52歳)。監督として広島商業高を優勝させたこと4回。プロ野球誕生とともに大阪タイガースに招かれ、2年連続日本一を達成。以後、4球団の監督を歴任と実績は十分。加えて野球人生最後の華を故郷広島で咲かせたいという熱い思いだったが、広島で彼を待っていたものは、選手がまだ一人もいないという厳しい現実。3ケ月後は開幕という時期に。
昭和25年シーズン開幕後、次第に成績も最下位に転落して低迷。財政もセリーグ加入金が未払いという苦しい状態が続く。観客収入がその日の勝敗に応じて各チームに分配される制度が響き、いくら客が入っても負け続けていたため、なかなか収入が増えない状態が続く。その年の夏を迎える頃には選手への遅配が当たり前に。石本監督は野球の事に加えて、経営の算段もしなくてはならない状態。
その結果、断腸の思いで2軍を解散。選手とコーチ20人を解雇。しかし、それでも事態は改善せず、地元企業から借りていた合宿所を家賃未払いで追い出される始末。その後、チームは御幸荘を合宿所として利用。
広島カープは何とか1年目のシーズンを終了。41勝96敗1分け。勝率2.99で最下位。この時、すでに球団の財政は火の車で終末の時が近づいていたとか。昭和26年に国体を初めて初開催。2年目のシーズンの開幕直前に、球団役員会において大洋への吸収合併の話が持ち上がる。市民球団の限界として絶望感に覆われるが、決議になりそうな役員会場の周りに、合併反対の市民が押し寄せる。
万策尽きて、これ以上の借金は不可能という役員会で、吸収合併が決まりかけた時に石本監督が、「市民は貧乏ながら戦い続ける境遇を、自分達とダブらせて応援してきた。カープは広島の心。解散だけは中心して、一切を自分に任せて欲しい」と言い、市民による募金、後援会設立を提案。「会員から募金を募る。カープはまだ生まれたばかりだから余白がたくさん残っている。その余白一つ一つ埋めるのは自分達(フロント)でなく、市民の皆さん。市民の皆さんにカープの未来を委ねましょう」と。


石本監督は企業という企業、工場、官庁、町内会まで後援会を作ってもらうよう一つ一つ頼んで回る。新聞社(中国新聞)には募金を呼び掛ける文章を書くので、無条件で(紙面に)掲載して欲しい。石本監督がぶち上げた後援会案に役員も賛同し、土壇場で合併中止、カープの存続が決定。
「後援会の結成急ぐ。選手も県民の絶大な声援に応えて、苦しくともとにかく頑張ってくれることにより、私も涙が出るほどうれしい。今このカープを潰せば、日本に二度とこのような郷土チームの姿を見る事はできないだろう。私も大いに頑張る。県民もこの際、大いに協力してカープを育てて欲しい」
と朝刊に寄稿。
石本監督は県庁舎前で、市民に直接呼びかける演説を行い、これを手始めに怒涛の後援会作りを開始。この年の後援会結成の知らせを聞けば、石本監督はどこへでも出向いたとか。試合を終えたばかりの選手を引っ張り出して駆けつけ、ファンサービスを実施。この間、石本監督は連日、地元新聞にカープ支援を呼びかける記事を寄稿。
後援会員数の推移: 4月:3,000人突破/5月:5,000人突破/6月:8,000人突破/7月:10,000を突破。


石本監督の気持ちを受け取った市民は、今度は自ら試合前に球場に募金樽を設置して広く募金を呼びかけた。カープ名物「樽募金」の始まり。昭和26年7月29日に後援会発会式を開催。この時の後援会員数は13,141人、支援金総額は2,715,784円。コーヒー1杯が30円の時代で現在の勝ちで実に1,800万円を超える額がカープに託されたとか。
石本監督はその後も後援会から1,000万円の募金を集め、他球団のスター選手獲得に成功するなど、強いカープ作りに精魂を尽くした。しかし、監督就任から3年目、自ら立ち上げた後援会の一部にワンマン体制を批判され、突如球団を追われた。それから4半世紀後の昭和50年に悲願の初優勝。その瞬間を石本氏(当時77歳)も自宅でTV観戦していたとか。


素晴らしい話でした。「復興」という付加価値も備わっている球団でした。まさに「真実の樽募金」、「市民(県民)後援会のルーツ」であり、当ブログで今まで抱いてきた「後援会」のイメージそのものの話でした。資金も人材もない地方クラブが産声を上げてから、どのようにもがきながら世の中と戦っていくのか、リアルによく描けていました。このまま、サッカークラブにもあてはめられる貴重な事例です。
一番参考になったのはやはり、後援会の誕生秘話です。後援会については以下のアーカイブにたっぷり載っていますが、基本的に「カネ」と「ヒト」。後援会とは、集金とマンパワーを集めるシステムですから。広島の事例でも、石本監督が呼びかけて、職域と地域の後援会組織を立ち上げていき、後援会結成の知らせを聞けば、選手を引き連れてどこへでも出向いたとしています。ドラマでは選手が壇上で「炭坑節」を歌うシーンがありました。これはまさにちょうどJ2を狙う当たりのサッカークラブが行う様ではないかと。また、試合会場で市民が募金活動を行うシーンがありました。いいですねー スタッフだけがやるのではなく、後援会が駆けつけて市民(県民)が行う募金活動。まさにこれが県民クラブではないでしょうか。うらやましい。
このドラマには、「後援会はものを言われるから作りたくない」「選手は試合だけ戦ってくれればいいから街には出さない」という価値観は存在しません。その時の苦労があるから、その後の初優勝が実現するのです。よく「100年続くクラブ」という表現を耳にしますが、広島カープのこの生き様を見れば、こういう市民(県民)クラブこそが100年続くと思います。格好だけで県の隅々にまで浸透できず、「市民の宝」になりえていないところがあれば、しんどいかなと思います。「カープは広島の心」という石本監督のセリフがありましたが、広島県民にはこういう地域の宝があっていいですね。
後援会関連⑫(総合):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20140607
〃 ⑪(千葉):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20131206
〃 ⑩(松本2):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20130707
〃 ⑨(松本):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20121107
〃 ⑧(仙台):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20111226
〃 ⑦:(大分2):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20111203
〃 ⑥(川崎・麻生区):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090823
〃 ⑤(湘南):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090801
〃 ④(鳥栖):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090608
〃 ③(甲府):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090126
〃 ②(大分):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20090117
〃 ①( 柏 ):http://blog.goo.ne.jp/kataru-kai/d/20081211















