保存資料を整理していたら下のコピーが出てきた。18×15㎝ほどの紙に書かれているがれっきとした公文書である。
御刑法方根取から御昇副頭に当てた、処刑に関する指示書である。
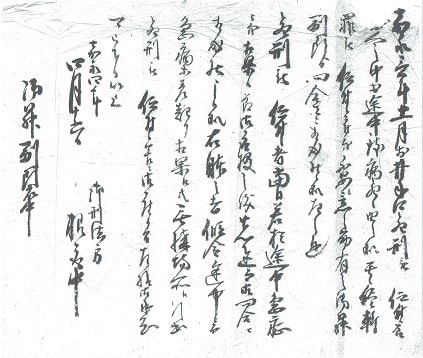
この文書の日にちが大変興味深い。嘉永四年四月十六日とあるが、この日に宝暦の改革以来80年ぶりとなる火炙りの刑が実行された。
宝暦の改革における肥後藩の「御刑法草書」は近代自由刑の発祥として知られるが、放火や残忍な殺人などは「火刑」が継続された。
先のコピーとは別に、一緒に出てきた宇野廉太郎の「肥後藩におけるー空前絶後の火炙りの惨刑」という文章にくわしい。
地回り役者の松五郎という人物は、なかなかの男前で女たらしで、女と遊んではだましては金をせびったりして生活していたが、或時
金に困り、知り合いの女から金を奪い家に放火して焼き殺してしまった。数件の類焼にも及んだらしい。
松五郎は逃亡したが、筑後の役者仲間の所に居ることが判って捕らえられた。そして下河原の処刑場で「火刑」となったのである。
その日は長六橋の上は見物人でごった返したという。火刑の模様も宇野氏は語っているが、これはやめておこう。
見物に来ていたある女が、竹矢来の外で泣き叫ぶのを見て、獄吏が「広い世間には松五郎に似た男もいるだろう」と慰めたところ、女は
「にたつよりもやあたつ」と語り、のちには気が狂ったと宇野氏は書いている。
この言葉、熊本人でもよく理解ができないであろうが、「~たつ=達」であり「達=~したもの」の意であろう。
「似た者よりも焼いた者」ということになるが、女は「似た人ではなく、(火刑で)焼かれた人」松五郎以外にはないといっているの
である。
ところで上記古文書だが、次のように記してある。
嘉永三年十一月於井出口為刑被 仰付候節
■人之中於途中致病為之由之処其侭斬
罪被 仰付候ニ付■不安意之筋有之御昇
副頭ゟ問合せニ相成居候処左之通
為刑被 仰付者當日若於途中急症
ニ而相果候節御取放之儀先達而御問合ニ
相成居申候処右躰之者假令途中ニ而
急病等差起相果候共無構場所江引出
為刑被 仰付置候ニ御座候左様御承知
可被下候以上
嘉永四年 御刑法方
四月十六日 根取中
御昇副頭衆中
罪人が途中で病気になったらどうするかとの、執行役の御昇衆の副頭からの問合に対し、たとえ病気でも死去していても火刑にするよう
にとの決定事項の通達である。(火刑の執行は御登衆が行う)
松五郎の処刑の日と同じ日付であることから、松五郎に対しての処断であることに間違いなかろう。
「御刑法草書」とはいえども、このような極悪な事件に対しては救いようがなかった。















