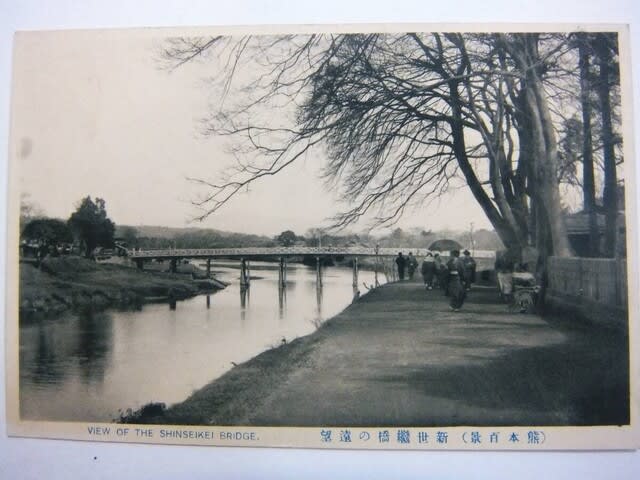20日の熊本史談会例会で2時間ほど講演を担当したが、82爺はすっかり疲れてしまった。
帰宅後午睡をし、昨日も椅子に座ったまま何度も昼寝をする始末である。講演は聞き手専門が気楽で良い。
今後は又、ブログ三昧で過ごそうと思うが、それとともに資料の整理をしようと思い立って動き始めた。
集めた先祖附などはA4の袋に入れて、段ボール(トマトジュース・桃ジュース缶の箱)に入れている。
まずはデスクの足元にある8個の段ボールの内4個を引っ張り出して中身を点検する。
袋の中身をすべて確認、捨てるもの一つもなし・・・ただリスト化出来たのみ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(1)1、秋山儀右衛門家・高本孝太郎家・藪九十郎家 先祖附(時習館関係)
2、両角家先祖附・新田藩両角家系図・荒木太平家先祖附(御祖母様の実家=荒木山城系・白井家先祖附
3、柏原新住家(4,500石)先祖附
4、小林恒太郎家先祖附(田辺城籠城衆・神風連関係)
5、小崎家先祖附
6、余田家・横山家・吉住家・吉山家・吉弘家・横井家・吉冨家・芳澤家・吉見家・吉岡家 先祖附
7、米村勝太郎家・吉海良作家 先祖附
8、河方家(松下民部少輔)、山崎家(本因坊) 先祖附
9、高見怘家・高見武之家 先祖附
10、三井家 先祖附
11、上林家 先祖附
12、佐方信博氏著「つづら文から」コピー
13、中瀬家(松下嘉兵衛)先祖附、中瀬家傳略
14、財津源之進家・平川弥丈家 先祖附
15、大塚源次家(5代・久成=大塚退野)先祖附、大塚家から拝領の「大塚家系図」
大塚退野に関する論考「九州儒学思想の研究」抜粋二件
(2)茶道関係
1、鷺絵源三郎久重覚書
2、同上関係 茶道古典全集・第九巻「久重会記」(p1~491)
「茶道四祖傳書」から「三齋公傳書」(p143~244)
3、茶道「利休編」全集巻の九 (抜粋p198~299) 2、3については寺井正文氏より拝受
4、不審菴「教授者講習会講座用教本
5、三斎公御流茶道之傳
6、その他肥後古流お稽古時の忘備録その他
(3)1、荒木村重関係 「荒木善右衛門」「細田七蔵」先祖附、ご子孫・荒木幹雄氏関係史料
2、横山隆蔵家先祖附 1,056石
3、高瀬藩、西氏・松村氏関係先祖調べの資料
4、大竹甚平家先祖附(妙立寺に墓地)
5、本庄源次家・国友儀兵衛家・同 半左衛門家・道家重三郎家・村井虎之允家(信長家臣・京都所司代村井長門守子孫)
平山伊一郎家(木下内記子孫) 先祖附
6、木下嘉納家・沼田小一郎家・沼田門太家・沢村衛士家 先祖附
7、門池群蔵家・河喜多治部左衛門家・同 烈蔵家・同 和学家・岡松俊甫家・鬼塚源八家・山田熊太家・山田昭九郎家・
山田傳次郎家・曽我庄三郎家・小畠富之助家 先祖附
8、高田家先祖附、ご子孫から拝領の高田家先祖系譜 、宮川龍太家・寺内平格家・八木田小家 先祖附
9、垂水家 先祖附及び系図 (熊本史談会・中村裕樹氏拝領)
10、沼田門太
11、伊津野氏関係 伊津野吉太夫家・伊津野十内家先祖附 及 別当上座町人伊津野家等 伊津野氏調査史料拝受
12、坂崎家先祖附 ご子孫H様御所蔵の先祖附及び関係資料と読み下し文
(4)1、田添源次郎家史料 ご子孫O様所蔵の先祖附及び関係資料をご提供いただきました。
2、久野次郎左衛門家先祖附 御所蔵の佐久間不干斎の久野氏宛書状をご提供いただきました。
3、魚住家関係資料 黒田如水感状 系図その他 東京都在住のご子孫からご提供いただきました。
4、緒方喜一郎家 山鹿在住のご子孫T様から系図その他のご提供をいただきました。
5、松宮家先祖附 細川幽齋室沼田氏の姉聟松宮氏 御近所にご子孫がお居ででした。
6、續小助家・谷助九郎家・長尾権五郎家・長束(田中)孫三郎家・津川(斯波)平左衛門家 先祖附
7、尾藤閑吾家・平野嘉門家・平野甚九郎家・平野角蔵家・平井井平家・平野五郎家・廣瀬新家・平野八十郎家・東雲衛家・東英四郎家・
平井勘右衛門家・平野九郎太郎家・平野庄左衛門家・平塚孫三郎家・平川貞四郎家・平川弥丈家・平井甚十郎家・久光善太家 先祖附
8、藪田 道家・田中八兵衛家・天野善次家 先祖附
9、庄林曽太郎家・白木弾次家・城市郎家・城安太家・白井一五家・白井善三家・白石傳太家・志賀太郎家・正垣九十郎家・庄野助市家
白石忠家・下田才兵衛家・下田平蔵家・志賀助十郎家・重見治三郎家・篠原新吾家・嶋田平三家・清水九郎家・下津縫殿家・白木五三家・
嶋田九郎次家・生源寺市家・樹下一平家・下村作衛家・嶋田徳三郎家・庄村省三家・白杦少一家・首藤十次郎家・志水凍家・同 新九郎家・
志水小一太家・同 小八郎家(松井家家臣) 先祖附