保坂廣志『戦争動員とジャーナリズム ―軍神の誕生―』(ひるぎ社、1991年)を読む。
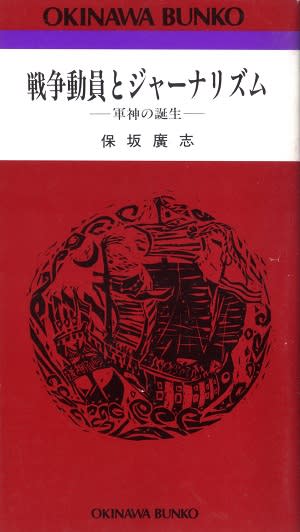
沖縄県与那国島に生まれ育った、大舛松市という人物がいた。彼は秀才として那覇で勉強し、念願の陸軍士官学校に入学した。その後陸軍歩兵部隊に入隊、最前線を渡り歩き、ソロモン諸島のガダルカナル島において、わずか25歳で戦死する。
中央各紙は、大舛中尉の武勲(感状上聞)を一面トップで掲載した。「軍神」化である。
本書は、そのことが沖縄において如何なる意味を持ったのかを追う。それは、軍部による利用ではなく、圧倒的に、新聞や教育界における狂騒的ともいえる祀り上げであった。このイコンは、戦意高揚のためにとどまらず、死ねる教育、死ねる覚悟の醸成のために使われつくしたのである。もちろんそれは、軍国主義のなかでの皇民化教育という構造的な帰結であり、住民自らの精神であったということは決してできない。
それにしても、メディアと教育現場が自己批判力を持たず、既存の権力強化へと向かっていく様は、現在と相似形であり、嫌になってしまう。ジャーナリストや教育者を名乗るということは、その出自を見つめてこそ可能になるのではないか。
戦時中、「沖縄新報」で軍神大舛の記事を書いたのは、主に、牧港篤三氏であったという。氏は戦後の「沖縄タイムス」創立メンバーであり、『鉄の暴風』や『沖縄自身との対話/徳田球一伝』(>> リンク)といった著書をものしている。本書でも、著者との対談において、当時のことを回想しつつ、「若い人達が、何も知らないうちに戦争に巻き込まれていくのを見るのが忍びない」と語っている。これはまさに現在進行形の状況である。そして、既存のメディアにはあまり期待できない。
わたしは、テレビや週刊誌の無批判なる情報操作に抗する力は、インターネットを通じた多数の声に他ならないと(本当に)思っている。










