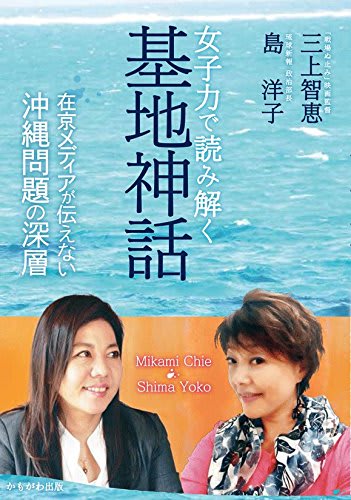ラルフ・ピーターソン『Triangular III』(Onyx、2015年)を聴く。

Ralph Peterson (ds)
Zaccai Curtis (p)
Luques Curtis (b)
『Outer Reaches』(2010年)のあまりのコピーバンドぶりに愕然として、ピーターソンを追いかけるのがバカバカしくなっていたのだが、これはなかなかの盤である。
ピーターソンは「Triangular」というシリーズでピアノトリオ物を出していて、1枚目がジェリ・アレン、2枚目がデイヴィッド・キコスキ。そして今回の3枚目がザッカイ・カーティス。なおベースはザッカイの弟である。以前にテナー吹きのレイモンド・マクモーリンさんが、好きなピアニストはデイヴィッド・ブライアントとザッカイ・カーティスだと話していて、いつかちゃんと聴こうと思っていたのだ。
このザッカイ・カーティスのピアノがスマートで尖ってもいて確かに素晴らしい。才気煥発という感じである。ピーターソンは、相変わらず、不要な土煙をたてながら爆走する無駄にハイスペックなクルマのようで(『マッドマックス』を思い出した)、やはりトマソン=人間扇風機たるものこうでなくては。
曲がまたいい。サム・リヴァース「Beatrice」、ジョー・ヘンダーソン「Inner Urge」、それにウォルター・デイヴィス・ジュニアのオリジナルが3曲(渋い)。こういうのが好きなんだろうね。ワイルドな爆走に知的なメロディ、悪いわけがない。
ピーターソンの好きなユニットは「Fotet」なのだが、ピアノトリオも追いかける価値大。この人にはシンプルな編成が合っているに違いない。
●ラルフ・ピーターソン
ウェイン・エスコフェリー『Live at Smalls』(2014年)
レイモンド・マクモーリン『RayMack』、ジョシュ・エヴァンス『Portrait』(2011、12年)
ラルフ・ピーターソン『Outer Reaches』(2010年)
ベキ・ムセレク『Beauty of Sunrise』(1995年)