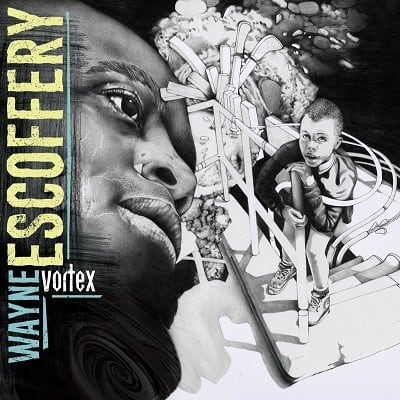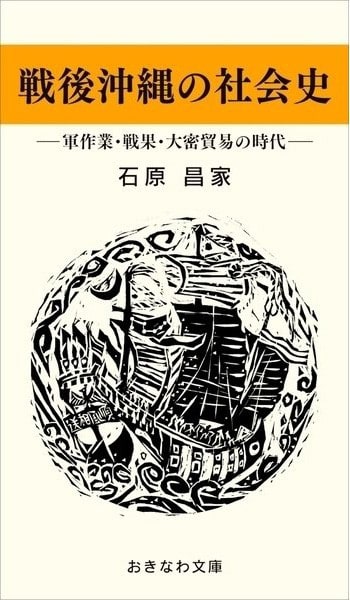マブタ『Welcome to This World』(Kujua Records、2017年)を聴く。

Shane Cooper (b, g, Juno 106, Korg Minilogue, Microkorg, Moog Slim Phatty, Rhodes)
Bokani Dyer (p, Rhodes, Korg Minilogue)
Marlon Witbooi (ds)
Sisonke Xonti (ts)
Robin Fassie-Kock (tp)
Reza Khota (g)
Shabaka Hutchings (ts) (tracks 2 & 3)
Buddy Wells (ts) (track 5)
Chris Engel (as) (track 5)
Janus Van Der Merwe (bs) (track 5)
Tlale Makhene (perc) (tracks 2,5,7)
『ラティーナ』誌2018年6月号の南アフリカジャズ特集に掲載されている。
実ははじめは割と大人しくパンチが無いという印象だったのだが、他のものを聴いてはまた戻っているうちに面白くなってきた。シェーン・クーパーのベースがずっと効いており、その周囲をきらびやかにまとった要素が多彩。展開が変わるときのナチュラルさが良いと思える。確かにダンサブルな時間があり、また、アフリカ音楽だと思わせてくれるメロディもある。気持ち良い。