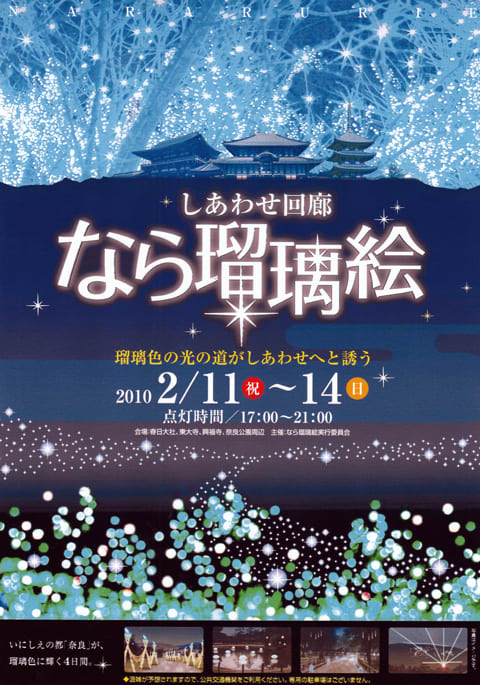大和郡山市小泉町の国道25号線沿いに「うなぎ川はら 大和郡山店」がある。以前から世評が高いし、最近では県ビジターズビューローの「三ツ星グルメ(奈良グルメガイド)」にも掲載されたので、ぜひ行こうと思っているうちに、今月に入って(2月2日)、奈良店がオープンした。それが「うなぎ川はら 三条家」(奈良市下三条町35)である。
※「三ツ星グルメ(奈良グルメガイド)」(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/804d341b856bf095e707220092a325d2

2月末までは、OPEN限定メニューとして「うなぎ丼 上」(鰻4切 通常価格1900円)が1300円、「うなぎ丼 並」(鰻3切 通常1500円)が1000円、という出血大サービスである。3月からはメニューが増え、うな重2300円、ひつまぶし2400円、白焼定食2350円、蒲焼定食1550円、お子様丼900円、うまき600円、肝吸い250円 など(丼は通常価格になる)。

トップとすぐ上の写真は「うなぎ丼 並」である(私の好みでタレは少なめ。100円でご飯を大盛りにできる)。「三ツ星グルメ」には《うなぎは、肉質や味、食感のバランスがよく、品質も安定している宮崎産を使用。当日の朝さばいたものを備長炭で香ばしく焼き上げ、あっさりめのタレでいただく。地元産の米“ひのひかり”との相性も抜群である》とある。
※参考:鰻丼とタレの問題(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/a1ad2ff2a880f97a34be6398807a05d3

うな重(2300円 グルメWalkerより)。3月からのメニューである
グルメWalkerには《蒸しを入れずに生のままこんがり関西風に地焼きする。国内産のうなぎを秘伝のタレと備長炭を使い、皮はパリッと身はふっくらジューシーに炭火焼き》《色合いと香りのよいものをブレンドした特製山椒を散らせば、さらにおいしく味わえる》とある。
http://gourmet.walkerplus.com/161082479001/

鰻が1切れ多い「うなぎ丼 上」。「タレなし」で注文した丼に、自分でタレを少しかけた
雑誌「ぱーぷる」別冊の『美食倶楽部』(08年版)によると《いくら納得できる鰻を手に入れることができても、店で品質管理ができなければ元も子もない。そこで、店(大和郡山店)の裏に鰻専用の小屋を併設。中は常に一定の水温に保ち、鰻を生かしておく水は珊瑚礁の濾過装置に通して循環させる。これだけの設備を整えている店は全国でもそうはないだろう。これもひとえに「お客様にほんまに旨い活の鰻を食べてもらいたい」との一心から》とある。これはすごいことだ。

ずいぶん以前、三島市(静岡県)で、日本一といわれる鰻の名店でうなぎ丼をいただいたことがある。もちろんとても美味しかったのだが、その秘密の1つは、鰻を一定期間、富士の湧水で生かしておき、肉の味を調えるからだと聞いたことがある。川はらはそれを人工的に再現しているわけで、全く理にかなっている。

「うなぎ川はら 三条家」は、JR奈良駅から三条通を東に徒歩5分、近鉄奈良駅からは三条通を西に徒歩15分。奈良ワシントンホテルプラザの東、「菓匠 千鳥家宗家」の並び(東隣)にある(もとローソンのあった場所)。
便利な場所で、本格派の関西風うなぎ丼が味わえる。ぜひお訪ねいただきたい。
※うなぎ川はら 三条家(奈良店) 奈良市下三条町35 電話0742-24-1138
営業時間 11:00~14:30 17:00~20:30(ラストオーダー 30分前) 火曜休
※「三ツ星グルメ(奈良グルメガイド)」(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/804d341b856bf095e707220092a325d2

2月末までは、OPEN限定メニューとして「うなぎ丼 上」(鰻4切 通常価格1900円)が1300円、「うなぎ丼 並」(鰻3切 通常1500円)が1000円、という出血大サービスである。3月からはメニューが増え、うな重2300円、ひつまぶし2400円、白焼定食2350円、蒲焼定食1550円、お子様丼900円、うまき600円、肝吸い250円 など(丼は通常価格になる)。

トップとすぐ上の写真は「うなぎ丼 並」である(私の好みでタレは少なめ。100円でご飯を大盛りにできる)。「三ツ星グルメ」には《うなぎは、肉質や味、食感のバランスがよく、品質も安定している宮崎産を使用。当日の朝さばいたものを備長炭で香ばしく焼き上げ、あっさりめのタレでいただく。地元産の米“ひのひかり”との相性も抜群である》とある。
※参考:鰻丼とタレの問題(当ブログ内)
http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/a1ad2ff2a880f97a34be6398807a05d3

うな重(2300円 グルメWalkerより)。3月からのメニューである
グルメWalkerには《蒸しを入れずに生のままこんがり関西風に地焼きする。国内産のうなぎを秘伝のタレと備長炭を使い、皮はパリッと身はふっくらジューシーに炭火焼き》《色合いと香りのよいものをブレンドした特製山椒を散らせば、さらにおいしく味わえる》とある。
http://gourmet.walkerplus.com/161082479001/

鰻が1切れ多い「うなぎ丼 上」。「タレなし」で注文した丼に、自分でタレを少しかけた
雑誌「ぱーぷる」別冊の『美食倶楽部』(08年版)によると《いくら納得できる鰻を手に入れることができても、店で品質管理ができなければ元も子もない。そこで、店(大和郡山店)の裏に鰻専用の小屋を併設。中は常に一定の水温に保ち、鰻を生かしておく水は珊瑚礁の濾過装置に通して循環させる。これだけの設備を整えている店は全国でもそうはないだろう。これもひとえに「お客様にほんまに旨い活の鰻を食べてもらいたい」との一心から》とある。これはすごいことだ。

ずいぶん以前、三島市(静岡県)で、日本一といわれる鰻の名店でうなぎ丼をいただいたことがある。もちろんとても美味しかったのだが、その秘密の1つは、鰻を一定期間、富士の湧水で生かしておき、肉の味を調えるからだと聞いたことがある。川はらはそれを人工的に再現しているわけで、全く理にかなっている。

「うなぎ川はら 三条家」は、JR奈良駅から三条通を東に徒歩5分、近鉄奈良駅からは三条通を西に徒歩15分。奈良ワシントンホテルプラザの東、「菓匠 千鳥家宗家」の並び(東隣)にある(もとローソンのあった場所)。
便利な場所で、本格派の関西風うなぎ丼が味わえる。ぜひお訪ねいただきたい。
※うなぎ川はら 三条家(奈良店) 奈良市下三条町35 電話0742-24-1138
営業時間 11:00~14:30 17:00~20:30(ラストオーダー 30分前) 火曜休