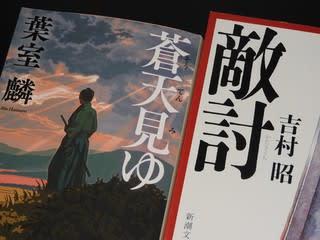950 茅野市玉川上赤坂の火の見櫓 4脚6〇型 撮影日180107
■ 平面が4角形の櫓に6角形の屋根を載せた変則的な組合せで、脚元に倉庫を納めた火の見櫓。
屋根下地の様子がよく分かる。なるほど、4本の柱と6角形の屋根の取り合いはこうすればよいのか。 下り棟の下地材の平鋼を伸ばして蕨手にしている。屋根のてっぺんの避雷針に付けた風向計はどうなっているのかな?
下り棟の下地材の平鋼を伸ばして蕨手にしている。屋根のてっぺんの避雷針に付けた風向計はどうなっているのかな?
別の方向から見ると・・・、どうやら羽(矢羽と呼んでいいのかな)が曲がってしまっているようだ。羽は2枚あるのが一般的だから、1枚はとれてしまったのだろう。
見張り台の半鐘はつるりんちょ、この踊り場の半鐘は乳付き。この組み合わせをどう考えるか・・・。
乳付きの方が古いということを前提にすれば、火の見櫓を建設して何年か後に見張り台の半鐘をここに移動して、見張り台に新たに設置したと考えるのが妥当? でもなぜわざわざそんなことをする? 相当重い半鐘を移動させるのはかなりしんどいはず。これを片手で持って、梯子を下りてくることは困難ではないか。
では、初めからこの状態だったか・・・。
鉄筋コンクリート造の陸屋根の端部と火の見櫓の脚が干渉しあっている。もちろん意図的だろうが、なぜこんなことをしたのだろう?









































 ①
① ②
② ③
③ ④
④