■ 「ゼロ・ダーク・サーティ」を観た。
ビンラディンの居場所を一体どのようにして突き止めたのだろう・・・。困難を極めていたビンラディンの居場所の特定。CIAの女性情報分析官・マヤ(写真)の執念によって、ついに特定された。パキスタンの首都・イスラマバードの近郊、アボッターバード(Abbottabad)という都市で。
映画の終盤、ゼロ・ダーク・サーティ、午前0時30分、特殊部隊を乗せたステルスヘリ2機がビンラディンが潜んでいる要塞のような豪邸に向けて飛び立つ。豪邸突入、ビンラディン射殺。
映画のラスト、主人公・マヤただ一人を乗せて飛び立とうとする輸送機。パイロットの「で、どこへ行く?」という問いかけ、これはマヤに対するものではなく、世界の人々に対する問いかけだろう。ビンラディンの殺害。で、世界はどこに向かうのか?
この映画の製作にアメリカ政府が「情報」を提供しているとのこと。このような映画をつくり、公開することができるアメリカはやはり凄い。



















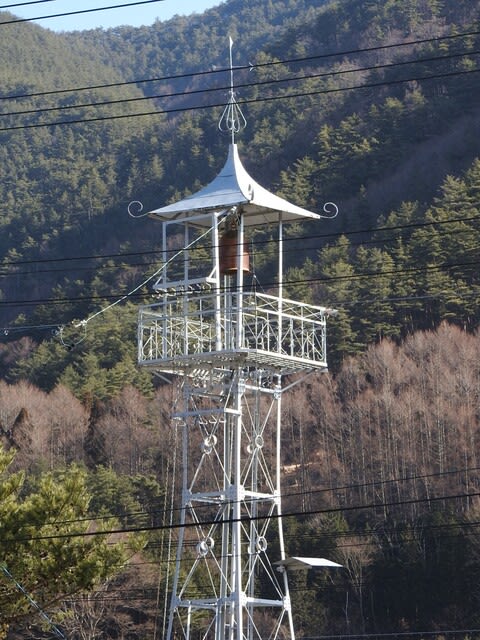
















 360
360 320
320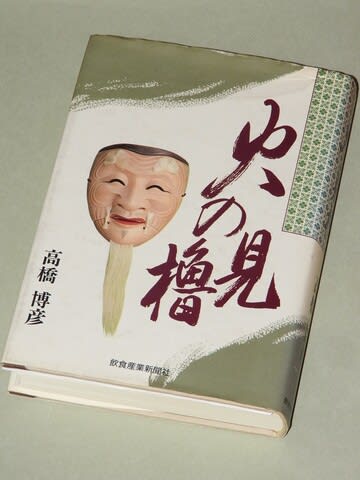 320
320 420
420
 320
320