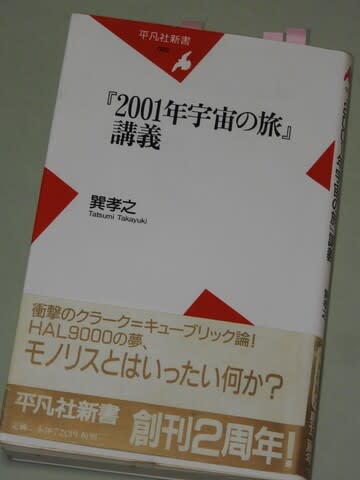
■ アーサー・C・クラークのSF小説『2001年宇宙の旅』はスタンリー・キューブリックによって映画化された。SF映画は好きだが、とりわけ「宇宙もの」が好きでレンタルDVDでよく観る。だが、この映画を超える作品にはまだ出会っていない。SF映画の、いや洋画のベスト1だ。ちなみに邦画では松本清張原作の『砂の器』。
『2001年宇宙の旅』に出てくるモノリスや後半に描かれているボーマン船長の視覚体験については様々な解釈が与えられている。モノリスは人類の進化に関わる造物主(神)の存在を暗示するものだと僕は思っている。また、ボーマン船長が見たのは(同時に僕たちも見ているわけだが、)宇宙の空間旅行ではなく(と敢えて書く)、時間旅行の映像表現だと解釈している。遙か彼方の未来からまだ生命が誕生していない宇宙、というか地球への旅行。現在から未来、未来からいつの間にか過去へつながる時間旅行、そして生命誕生から猿人への進化・・・、そう生命の輪廻。
「『2001年宇宙の旅』講義」巽 孝之(平凡社新書2001年発行!)をまた読み始めた。
この本で著者の巽氏はモノリスについて次のように書いている。**人類は、じつは神ならぬ地球外知性体によってもたらされた石板(モノリス)状の教育装置の力で、四〇〇万年前(小説版では三〇〇万年前)に猿人だった時代より密かに誘導されてきた。**(14頁)
また、後半ボーマン船長の視覚体験については**これまで映画版『2001年』後半の万華鏡的シークエンス(*1)が、じつはよくいわれるような麻薬幻想でもなければ超絶体験でもなく、たんにモノリスという名のもうひとつのコンピュータ・マトリックスがボーマンという人間を素材にその生体情報をカットアップ/リミックス/サンプリングしているシーンにほかならないことが了解されよう。**(63頁)と書いている。
*1 引用者である僕の注:ソリッドで金属的なシーンは、超未来へと進む視覚的表現として、その後に出てくるシーンは非常に有機的で柔らかく、生命誕生前の水中のようなイメージとして僕は観る。
この本を読み終えたらクラークの原作を読もう。映画も観よう。
昨年の5月に文庫本の大半を処分した。僕が残したSF作品はこれだけ。アーサー・C・クラークの作品では『2001年宇宙の旅』1冊のみ。












