■ 日本の風景は「水」によって特徴付けられる。輪郭が曖昧な水っぽい風景は水彩画が相応しく、油彩画では表現が難しい。水彩画でも輪郭をペンで きっちり描いて、透明水彩絵の具で淡く着色するという私の描法は日本の風景、特に遠景には適してはいないだろう。なぜなら水っぽい風景では春に限らず遠景の山並みなどの輪郭線は不明瞭で霞んで見えるから。このようなことは理解しているが、私の場合、風景の構成要素の形、要素間の関係、即ち風景の構造を捉えることに関心があり、その把握と表現に力点を置いている。
若狭宣子水彩画展 「空」
11月8日(金)から今日10日(日)まで3日間の会期でBLUE HOUSE STUDIO(長野県東筑摩郡朝日村針尾)で開催された作品展を昨日(9日)観てきた。在廊中の若狭さんと名刺交換して、作品についてあれこれ話しをすることができた。有意義なひと時だった。
 260
260枚目の名刺をお渡しした画家・若狭宣子さん
展示作品は私の描法とは対照的で、対象の形を明確に表現したものはなかった。上掲写真に写っている作品は水をたっぷり含ませた絵筆で色が紙に置かれ、後は紙の表面の水の作用によってグラデーショナルな広がりになっている。従って形も曖昧だ。
会場に掲示されている挨拶文に**知ろうとし、理解ろうとする気持ちは持ち続けながら、今の時点での知っていることを結論のように絵の中に 「こう感じました」と持ち込まないで描きたいと思いました。**という一節があった。
なるほど、そうであるなら、表現されるのは確定的な形ではないし、確定的な色でもないのだな、と得心した。ただし若狭さんは常にこのように思っているのではないのだろう。会場に置かれていた絵はがきには展示作品とは別の表現のものがあったから。複数の描法、表現法を持っていると、その時その時の気持ちというのか、想いに相応しい描法を選択できるという強みがある。
展示作品を鑑賞者が自身の美的感性によって、美しい絵だなと感じようが、理性的で分析的な見方をしようが、構わないだろう。作者の手を離れた作品は観る者に委ねられるのだから・・・。
会場に置かれていた「岳人」という月刊誌に掲載されていた若狭さんの文章に次のような下りがあった。
**見える物は人それぞれで違うと思います。**
**あなただけが見出した風景を表現する喜び**
まったくその通りだと思う。























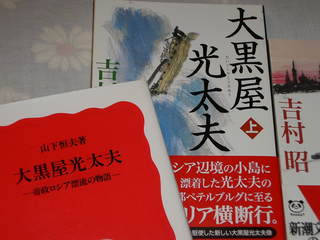 ①
① ②
②
















