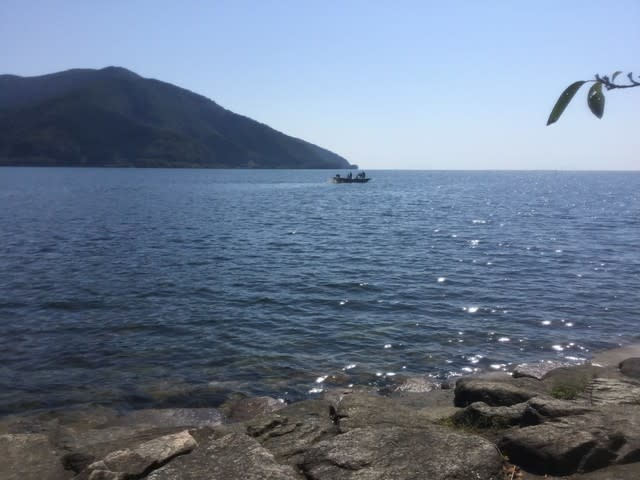父の第四歌集 「 永遠と木草 」( 昭和 57年 )の中の「 木ノ本 にて 」
より
木ノ本にわれら来りて裏通り いちゃうの大木並立つところ
いちゃうより眼移せば中空に 未だ輝かず白き半月
たしかなる季の過ぎ行き梢高く 黄の残葉のいちゃう仰げば
木ノ本の本陣なりし薬種屋に げんのしょうこをわが求めたり
木ノ本は湖北の旧伊香郡の中心地 、北国街道の宿場町として栄えた所
で今は長浜市。
私の思い出では、列車で若狭へ帰省する際 、北陸本線で木ノ本と敦賀
の間はとても雪深かった印象しか残っていません。
今回の車の旅では、まず木之本地蔵にお参りした後、北国街道沿いの
古い家並を歩きながら写真を撮ってきました
父の歌に出てくる「 ゲンノショウコ 」は、昔から下痢止めの薬草と
して使われています。
旧本陣は薬局になっており、明治26年、先先代の当主は日本薬剤師の
第一号の免許を取得されたとか。
近くの伊吹山は薬草の自生地としても知られています。
父の第三歌集 「 しらぎの鐘 」( 昭和 57年 ) の中の「 湖北遊草 」より
びわのうみ その北岸をわれら行く 秋の光はけぶらへるなり
たたえたる水あをぐろく晩秋の 光あびるびわのみづうみ
琵琶の水 鈍き銀いろに光りつつ 湛へたりけり さざなみもなく
歌集「 木草と共に 」より
父は師と仰ぐ歌人 若山牧水の「 自分は自然の一部である。また、自分
は自然の裡 ( うち ) にある 」という考え方に共鳴していました。
父は「 自然に溺れた。平凡な雑木雑草に心を惹かれた。私の歌が平凡な
のは、あたりの自然が平凡なのと同じであろう。」と歌集の後記で述べ
ています。
琵琶湖周辺へも飽きることなく歌友と共にで出かけています。
その歌友に 「 同じ道でも四季によって感動が違う。去年と今年 、昨日
と今日、又朝と夕暮れとでも異なる。毎日毎日が新鮮である。」と
語っていたそうです。
写真は琵琶湖 北岸 筆者 撮影
毎日毎日が新鮮である、という感性は素晴らしいですね。
とくに齢をとってからは。(遅足)