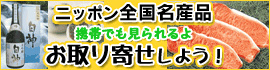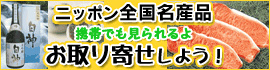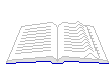【まくら】
江戸時代の旅は、「講」を組んで伊勢や大山にでかける信心の(を理由にした)旅であった。
大山は神奈川県伊勢原市にある霊山で、開かれたのは一三世紀だが、江戸時代に御師(おし)が活躍して講が組まれるようになり発展した。
門前には今でも御師の集落がある。
大山は雨乞いの山であり水の神信仰であったため、鳶や職人が講を形成して参拝することが多かったという。
とくに旧暦七月一四~一七日の盆の時に集中した。
講の連中は両国橋際で川に入って水垢離をする。
そして除災、招福を願う木製の太刀を持ち、大山の水や酒を納める御神酒枠(おみきわく)をかついで出発した。
赤坂、青山、渋谷、三軒茶屋、長津田、厚木を通ったが、沿道の村々は大山灯籠を立てて道案内したという。
帰りは江ノ島に寄るコース、富士登山と組み合わせるコースなどがあって、旅を楽しんだ。
出典:TBS落語研究会
【あらすじ】
現在、登山はスポーツやレジャーだが、当時は神信心で登っていた。
講中があって富士山なら富士講、大山なら大山講が組織されていて、その講のリーダーが先達さんと言われ、山案内をした。
当日は七つ立ち(午前4時)で、先達さんの家に集まった。
「決め式を守ってくださいよ。腹を立てたやつは二分(1両の1/2)払い、暴れたやつは坊主だから。」と言う事で出発した。
この決め式が効いたのか、道中間違いなくお山も済ませて、神奈川宿は大米屋さんという宿に入った。
仲間の講から酒の差入れがあったので、先達さんが足して5升の酒を仲間に振る舞った。
先達さんは若い者だけにしてあげるからと、早々に隣の旅籠に行ってしまった。
酒が入った熊さんが、湯船に乱暴に入ってきた。
熊が放った屁が仲間の鼻先で破裂した。
それを吸い込んでしまったので、喧嘩が始まった。
「俺は腹を立てたから、二分払うが、熊は暴れたので坊主にする」と息巻いたが、若者頭に止められた。
しかし、酔っているので収まらない。熊を探すと酒と風呂で酔いが回って大の字になって酔いつぶれていた。
仲間二人で熊の頭を坊主にしてしまった。
翌朝は早立ち、お膳を一つごまかして、熊を置いて出掛けてしまった。
女中さんに起こされ、始めて坊主になってしまった、自分を認めたが後の祭り。
通し駕籠を雇って一足お先に江戸へ戻ってきた。
熊の女房に、山に行った連中のおかみさん全員集めさせた。
「今年のお山は素晴らしかった。帰り道、金沢八景に回って舟に乗る事になった。気が進まなかったが『残る』とも言えずに舟に乗った。船頭が『天気がおかしいので、またの日になさい』と言ったが、江戸っ子だからと舟を出した。烏帽子岩を回るときは解らなかったが、その先にポツリと雲が湧いて、見る見るうちに真っ暗になってしまった。ポツリポツリと雨が降ってきたが、間もなく前後も、雨も海も解らないくらいの雨になった。『キャ-キャ~』言っていると、 突風も加わって、舟がひっくり返ってしまった。
間もなくして気が付くと誰一人知るものが居ない。『船が沈んで浜に打ち上げられたのはアンタ一人だ』と言われたときは、海に飛び込んで死んでしまおうと思った。しかし『お前さんが死んだら、誰がこの事を知らせるんだ』と言われて、ハズカシながら江戸に戻ってきた。この先、いくら待ってもアンタ達のご亭主は帰っては来ませんよ」。
若いおかみさん達は「ワァーワー」泣き出した。
「みなさん、熊さんをなんて呼んでるんだい。ほら熊、千三つの熊、チャラ熊と呼ばれてるんだよ。ウソに決まっているだろう。」、「先達さんのおかみさん、そう呼ばれているが『生き死に』の冗談は言わない。皆さんの菩提を弔うために坊主になった」と言って、頭の手ぬぐいを取って坊主頭を見せた。
「見栄坊の熊さんが坊主になったのだから本当だろう」と先達さんのおかみさんが泣き出したのでたまりません。
井戸に飛び込もうとする者まで出たので「そんなに菩提を弔いたいのなら坊主になったら良い」と騙して、全員丸坊主にしてしまった。
百万遍の大きな数珠を回しながら、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。
話変わって、神奈川を出た一行。川崎、早昼。大森が八つ。
日イッパイに品川に入ろうという、のんびりした旅です。
品川八つ山下の茶屋に腰掛けて、迎えを待っている一行であったが、だれも顔を見せない。
おかしいので、考えてみると「川崎宿で追い抜いていった駕籠が温気が激しいのにタレを降ろしていた。あれはきっと熊が乗っていたのではないだろうか」、「それでは迎えは来ないだろう。」と言う事で、江戸に向かって歩き出した。
長屋に着いてみると、線香の匂いがして、鐘の音がした。
熊の家には尼さんが沢山集まっていた。
「あの尼さんはお前のところのかみさんにソックリだ」、「そんな馬鹿な事があるか。あっ!あれは俺のかみさんだよ。先達さんのかみさんもいるよ。あ~、長屋中のかみさんが居るよ。お~~ぃ、みんな来いよ~」
「さ~ぁ、みなさん、死んで間もないから、亡者が入口当たりで騒いでいますから、しっかりお念仏を唱えてくださいよ」、「あら、いやだ。家の人だわ」、「誰がこんな事を。熊のやろうか。お前は決め式で坊主になったのだろう」
「ワラジを履いている内は旅の最中だ。腹を立てたら二分ずつ出しな」、「う~ぅ。話が出来ね~。先達さ~ぁん、来てくださいよ」
「バカだねぇ~、家の婆さんまでが坊主になっちゃって・・・。こんな目出度い事はありませんよ」、「とんでもない。二分を取られた上に、どこが目出度いんだ」
「お山は無事済んで、家に帰れば、くりくり坊主。みなさんお怪我(毛が)無くてお幸せ」
出典:落語の舞台を歩く
【オチ・サゲ】
地口落ち(いわゆる駄洒落が落ちになっているもの)
【噺の中の川柳・譬(たとえ)】
『盆山を賭場からすぐに思い立ち』
『十四日末は野となれ山へぬけ』
【語句豆辞典】
【大山】
雨降山大山寺(あめふりさんだいせんじ)通称雨降神社。山上には石尊大権現・不動明王・八大竜王・大天狗・小天狗が祀られている。
古くから雨乞いの神とされていたが、徳川中末期より、どうしたわけか勝負の神様と間違われたり、また農家は旱魃の神様にしてしまったりしたので、町人、とりわけ博打打・鳶の者などが講を仕立てて盛んに参詣した。
【早立ち】
昔は道中が物騒で、ことに夜分は危険であったので「早立ち早着き」と言って、多くは六ツ(午前六時)頃出発した。なお、それより一時刻早く、七ツ(四時)に提灯をつけて出かけるのを七ツ立ちと言った。
【通し駕籠】
駕籠は原則として各宿場毎にその宿場に専属している担ぎ手に代わったが、目的地まで駕籠を変えずに行くのを通し駕籠といって料金は非常に高かった。
【この噺を得意とした落語家】
・五代目 古今亭志ん生
・三代目 古今亭志ん朝
・六代目 春風亭柳橋
【落語豆知識】
【楽屋落ち】内部事情に詳しい人に受けるネタ、あまり多いとツマラナイ。