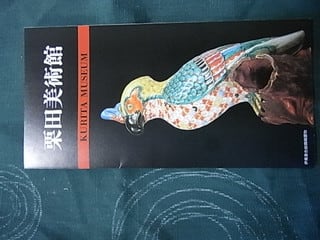絵画展・美術館に行った記事を続けて書いています。
※ 真夜中に書いた「足利「栗田美術館」」
も、よろしくお願いいたします。
4月27日に行って参りました。連休前でもチケット売り場は混んでいて長蛇の列。
そう言えば先日NHKの「日曜美術館」でも特集の再放送をしていた事を思い出しました。番組に気が付いたのが遅すぎて、チャンネルを合わせた時には、もうラストでミュシャが亡くなったいきさつが語られたところだったと言う、ちょっと残念なタイミングだったのですが、あそこで特集をやった後は混むのですよね。
でもそれは勘違いだったようです。このチケット売り場が混んでいたのは、今、「国立新美術館」では草間彌生さんの「わが永遠の魂展」も開催されていて、そちらもかなりの人気があるからなのでした。因みに草間彌生さんの企画展は5月22日までで、「ミュシャ展」は6月5日までです。

私は「ミュシャ」と聞くと、今まではアール・ヌーヴォ―の綺麗な絵を描く人と言う認識しか持ってなかったように思いました。
確かに彼はパリで舞台用や商業ポスターを手掛け、その人気を絶大なものにしていったのです。

だけどその後彼は・・・・
その詳しい説明はこの企画展のHPの「展覧会の構成」と言うページを読むと、よく分かります。
そのページは→ こちら
(そのページの後半に書いてあります。すでにお出掛けになって、その余韻に浸りたい方にも良いページだと思われますのでご利用ください。)
または→ミュシャ展
の「見どころ」「スラブ叙事詩」のページをご覧ください。
「スラブ叙事詩」、圧巻です !
大作であると言う事も含めて、一枚の絵の中に描かれた世界観に引き込まれるような気がします。

「スラブ式典礼の導入」 ↓

上の画像はフライヤーからのものです。
でも行かれた方は、なぜこの人はそんな事をしているのだろうかと思う方もいらっしゃるかもしれません。なぜなら、この美術展、凄いのですよ。何がって、最初の大広間と言うか、これらの大作が展示している部屋は撮影がOKなのです。
でも私・・・(ノД`)・゜・。
美術館とカメラって、ほとんど結びつかない場所。いつでも持ち歩いているけれど、その時ロッカーに入れて来てしまいました。しかもスマホの電池が危機状態。
アホか~、私・・・。
その危機状態のスマホで撮った「スラブ民族の賛歌」↓

下のは、「イヴァンチツェの兄弟団学校」の一部。少女たちがこの作品のこの部分をこぞって写真を撮っているので、私も真似してみました。この部分が人気があったのは、たぶんこの老人に聖書を読んであげている若者がハンサムだったからだと思いました。

解説によると、この若者はミュシャ自身らしい・・・。
御一緒した星子さんから画像を頂きました。「聖アトス山」です。

解説にはなかったのですが、ほらここにも。
 彼らは絵の中のストーリーとは関係なく存在しているのです。つまり彼らは目撃者・・・?
彼らは絵の中のストーリーとは関係なく存在しているのです。つまり彼らは目撃者・・・?
これらの作品(スラブ叙事詩20作品)は、流石に写真OKだけあって、みなHPの作品紹介に載っています。
だけれど、まるでミュシャが魂を注いで描いたと思われるこの大作は、実際にその目で確かめる事をお勧めいたします。
ミュシャの絵画は、叙事詩的な実際の物語が描かれて、そしてその絵の中に寓意的なイメージが描かれ、そして目撃者的なものが居たり、強いアピールするものが存在していたりと、一枚の絵の中に事実とメッセージが巧みに描かれていると思いました。
私はこれらの絵を観ていて、漫画を描く人、映像を作る人、もしくは物語を綴る人に何かしらのヒントを与えそうだと感じました。今の自分がそれらの何にも当たらない事が、ちょっと寂しくも感じました。
ただ綺麗な絵を描く人と言う認識でしかなかったミュシャが、私にとって大好きな方になったことは間違いのない事でした。
お土産に買って来たファイルの一枚。他にも「スラブ叙事詩」デザインのも買い求めてきました。

「国立新美術館」の外には、草間彌生さんのオブジェが展示されていました。

通路は「ミュシャ」「草間」「ミュシャ」「草間」・・・・・

そして花より団子タイム。
3階の「ブラッスリー ポール・ボキューズ ミュゼ」にて。


ちょっとリッチなランチ。美味しかったです♪