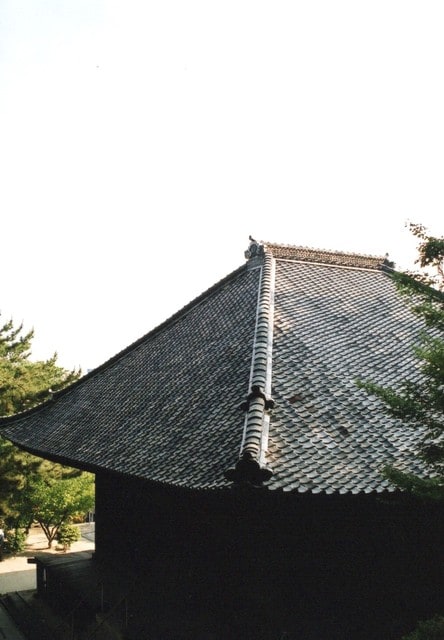(しんちていえん 東京都千代田区九段北)
靖国神社境内南西側にある回遊式庭園である。靖国神社の前身である東京招魂社が明治5年(1872)に玉川上水を引き作庭したもので、明治37年(1904)には中島が造られた。平成11年に改修工事がされ、花崗岩の直橋は日本一の長さであるという。










(愛知県葉栗郡木曽川町玉ノ井 2002年8月11日)
昭和34年(1959)それまでの玉ノ井港駅に代わって終着駅となった、尾西線玉ノ井駅を降りる。地名の由来は、地域の賀茂神社にある清水「玉ノ井」に由来する。町名、字名共に水に関わるものである。


程近い木曽川畔に向かってみた。
この自然豊かさが、辺りの発展にも寄与したことが感じられた。
(神奈川県小田原市栄町)
昭和47年(1972)小田原ショッピングデパート開業に際し、核テナントとしてニチイ(1996-マイカル)小田原店が入居した、RC造6階地下1階、17,202m2の商業施設である。平成4年、ファッションビル・マイカル小田原ビブレに業態変えされたが、平成11年、業績不振により撤退し、翌年には核テナントを持たない専門店の集合体である「アプリ」の商号で再オープンした。然しながら市街地ドーナツ化により志澤西武、箱根登山ベルジュ、マルイ等が相次いで閉店し、中心地の集客力が失われたことにより、アプリ自体にも影響を及ぼした。また、建物の老朽化も相俟って、平成28年8月をもって閉店することが決定した。



 閉鎖後のアプリ(2016年11月7日)
閉鎖後のアプリ(2016年11月7日)
(東京都千代田区九段南)
昭和16年(1941)三井財閥創業家三井高陽が土地を寄贈し、イタリア外務省が文化の普及と日伊文化交流の振興を目的として開設されたことに始まる。現在の建物は平成17年に改築されたSRC造12階地下2階、延床面積14,787m2の貸オフィスを兼ねた教育支援施設で、館内の図書室は約2万点のイタリア関係の洋和書が所蔵されている。

(長野県上田市武石・松本市三才山 2002年6月15日)
里山辺の麓から見ると、ツツジが咲き誇っているのかと思われた山肌は、実は山火事の爪跡。途中の美鈴湖まで広範囲にわたって被害を受けていた。美ヶ原スカイラインに入り、やがて急坂を上るにつれ、辺りに霧が立ち込め始めた。ツールドフランスのように何十台もの自転車登山者が、行く手を阻むかのように犇めき合う。峠に近づくにつれ朱色の蓮華ツツジが現れ始め、夏の下界との違いを表現し始めた。そして標高1830mの武石峠に差し掛かった。



(愛知県南設楽郡鳳来町長篠字丸井 2002年6月9日)
長篠から門谷に至る道(主要地方道長篠東栄線)の脇に古い構造物が聳え立つ。これは宇連川の支流大井川を跨いでいた田口鉄道(1956-豊橋鉄道田口線)の鉄橋の橋脚であり、昭和4年(1929)に築造されたものであるが、橋桁は廃止後間もなく撤去され、橋脚と橋台のみが残されている。
(関連記事:田口線跡 本長篠-鳳来寺間)
(さかわがわ 神奈川県小田原市)
富士山と丹沢山地の間を水源地域とし、相模湾に注ぐ全長46kmの二級河川である。河口から2km地点の東海道新幹線鉄橋付近には飯泉取水堰があり、日に1,564,300m3の水道水を県内各地に送水している。







(愛知県岡崎市戸崎町外山 2002年6月8日)
前回訪れたときは日清紡戸崎工場の敷地内であり、工場の庭の築山として利用されていた古墳は、その後イオンモールの敷地の小公園となった。
(関連記事:外山古墳平成二年)
(かものみや 神奈川県小田原市鴨宮)
この日、東海道線は強風により飛んできた漁網が架線と車両に絡み、長時間足止めを余儀なくされた。そのため当初の予定を変更し、途中の鴨宮で下車することにした。空気が澄んでいるときは富士山が見える鴨宮は、近隣、飯泉観音への巡礼街道沿いの地である。酒匂川左岸で、旧東海道からやや内陸に入ったこの地は、大正12年(1923)に熱海線の鴨宮駅が開業し、昭和9年(1934)東海道線に昇格して以降は人口が増加した。地名の由来は、平安時代に創建したという加茂神社による。





(静岡県浜名郡三ヶ日町尾奈 2002年5月4日)
猪鼻湖に面するこの地は、かつて乎那という字が当てられていた。地名の由来に関して次の伝説がある。保元三年(1158)二条天皇は不思議な病気にかかった。丑三つ時、東三条の森から黒雲が現れ、御殿を覆って鵺(ぬえ)という鳥が鳴くとき、天皇の病気は急に重くなるのだという。これはあの鵺の仕業に違いないと源頼政は鵺を討ち取るように命じられた。頼政は家臣と遠江国の住人である猪の早太の二人を従えて鵺の現われるのを待った。やがて日が変わる頃、東三條の辺りから鳴き声と共に黒雲が御殿の上で渦巻き始めた。 頼政は、八幡大菩薩を念じながら、その黒雲の中心に向かって矢を射った。すると黒雲の中で鵺の一声鳴く声がし、更に頼政が続いて二矢を射ると、御殿の屋根を転がって庭に落ちるものがあった。猪の早太はすかさずそれを斬りつけて息の音を止めた。死骸を見ると、頭は猿、背は虎、尾は狐、足は狸、声は鵺という怪物であった。間もなくして二条天皇の病気も全快したという。このとき、猪の早太の斬った怪物は四つに飛び散り、頭の落ちたところが三ヶ日の鵺代であり、胴の落ちたところが胴崎、尾の落ちたところが尾奈、羽の落ちたところが羽平となったと伝わっている。 対岸の大谷山
対岸の大谷山 隣海院庚申塔
隣海院庚申塔 浅間山から
浅間山から
(鎌倉街道 水戸街道 東京都葛飾区金町)
江戸川沿いのまち、金町の地名が見られる最も古い資料は室町時代であり、対岸の松戸と渡船を通じての街道交通は鎌倉時代には確立していたという。江戸川には一時期日本一不味い水道水として有名になった金町浄水場があるが、今は浄水処理技術の進歩により、この浄水場で濾過し、塩素を除去した水が販売されるまでになっている。