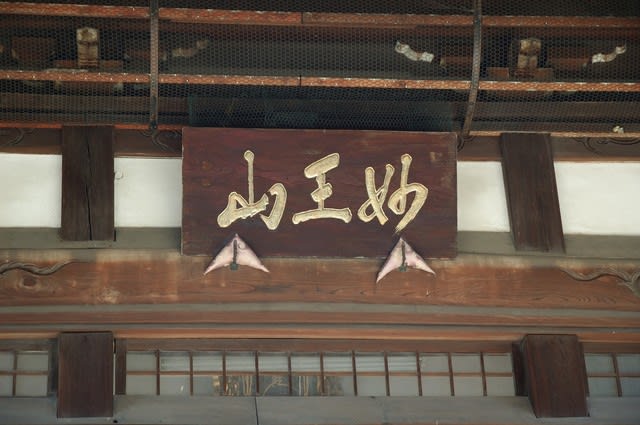(東京都港区麻布台)
桜田通りと外苑東通りの交わる飯倉の交差点に楕円形の黒いビルがある。昭和49年(1974)に竣工した、SRC造15階地下2階塔屋付、延床面積10,386m2のオフィスビルである。角地という立地と、黒い壁、窓が小さいことにより、形状とサイズ感が他のビルとは違う。
(愛知県岡崎市昭和町天神 2007年1月9日)
旧碧海郡小望(こもう)村の鎮守である天満宮は、享保五年(1720)原田弥右衛門という武士が、真菰(まこも)の生い茂る土地を有志と共に開墾して数十町歩の田を作りその地を「真菰村」と称し、享保七年(1722)鎮守として祖先の菅原道真を祀ったのが始まりという。
(愛知県新城市有海字小呂道 2007年1月5日)
有海(あるみ)村の鎮守であるこの神社は、誉田別命(ほんだわけのみこと)を祀るが、境内には古神道の信仰対象物である磐座(いわくら)があり、自然崇拝から始まったことが分かる。

(東京都目黒区八雲)
氷川神社の参道脇に石仏を祀る祠がある。中の石仏は地蔵であるが、原形を留めず顔の表情すら分からない。これは、参拝者が自分の痛い場所と同じ地蔵の場所を擦ると治るという言い伝えにより、すり減ったものである。
(愛知県新城市乗本・有海 2006年12月27日)
間もなく第二東海自動車道の築造工事が始まる。これにより長篠の戦いの中山砦が失われ、新昌寺境内の鳥居強右衛門墓が分断される。予定地には樹木にビニールテープが巻かれ、変わるときを待っている。



(東京都千代田区内神田・神田錦町・大手町) 日本橋川に架かるこの橋は、かつて神田明神がこの場所に鎮座したことに由来し、江戸城拡張により外神田の現在地に遷座した。この場所には江戸城神田橋門が設けられ、また、門前に土井大炊頭(おおいのかみ)利勝の屋敷があったことから、大炊殿橋の別名がある。明治6年(1873)門が撤去され、明治17年(1884)に架け替えられている。関東大震災によって焼失し、大正14年(1925)KR形式(ラーメン構造)橋に架けられたが、現在の橋は昭和55年(1980)に架け替えられたものである。



























 背後には金華山岐阜城
背後には金華山岐阜城