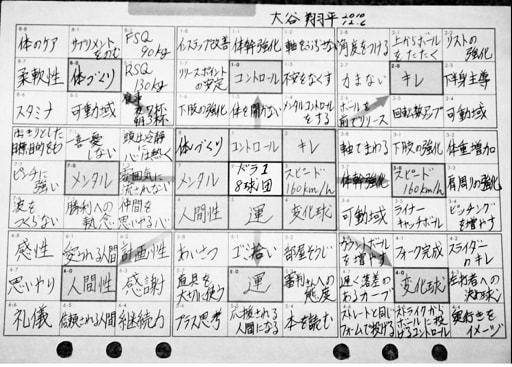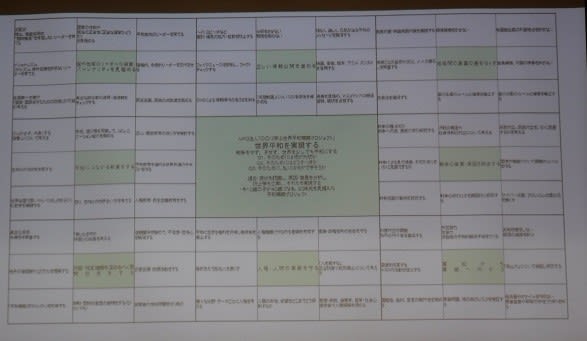非常に心が重くなる映画である。今まさに衝突を繰り返しているパレスチナとイスラエル…。その根幹は土地の奪い合いである。ある意味で強引に武力で土地を奪おうとするイスラエルに対して、パレスチナの人々が必死に抵抗する姿を追ったドキュメンタリー映画である。

昨日(3月28日)午後、シアターキノで上映されている「ノー・アザー・ランド ~故郷は他にない~」を観ました。
観ようと思った動機は、この映画の共同監督の一人であるハムダーン・バラール氏がイスラエル人から暴行を受け、その後イスラエル軍に拘束されたうえリンチを受けた末に釈放されたというニュースに接したのが直接の動機でした。
映画は、イスラエルが占領を主張するヨルダン川西岸のパレスチナ人居住地区(マサーフェル・ヤッタ)にイスラエル軍が訓練基地を造成するという理由で、そこに住むパレスチナ人の住居や小学校などの家や施設をブルドーザなどで強制的に破壊する様子を映し出します。
映画を撮った共同監督の一人、バゼル・エイドラはそこで生まれ育ち、イスラエルの横暴の様子を幼いころからカメラに記録し、世界に発信していました。そこへイスラエル人ジャーナリストであるユーバール・アブラハムが訪れた。ユーバールは、自国政府の行いに心を痛め、バゼルの活動に協力しようとこの地を訪れたのでした。
二人は同じ年齢だったこともあり意気投合し、二人に加えてさらにパレスチナ人とイスラエル人の友人を加え、4人が共同監督となりイスラエルの破壊行動を記録し続けました。
イスラエル軍の破壊活動は容赦ないもので、地上にある建物はほとんど全てを破壊し、はてはパレスチナ人のライフラインである水道管さえ破壊してしまいます。パレスチナ人たちは洞窟のようなところで生活するしかない状況を追い込まれます。
カメラは執拗に、そして事細かにその様子を映し出します。現代はスマートフォンの動画、あるいは手持ちのカメラで容易に映像として残せる時代だからこそ、こうした現状を映し出すことが出来るということを改めて教えられた思いです。
2023年10月まで撮り続けた記録は、一つの長編ドキュメンタリーとして一応の完成をみます。
映画は世界に大きな衝撃を与え、各種映画祭において圧倒的に評価され、各賞受賞しますが、今年3月には最も影響あるアカデミー賞において「長編ドキュメンタリー賞」に輝くという栄誉に輝きました。

※ アカデミー賞「長編ドキュメンタリー賞」のオスカー像を手にした4人の共同監督たちです。
そのことがイスラエル側を怒らせた結果なのでしょうか?前述したように共同監督の一人が暴行を受けたうえ、拘束され、リンチに遭うということに繋がったようです。
俗にいうパレスチナ問題というのは、私のような浅学菲才の者が軽々に述べるほど簡単なものではなく、非常に複雑な経過を辿り現在に至っているようです。
ただ、現象面だけを見ると、圧倒的な武力を背景としてイスラエル側が無慈悲とも思える攻撃をくり返しているという事実があるようにも思えます。
武力の行使によって悲惨な思いをするのは、いつも無力な住民たちです。
武力に頼らずに解決する術をなんとか見いだせないものでしょうか?
ドキュメンタリーの最後も悲惨でした。イスラエル入植者の一人がカメラの前でパレスチナ人に向けて発砲したのです。私は画面を観ながら、思わず「ワッ!」と声を出してしまいました。
そのことがイスラエル側を怒らせた結果なのでしょうか?前述したように共同監督の一人が暴行を受けたうえ、拘束され、リンチに遭うということに繋がったようです。
俗にいうパレスチナ問題というのは、私のような浅学菲才の者が軽々に述べるほど簡単なものではなく、非常に複雑な経過を辿り現在に至っているようです。
ただ、現象面だけを見ると、圧倒的な武力を背景としてイスラエル側が無慈悲とも思える攻撃をくり返しているという事実があるようにも思えます。
武力の行使によって悲惨な思いをするのは、いつも無力な住民たちです。
武力に頼らずに解決する術をなんとか見いだせないものでしょうか?
ドキュメンタリーの最後も悲惨でした。イスラエル入植者の一人がカメラの前でパレスチナ人に向けて発砲したのです。私は画面を観ながら、思わず「ワッ!」と声を出してしまいました。