いよいよ今日は大晦日です。私自身の中では一年の区切りを以前ほど感慨深く迎える気持ちが失せてきているような気がする。だからこそ、このように一年を区切る意味でも自分自身の一年を振り返ることをしている。そうして振り返ったとき、今年一年もいろいろなことがあった一年だった思う。できれば来年も健康でたくさんの体験ができたらいいなぁ、と願っているところだ。
それでは「‘14を振り返る」シリーズの最終章、【どこに旅したか?】、【どんなボランティアをしたか】、【その他参加したイベント・体験等】について振り返ることする。
【どこに旅したか?】
◆奄美群島を巡る旅(奄美大島・徳之島・沖永良部島・与論島・沖縄本島9泊10日 2/23~3/04)

※ 与論島のコバルトブルーの海です。
◆東京の桜を愛でる旅(新宿御苑・上野公園・目黒川ほか 4泊5日 4/04~4/08)
◆石狩市自然観察会(石狩市観光課が主催する石狩市内の自然を巡るバスツアー 5/24)
◆めだかの学校 修学旅行 Ⅰ(余市方面 鰊番屋・旧運上家・ニッカウィスキーなど 6/24)
◆天売島・焼尻島の旅(二つの島をレンタサイクルで巡った旅 2泊3日 6/26~6/28)

※ 天売島のカブト岩を望む日本海です。
◆羊蹄山登山(息子と二人で真狩コースから登るも悪戦苦闘 真狩前泊 1泊2日 8/29~8/30)
◆めだかの学校 修学旅行 Ⅱ(千歳方面 岩塚製菓・リハビリ学院・サッポロビール 9/30)
◆石狩沿岸 サケをめぐるバスツアー(石狩湾自然史ネットワーク主催 10/18)
【どんなボランティアをしたか?】
◆近美を愛するブリリアの会 清掃活動(一年間で会員と一緒に15回の清掃活動を実施
4/14, 5/09, 5/19, 6/03, 6/19, 7/03, 7/17, 8/01, 8/14, 8/28, 9/12, 9/27, 10/10, 10/24, 10/28)

※ 近代美術館前の清掃活動の一コマです。
◆近美を愛するブリリアの会 会報発行 21回発行 №82 ~ 102
◆現職時代の退職者の中央区の団体の役職としてのボランティア 15日
◆現職時代の退職者の全道規模団体の役職としてのボランティア 30日
【その他参加したイベント・体験等】
◆古神札焼納祭(北海道神宮どんと焼 1/14)

※ 北海道神宮のどんと焼きの光景です。
◆札幌雪まつり大雪像制作見学会(札幌市主催 大通公園4丁目 1/24)
◆さっぽろ雪まつりプロジェクションマッピング 見物(大通雪まつり会場各所 2/05)
◆コンサドーレトークショー(野々村芳和社長、石井謙吾、荒野拓馬、古田寛幸選手 道新ホール 4/21)
◆篠山紀信展「写真力」(写真家・篠山紀信の大小の写真の展覧会 芸術の森美術館 5/25)
◆徳川美術館展(名古屋・徳川美術館の所蔵品約230点の展示 国宝4点 道立近代美術館 7/15)
◆札幌国際芸術祭(札幌芸術の森会場 札幌市肝いりの芸術祭だったが… 9/18)
◆だい・どん・でん 2014(家族バンド「Four Leaf Clover」出演 札幌駅前通り一円 9/06)

※ だい・どん・でん 2014の様子です。
【どこに旅したか?】では、やはり春に旅した奄美群島を巡る旅が今年の旅のハイライトだろう。「島の人との出会い」をテーマにした旅であったが、その時々にいろいろな人と出会い、交流することができ、意味ある旅となったと振り返っている。
その他でも、東京の桜を愛でる旅、天売・焼尻の旅と今年は小型ではあったがいろいろなところへ旅することができた一年だった。さて来年は?
【どんなボランティアをしたか?】では、今年で5年目を迎えた「近美を愛するブリリアの会」の活動を今年も会員の皆さま方と協力しながら計15回の活動をすることができた。ささやかな活動ではあるが、少しは地域に役立っているかな、という思いが会員の共通の意識であり、それが継続の力にもなっている。会の活動の連絡手段である会報も通算100号を越え、一定の役割を果たしているのではと思っているところだ。
3項目、4項目については、これまでもやってきていたことだが、今年初めて公にした。純粋のボランティアかどうかというと、議論の分かれるところかと思うが、私からすると団体に奉仕しているという思いが強く、かなりの日数を割かねばならないこともあり公にすることにした。
【その他参加したイベント・体験等】については、これまで取り上げてきたどのカテゴリーにも属さないものをここで拾い上げてまとめてみたものである。
以上、今年も5回にわたって私自身のこの一年を振り返ってきたが、今年もまたいろいろと見聞を深め、たくさんの体験をすることができた一年だったと感謝している。こうしたことが可能なのも何といっても健康であったことが、その最大の要因である。
来年もまた、一年を通して健康で過ごすことができることを念願して、今年のブログ投稿の最後としたい。
拙ブログにお立ち寄りいただいた皆さま、一年間ありがとうございました。
そして、良いお年をお迎えください。
《ウォーキング覚書》
本日(31日)のブログ投稿を終えてから、今日の「札幌ぶり散歩」に出かけた。「今日はどこへ行こうか?」と迷ったが、元旦前の北海道神宮の様子を見てみようと神宮に向かった。きっと大混雑を前にして静かなのではと思っていたが、予想に反してたくさんの人たちが参っていた。お御籤を買い,破魔矢のようなものを購入している人まで目にした。
これは予想外!! 大混雑を避けて、という気持ちも分からないわけではないが、はたしてどうなのだろうか? 今日は今年最後の6日間のウォーキング覚書とする。
◇12/26 13,701歩 ◇ 12/27 15,017歩 ◇12/28 11,253歩 ◇12/29 11,110歩 ◇12/30 10,950歩 ◇12/31 10,419歩
この6日間のトピックは、27日のキタラでの第九の演奏会に歩いて会場に向かい、忘年会のあったススキノからも徒歩で帰宅したことだろう。
そして翌28日は冬の藻岩山のリベンジ登山をしたことだ。
昨日、そして今日は一万歩に達するために、自宅近くまで帰り着いてからも、近くを歩きなんとか帳尻合わせをして一万歩にした。
さあ、来年も頑張るぞ!
いよいよ年の瀬も押し詰まってきた。どうやら元旦はあまり天気が良くなさそうだ。はて、どうしたものか?
さて、「私的に‘14を振り返る」シリーズも今回を含めて残り2回となった。今回は、【どんなステージを堪能したか】、【どんな映画を観たか】について今年一年を振り返ってみることにした。
【どんなステージを堪能したか】
◆平成開進亭(「初笑い寄席 in シアターZOO」桂枝光と桂宮治の落語 シアターZOO 1/04)
◆中国大黄河雑技団(中国の地方の雑技団の選抜による演技 サッポロファクトリー 1/04)

◆フランツ・ヴィルト修復記念レクチャーコンサート(ラントシュ・イシュトヴァーン他 1/18)
◆タマラ・コキラシヴィリ ピアノコンサート(ポーランド人ピアニスト 道立近代美術館 3/22)
◆札響アンサンブルコンサート(札響の管楽器の三人でのコンサート 道立近代美術館 3/25)
◆チカホ クラシックライブ VOL.11(大平まゆみ + 高橋聖純〈フルート〉 &教育大生 4/17)
◆小樽・手宮夜桜ライブ(道内で活動するアマチュア、セミプロのライブ 手宮神社境内 5/10)
◆チカホ クラシックライブ VOL.12(大平まゆみ + ホクレングリーンコール 5/22)

◆Sapporo Sound Square (Jammin’ Zeb ステージ チカホ3条広場 6/13)
◆円山ミュージックソン(アマチュア音楽祭的イベント 北海道芸術高校、カフェ他 6/22)
◆PMF大通公園コンサート(PMFヨーロッパ、PMFオーケストラ・ブラス・メンバー 7/09)
◆PMFオープニングコンサート(PMFオームストラ、九嶋香奈枝他 芸術の森野外ステージ 7/12)
◆PARK JAZZ LIVE CONTEST(アマミュージシャンのコンテスト ミュージックテント 7/21)
◆PMF GARAコンサート(PMFオーケストラを初め豪華な出演陣 キタラ 8/02)
◆ばんけいミュージックフェスティバル(多彩な顔ぶれが揃う野外音楽祭 ばんけいスキー場 8/10)

◆ハーモニカアンサンブル演奏会(北海道内のハーモニカの祭典 東京からも賛助出演 キタラ 9/19)
◆チカホ クラシックライブ VOL.13(大平まゆみ + 札幌国際短編映画祭関係者 10/10)
◆サッポロサウンドスクェア(函館出身のMACO、三人組のWHITE JAMのライブステージ 10/16)
◆ザ・北海道ベンチャーズ チャリティライブ(札幌大教授をメインとしたメンバー 札幌大学 11/02)
◆北海道ハンドベルフェスティバル(全道のバンドヘル愛好家が集った祭典 教文会館 11/08)
◆Mother Crossライブ(幼稚園父母のゴスペルグルーブ サッポロファクトリー 11/21)
◆X‘mas朗読とハープの夕べ(クリスマスの詩の朗読とハープのコラボ 時計台ホール 12/17)
◆アートパフォーマンス in 赤れんが(打楽器アンサンブル、ジャズコンボ演奏 赤れんが庁舎 12/21)
◆札響の第九(恒例の年末行事、今年で5回目 きたら 12/27)
【どんな映画を観たか】
◆「かぐや姫の物語」(製作費50億円を投じた高畑勲監督のアニメ シネマフロンティア 1/05)
◆「鑑定士と顔のない依頼人」(沢木耕太郎が絶賛したミステリー ディノスシネマ 1/08)

◆「キタキツネ物語」(獣医師竹田津実氏原作 1978年制作のオリジナル版 学院大サテライト 1/14)
◆「さよなら、アドルフ」(ナチスに翻弄された少女の物語 ディノスシネマ 2/16)
◆映画版「おしん」(主役の濱田ここねが予想外の好演をした映画 道新ホール 2/18)
◆シリア問題映画会(「シリア、踏みにじられた人々と希望」 北大学術交流会館 3/20)
◆「銀の匙」(農業高校の生活の漫画を原作とした映画 シネマフロンティア 3/31)
◆「それでも夜はあける」(黒人奴隷社会からの脱却を試みる黒人の物語 シネマフロンティア 4/17)
◆「WOOD JOB」(都会の軟弱な青年が林業に挑む話 シネマフロンティア 5/23)
◆「ふしぎな岬の物語」(吉永小百合主演 千葉の岬にある喫茶店の物語 札幌プラザ2・5 10/02)
◆「めぐみ-引き裂かれた家族の30年」(北朝鮮による拉致被害者家族の記録映画 教文会館 10/13)
【どんなステージを堪能したか】では、今年もたくさんのステージを楽しむことができた。私の中でのベスト3を挙げるとすれば、PMF GARAコンサート、ばんけいミュージックフェスティバル、チカホ クラシックライブといったところだろうか?
PMF GARAコンサートは豪華出演陣のうえ、クラシック初心者でも十分に楽しめる構成となっているので来年もぜひ参加してみたいと思っている。
ばんけいミュージックフェスティバルは、おじさんたちでも楽しめるロック系の音楽祭で、昨年に続き楽しむことができた。
チカホ クラシックライブは、札響の大平まゆみさんのチャリティーによって行われている無料ライブだが、今年は3回も聴かせてもらうことができた。大平さんのクラシックを広めようとする奉仕の精神には頭が下がる思いである。
【どんな映画を観たか】を振り返ると、今年は映画観賞の本数が例年の半分以下と、映画観賞の機会が極端に少なくなったのが一つの特徴である。常々、「映画は最高のエンターテイメント」と言ってはばからない私らしくない一年だった。
原因として考えられるのは、メディアなどで宣伝する映画にけっこう期待外れが多いという思いが私の中で育ちつつあることが一つある。もう一つは、良質の映画の情報を入手する手段を持てていないことが挙げられる。
それにしてもである。やはり、私の関心が映画以外に向きつつある一年だった、ということも言えそうだ。
わずか11本の中からベストワンを挙げるとすると、ミステリアスなストーリーがいつまでも記憶に残った「鑑定士と顔のない依頼人」ということになる。
しかし、ステージも、映画も、例え年齢を重ねても楽しめる分野である。これからもできるぎり楽しむ機会を増やしていきたいものだ。
私的に‘14を振り返る 第三弾は【どんな山に登ったか】、【どこを歩いたか】、【どんなスポーツイベントに参加したか】《参加型》&《観戦型》という三分野について振り返ってみた。
【どんな山に登ったか】
◆初日の出登山 in 藻岩山(1月元旦 朝4時45分登山開始 無事にご来光を仰ぐ 標高531m 1/01)
◆スノーシュー in 青山(白川市民の森内にある「青山」に単独で登る 標高531m 1/07)
◆藻岩山登山(北の沢コース 5/08)
◆春香山登山(車道と登山道が入り混じっているコース 下山時に迷ってしまった 標高906.9m 7/25)
◆空沼岳登山(登山口がかなり複雑 長い距離に苦戦 脱水症状に苦しめられる 標高1251m 8/03)
◆羊蹄山登山(息子と二人での登山 苦戦苦戦大苦戦 膝を完全に痛めてしまう 標高1898m 8/30)
◆藻岩山 冬山登山(慈啓会コース 途中で踏み跡なく登頂断念 標高531m 12/18)
【どこを歩いたか】
◆スノーシュー in 石狩川河口 石狩川河口 ~ 石狩河口橋 危機一髪回避! 約5キロ 1/22)
◆スノーシュー in 石狩川河口 Ⅱ 石狩河口橋 ~ 札幌大橋石狩 吹雪実験場 約8キロ 1/30)
◆スノーシュー in 石狩川河口 Ⅲ 札幌大橋 ~ 新石狩大橋 足の痛み深刻 約9キロ 2/09)
◆ウォーク in ドリームピーチ(大浜海岸 スノーシュートウオーキング 約6km 3/08)
◆そらちフットパスウォーク(三笠市、美唄市 5/03)
◆そらちフットパスウォーク(砂川市 5/31)
◆そらちフットパスウォーク(滝川市 6/01)
◆そらちフットパスウォーク(歌志内市 8/16)
◆そらちフットパスウォーク(上砂川町 8/17)
◆一日一万歩を目ざして!(10月から記録を取りはじめた)
◇10月 1日平均 7,431歩
◇11月 〃 11,521歩
◇12月 〃 11,616歩(12月29日現在)
◇3ヶ月トータル 10,126歩 ※かろうじて一日一万歩をクリア
◆発見したトマソン物件
№1. 途中から切られた立木(CT.阿部定) ※ CT.はカテゴリーを表す
№2. ブロック塀から突起している塊(CT.でべそ)
№3. 駐車場の真ん中に鎮座する積み石(CT.あたご)
№4. 建物の壁に残った影(CT.原爆タイプ)
【どんなスポーツイベントに参加したか】
《参加型》
◆初滑り in ばんけい(シーズン最初のスキーイングは近間のばんけいスキー場で 1/06)
◆初クロカンin 真駒内公園(4年ぶりのクロカン復活を目ざして真駒内公園で試し走りを 1/09)
◆クロカン第1戦 HBCラジオ歩くスキー大会(5キロの部に出場 白旗山競技場 1/19)
◆クロカン第2戦 滝野ニューイヤー歩くスキー大会(6キロの部に出場 滝野公園歩くスキーコース 1/26)
◆スキーツアー in ルスツ(友人2人と2年ぶりのスキーを楽しむ ルスツスキー場 2/20)
《観戦型》
◆HBCジャンプ競技会(KO方式のトーナメントによるジャンプ大会 大倉山ジャンプ競技場 1/09)
◆コンサドーレ戦観戦(対 ザスパクサツ群馬 1対0で勝利 札幌ドーム 4/20)
◆春の高校野球観戦(札幌日大 VS 札幌創成 7対1で札幌日大勝利 江別野幌野球場 5/11)
◆春の高校野球観戦(札幌日大 VS 立命館慶祥 8対0で札幌日大勝利 江別野幌野球場 5/12)
◆春の高校野球観戦 支部代表決定戦(札幌日大 VS 東海四校 1対8で東海四校勝利 札幌麻生球場 5/15)
◆プロ野球日ハム戦観戦(対中日戦 7対5で勝利 大谷選手が投打で初の先発も不完全燃焼 札幌ドーム 5/20)
◆WCブラジル大会 日本戦パブリックビューイング(対コートジボワール戦 1対2の敗戦 サッポロファクトリーアトリウム 6/15)
◆夏の高校野球札幌支部大会観戦(札幌日大 VS とわの森三愛 5対0で札幌日大勝利 円山球場 7/01)
◆夏の高校野球札幌支部大会観戦(札幌日大 VS 尚志学園 10対3で札幌日大勝利 円山球場 7/04)
◆夏の高校野球観戦 支部代表決定戦(札幌日大 VS 立命館慶祥 7対0で札幌日大勝利 円山球場 7/06)
◆夏の高校野球南北海道大会第一日観戦(浦河、恵庭南、小樽潮陵がそれぞれ勝利 円山球場 7/17)
◆夏の高校野球南北海道大会第二日観戦(札幌第一、東海四校、札幌日大がそれぞれ勝利 円山球場 7/18)
◆夏の高校野球南北海道大会第三日観戦(駒大苫小牧、浦河、小樽潮陵がそれぞれ勝利 円山球場 7/19)
◆夏の高校野球南北海道大会第四日観戦(東海四校、札幌日大がそれぞれ勝利 円山球場 7/20)
◆夏の高校野球南北海道大会第五日観戦(浦河VS樽潮陵は樽潮陵、札幌日大VS東海四校は東海四校のそれぞれ勝利 円山球場 7/22)
◆ラグビートップリーグ戦観戦(NECVSヤマハ発動機 55対7でヤマハの圧勝 月寒ラグビー場 8/31)
◆秋の高校野球全道大会準決勝観戦(北海高、東海四校が札日大、駒苫を破り決勝へ 円山球場 10/11)
◆秋の高校野球全道大会決勝観戦(北海高 VS 東海四校は3対2で東海四校の勝利 円山球場 10/12)
◆フットサル Fリーグ戦観戦(エスポラーダ VS 浦安 2対3で敗戦 北海きたえーる 11/01)
【どんな山に登ったか】で今年のハイライトは何といっても羊蹄山登山である。辛酸をなめつくし、その上膝痛まで発症してしまった登山であったが、憧れだった山に遂に登ることができたことは私の中では大きな出来事だった。
また、一月元旦に藻岩山に登り初日の出を拝むことができたが、これも初めての貴重な経験だった。
しかし、その他で特筆すべきは春香山と空沼岳くらいで、例年に比べて登山に向かうことが少ない一年だった。来年は膝と相談しながらもう少し山に向かいたいと思っている。

※ 倶知安方面から見た羊蹄山です。
【どこを歩いたか】では、一つは足掛け3年をかけて空知管内の全市町村のフットパスコースを歩いたことが挙げられる。この取り組みによって、多少は空知管内のことについて理解を深めることができたのも私にとっては収穫だった。
さらには、冬期間にスノーシューによって石狩川河岸を歩いたのも私にとっては大きな出来事だった。非常に負荷のかかる運動で、毎回疲労困憊で帰路についたが、それだけに思い出も強烈である。来シーズンもう少し上流までとも思うのだが、交通の便などが極端に悪くなるため、「どうしたものか?」と思案しているところである。
また、今年後半から取り組み始めた「一日一万歩ウォーキング」は今のところ順調である。
10月から記録を取り始めたのだが、当初は休む日も多かったが、11月頃からは毎日順調に歩いていたので平均では軽く一万歩に達していると考えていたが、昨日計算するとギリギリのところでクリアしていることが分かった。記録を見ると、10月はほとんど歩いていない日が6日もあり、平均歩数をグッと下げたようである。しかし11月、12月で盛り返し、なんとか一万歩をクリアできたようである。、
市内の珍しい物件を探しながら、なおかつ健康維持にも繋がるこの取り組みは我々世代に適しているのかもしれない。飽きっぽい私がどこまで続けられるのか、私が私自身に興味津々である。

※ 滝川市のフットパスルートを歩いた時はちょうど菜の花の季節でした。
【どんなスポーツイベントに参加したか】では《参加型》が少なくなっているのが今年の一つの特徴となってしまった。やはり年齢がそうさせるのか、スポーツイベントに参加するよりは、ウォーキングとかスノーシューのような日常的な運動にシフトしてきているということなのかもしれない。

※ HBC歩くスキー大会のゴール風景です。
《観戦型》ではいつの年にも増して高校野球の観戦が多かった。これも札幌日大高校の戦いを追い続けたことが影響している。
プロ野球観戦も、Jリーグ観戦もずいぶんと少なくなってしまった。私の中では一段落といった感が強いようだ。
残念だったのは、アギーレジャパン(いつまでもつのかな?)の初戦が札幌ドームで行われたのに、そのチケットを取得することができなかったことだ。次回(いつになるか?)は、今回の反省を踏まえてぜひとも入手できるよう努めてみたいと思っている。

※ ラグビートップリーグ NEC 対 ヤマハ発動機の対戦の模様です。
※ このまとめの中ほどで「トマソン物件」に触れている。報告したのはすでに拙ブログで報告したもののみだが、その後続々と発見している。年が明けてから随時報告していきたいと思っている。
「私的に‘14を振り返る」シリーズ第2弾は「どんな講座を受講した」である。 今年も数多くの講演・講座を受講することができた。その数があまりにも多く、一つ一つを正確に思い出すことが困難なくらいである。
今年の場合は、昨年と同様に道民カレッジとの連携講座を受講することによって、道民カレッジの単位もかなり取得することができた。
【どんな講座を受講したか】
◆札大 北方文化フォーラム(「部活って何?」一橋大講師 中澤篤史氏 札幌大学教室 1/09)
◆北海道環境の村セミナー(「コミュニケーションと環境教育」東海大教授氏名? エルプラザ 1/14)
◆さっぽろオトナ学 №4(コープ札幌文化教室 「役立つ年金のハナシ」 コープ札幌中央教室 1/16)
◆第9回ほっかいどう学・かでる講座(「スポーツと健康」 日ハムチームドクター横田正司氏 1/17)
◆札幌大谷大学公開講座(「フランツ・ヴィルト修復記念レクチャーコンサート 大谷ホール 1/18」

◆映像で綴る昭和の記録(「めだかの学校」主宰 かでる2・7 1/20、2/10、3/10、4/14、6/09, 7/14, 9/08, 10/31, 11/10, 12/08)
◆自然エネルギー実践講座(「草の根からのエネルギー転換」愛媛大学・村田武講師 エルプラザ 1/21)
◆先端医学公開講座(「総合医療を知っていますか?」札幌医大主催 かでるホール 1/25)
◆北海道教育支援活動推進フォーラム(「これからの教育支援活動について」 ホテルライフォート 1/29)
◆環境・自然を考える会 講座(「大規模な気候変化と変動」見延庄士郎北大教授 エルプラザ 2/01)
◆がんプロフェッショナル要請基盤推進ボード市民公開講座(「がん治療を学ぶ」プリンスホテル 2/02)
◆北大博物館土曜セミナー(「有珠火山の植生と土壌の回復」 北大博物館 2/08)
◆さっぽろオトナ学 №5(コープ札幌文化教室「よくばりは禁物!医療保険」コープ札幌中央教室 2/13)
◆イスラエルを知るセミナー(「イスラエルとユダヤ人社会」外務省官僚 三上陽一氏 国際プラザ 2/21)
◆中国を知るセミナー(「中国の若者の恋愛・結婚事情」中国国際交流員 国際プラザ 3/06)
◆さっぽろオトナ学 №6(コープ札幌文化教室「終の棲家とセカンドライフ」コープ札幌中央教室 3/13)
◆ケニア事情講演会(「ケニア・マサイ族の新たな挑戦」ケニア人とケニア在住日本人 国際プラザ 3/15)

◆映像の記録 世界遺産(「めだかの学校」主宰 熊野・厳島神社 かでる2・7 3/24)
◆道民カレッジ 学習成果実践講座 in 札幌(講演とパネルディスカッション かでる2・7 3/28)
◆石狩川フォーラム(第15回最終回「石狩川沿いの湖沼の自然を守る」紀伊國屋インナーガーデン 3/28)
◆札幌大学シンポジウム(「大学が地域の教育支援人材育成に果たす役割」札幌大学 3/30)
◆道新ニュースカフェ in チカホ(「ソチ五輪 カメラを通して感じたこと」中川明紀記者 4/11)
◆道新ニュースカフェ in チカホ(「これがニュースの焦点だ!」菅原淳解説委員 4/11)
◆北大博物館土曜セミナー(「外来アライグマ対策を通して見える人間社会」 北大博物館 4/12)
◆東海大学公開講座(「野生との共生~カラス~」東海大竹中准教授 紀伊國屋インナーガーデン 4/16)
◆石狩市民カレッジ(「知られざる隣国、ロシアとのかかわり」2回シリーズ 花川北コミセン 4/19, 4/26)
◆めだかの学校 音楽の時間(昭和の懐かし歌謡を唄う かでる2・7 4/28, 10/31)
◆北大公開講座(「記憶の中のユーラシア」7回シリーズ 北大文系共用棟 5/12、5/16、5/19, 5/23, 5/26, 5/30, 6/02)
◆札幌学院大コミュニティカレッジ(「アイヌ民族の碑が訴えていること」3回シリーズ 5/14, 5/21, 5/28)
◆北大公開講座(「近代とその行方」4回シリーズ 北大メディシア研究院 5/14, 5/21, 5/28, 6/04,)
◆石狩市民カレッジ(「原子力 負の遺産」2回シリーズ 花川北コミセン 5/15, 5/29)
◆第3回北海道JCフォーラム(記憶にもなく、記録もとらなかった 札幌コンベンションセンター 5/18)
◆石狩市民カレッジ(「村山耀一 by 石狩歴史さんぽ」3回シリーズ 花川北コミセン他 5/24, 6/07, 6/28)
◆めだかの学校 野外教室(北大構内、札幌市環境プラザ、札幌市融雪溝見学 5/26)
◆石狩市民カレッジ(「不思議いっぱい!石狩川河口」3回シリーズ 花川北コミセン他 6/04, 6/18, 7/02)

◆東海大学公開講座(「多様な文化と音楽」東海大沖野准教授 東海大学校舎 6/14)
◆6月 かでる講座(「卓上四季執筆~新聞コラム編」 菅原淳道新解説委員 かでる2・7 6/17)
◆石狩市民カレッジ(「札幌アート散歩」2回シリーズ 花川北コミセン、近代美術館他 7/08, 7/15)
◆石狩市民カレッジ(「石狩湾新港の最先端技術を学ぶ」2回シリーズ 花川北コミセン他 7/23, 8/06)
◆北大公開講座(「憲法改正を考える」4回シリーズ 北大法学部 7/24, 7/31, 8/07, 8/21)
◆7月 かでる講座(「戦国時代における大名の権力構造」 北大平井上総助教 かでる2・7 7/28)
◆アイヌ文化普及啓発セミナー(アイヌ文化振興・研究推進機構の主催 4日間連続講座 かでる2・7 7/29, 7/30, 7/31, 8/01)
◆北大公開講座(「IPCC第5次評価報告書を読み解く」6回シリーズ 北大環境科学院 8/20, 8/27, 9/03, 9/10, 9,17, 9/24)
◆めだかの学校 野外教室(北海道警察本部、道庁赤レンガ庁舎 8/25)
◆「領土という病」トークショー(岩下明裕 × 本田良一 紀伊國屋インナーガーデン 9/20)
◆ボーダーツーリズムシンポジウム(岩下明裕氏ほかが国境観光について論じる パレスガーデン 10/02)
◆オントナ市民公開講座(「膝のいたみの治療法」主治医・東裕隆医師の講演 道新ホール 10/04)
◆札幌学院大コミュニティカレッジ(「古文書に見る歴史の変換点」3回シリーズ 10/09, 10/16,10/23)
◆道民カレッジ称号取得者セミナー(講演とグループディスカッション かでる2・7 10/20)
◆北大公開講座(「観光創造の最前線」5回シリーズ 北大教育情報館 10/23, 10/30, 11/06, 11/13, 11/20)

◆TPPを考える道民会議フォーラム(「TPPでどうなる?私たちの生活」 道新ホール 11/04)
◆不登校の子供の支援を考えるシンポジウム(玉川大・田原教授の講演他 クラーク高校白石校舎 11/09)
◆電力全面自由化セミナー(電力の購入先を自由に選択できる時代の到来? TPKセンター 11/15)
◆めだかの学校 世界遺産(日本で指定された世界遺産の映像を視聴 かでる2・7 11/17, 12/22)
◆札幌資料館講座(「北海道の軟石文化 これまでとこれから」 札幌市資料館 11/16)
◆水素社会シンポジウム(「北海道における水素社会の実現に向けて」 ロイトン札幌 11/20)
◆サイエンスカフェ札幌(「冷たい海が氷をとかす~南極の海流と気候変動~」紀伊國屋インナーガーデン11/23)
◆11月 かでる講座(「知られざる北の国境」相原秀起道新編集委員 かでる2・7 11/27)

◆札幌大時計台フォーラム(「奇跡の島々(?)先史時代のおきなわ」高宮札幌大教授 時計台ホール 11/27)
◆サイエンスフォーラム in 札幌(「地震の正体と北海道の地震たち」 北大名誉教授 中央図書館 11/29)
◆北翔大市民講座(「地域資源を考える」道内外の煉瓦や軟石建造物の現状報告 北翔大ポルト 12/14)
◆12月 かでる講座(「心臓病ってこわくないの?」三浦雄一郎の登山支援医師・大城氏 かでる2・7 12/15)
今年受講した講座の特徴の一つに、今年の前半意識的に「石狩民カレッジ」の講座を受講したことがあげられる。(6講座、14日間)これはちょっと不純な動機だったのだが、道民カレッジの「ほっかいどう学」コースの「博士号」の称号を
早く取得してしまいたいという思いがあったことを吐露しておく。何事にも熱しやすく、冷めやすい自分の性格から熱いうちに一区切りつけてしまいたいという思いがあったのだ。
しかし、怪我の功名か、意外に興味深い講座が多く、遠くまで通うことが苦痛でなかったこと幸いだった。
また、目立つのとしてはやはり北大の公開講座への参加が目立つ。数えてみると、5講座を受講し、計26日間通っている。中には難解な講座もあったが、知的好奇心をおおいにくすぐられる講座が多かった。
その他でも、札幌市内の各大学が市民向けに数多くの講座を開設していて、できうる限り受講しようと努めたが、中には情報漏れのために受講できずに臍を噛んだものもあった。
受講した講座の内容については、そのエッセンスだけでも拙ブログでレポートするように努めたが、中にはレポートできずに終わってしまったものもあった。
これだけ多くの講座を脈絡なく受講するのはどうなのか?という疑問の声が聞こえてきそうな気もするのだが、私は敢えてその問いを気にしないようにしている。
私にとっては講演・講座を受講することで、自身の知的好奇心をくすぐってもらえたら、それでヨシと思うことにしているからだ。
来年も機会があるかぎり、意欲が継続するかぎり、積極的に受講していきたいなぁ、考えている。
《余話》
今年で6年連続となる「札響の第九」を昨日、いつも3人+1の4人で楽しんだ。聞くところによると長年札響で首席指揮者や音楽監督を務められた尾高忠明さんが札響を去ることになったという。その尾高氏が指揮を務められた。心なしかいつもの第九とは違って聴こえたのは気のせいか? その後、4人で忘年会へとなだれ込んだのは言うまでもない。楽しいひと時だった…。
今日、先日途中で断念した藻岩山へリベンジの登山をした。風もなく良いコンディションで楽しく登れた。
私にとっては年末の恒例になったかの感のある〔私的に○○年を振り返る〕シリーズを今年も綴ろうと思う。この振り返るシリーズを振り返ってみると、2008年にその原型が生れている。それ以来ずーっと継続しているのだが、現在のように5日間にわたって分野ごとに振り返るようになったのは2010年からである。
この企画について私自身はけっこう気に入っている企画である。これをまとめるにはけっこうな時間も要するが、自分自身の一年を振り返ることによって、「この一年間を自分はどう生きたのか?」という問いに対する一つの答えがここにあるような気がするからである。
それではいつものようにPart Ⅰは「誰のお話を聴いたか」から始めることにする。
【誰のお話を聴いたか】
◆竹田津 実 氏(獣医師 映画「キタキツネ物語」原作者 札幌学院大サテライト 1/14)
◆寺島 実郎 氏(日本総研理事長 「『市民が主役』の政治をつくろう!フォーラム」 京王プラザ 2/03)
◆山口 二郎 氏(北大大学院教授 「『市民が主役』の政治をつくろう!フォーラム」 京王プラザ 2/03)
◆岸 博之 氏(慶応大学教授 トランスポートセミナー「日本経済のゆくえ」 ポールスター札幌 2/14)
◆柄谷 行人 氏(哲学者 フォーラム in 札幌時計台(テーマは下段に) 札幌時計台 3/06)
◆佐藤 優 氏(作家、元外務省官僚 「グローバル化に抗する人間とコミュニティ」 札幌時計台 3/06)

◆蟹瀬 誠一 氏(国際ジャーナリスト「世界の潮流を読む~今後の日本の行方~」 京王プラザ 3/11)
◆郷原 信郎 氏(元検察官、弁護士 「企業はなぜ危機対応に失敗するのか」 札幌パークホテル 4/25)
◆篠山 紀信 氏(写真家 「篠山紀信展 写真力」記念トークショー ホテルロイトン札幌 4/25)
◆谷村 志穂 氏(作家 北海道野生基金講演会「イギリスのフットパスを歩いて」 道新ホール 4/26)
◆渡邊 芳樹 氏(元スゥエーデン大使 北海道スウェーデン協会講演会「現代スゥエーデンからの教訓」)ホテルモントレーエーデルホフ札幌 5/27)
◆福島 敦子 氏(エッセイスト 道社会教育主事研修会「私が出会った素敵な人たち」かでる2・7 6/06)
◆葛西 紀明 氏(ジャンパー、銀メダリスト 「ジャンプにかける熱き情熱」 ホテルロイトン札幌 6/19)
◆山口 二郎 氏(法政大学教授 北大講座「民意による政治の意義と限界」 北大法学研究科 7/31)
◆寺島 実郎 氏(多摩大学学長 読売北海道セミナー「世界の構造転換と日本」グランドホテル 8/05)
◆岩下 明裕 氏(北大教授 トークライブ「領土という病」 紀伊國屋インナーガーデン 9/20)
◆合田 一道 氏(ノンフィクション作家 札幌学院大講座「古文書に見る歴史の変換点」札幌学院大社会連携センター 10/09、10/16、10/23)
◆角幡 唯介 氏(作家、探検家 北海道山岳会講演会「登山と冒険」 りんゆう観光ホール 10/11)
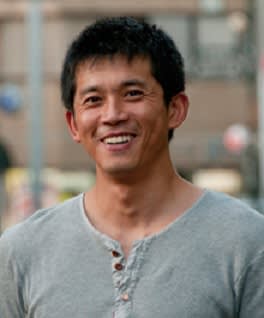
◆金平 茂紀 氏(TBS報道記者、キャスター「笑顔が輝く 子どもと大人の世界」 エルプラザ 10/13)
◆春香クリスティーン 氏(タレント TPP問題を考える道民会議 ゲスト 道新ホール 11/04)
◆保阪 正康 氏(作家 現代への視点2014 道新ホール 11/24)
◆姜 尚中 氏(聖学院大学長 現代への視点2014 11/24)

◆なかにし礼 氏(作家 現代への視点2014 道新ホール 11/24)
◆植村 隆 氏(北星学園大講師、元朝日新聞記者 「マケルナ会」シンポジウム 北大学術交流会館 12/20)
明日掲載予定のPart Ⅱでは受講した講演・講座やフォーラムなどをまとめた。講演・講座やフォーラムなどは全て講師が中心となって進められるのだが、ここに取り上げた方々はいわゆる全国的な知名度があると私が判断した方だけを抽出した方々であることをお断りしておきます。
今年も多くの著名人のお話を聴くことができた。
私にとってどの方のお話を聴くかについて特別思っていることはない。その方がどのような主張をされている方でも一応は聴いてみようというのが私のスタンスである。判断するのは私である。最初から先入観をもって講演会に臨むことは極力避けて、今年も多くの方のお話を聴いた。
そうした中、どの方のお話も名を成した方ばかりなので魅力的であったが、特に私にとって印象的だったのは、作家の佐藤優氏と聖学園大学長の姜尚中氏、そして冒険家の角幡唯介氏の三人が印象的だった。
佐藤氏はその難解な言い回しが印象に残る。彼の著書も少しは読んでいるが、そこでは割合分かりやすく事象を解説してくれているのだが、テーマがテーマだったこともあってだろうか、私のメモする手は止まったままだった。
姜尚中氏は「時代の相続をどうするのか」と問うた。そして「自分は何を受け継ぎ、何を語り継ごうとしているの」と…。その意味するところは重い。さらに歴史は事実に基づかなければならないという。歴史を直視し、そこで得た平和の尊さを語り継がねばならない、と姜氏は強調した。
角幡唯介氏は別の意味で衝撃的だった。
彼の冒険物の著書も読んではいたが、実際の話を聴いてみて、常識人には考えられないような危険極まりない冒険に次々と挑んでいるようだ。彼の話を聴いた後、彼の著書を3冊ほど読んだが、私は彼が将来命を落とすような事態に陥るのではないかと真剣に心配している。 彼は平成27年の暮れからこれまでにないような危険な冒険に挑もうとしている。何としても生きて帰ってきてほしいと願っている。
彼を追い続けようと思っている。
私は常々思っている。札幌は著名人の話を聴くことのできる機会が全国的に見ても多いのではないかと…。少し大げさに言えば、ここ数年の間で日本の著名な文化人の話はおおよそ聴くことができたのではないかと思っている。
機会があり、聴こうとする気力の衰えがないかぎり、来年もまたたくさんの方々のお話を聴きたいと思っている。



12月21日(日)午後、赤れんが庁舎において、二つのグループが出演するパフォーマンスが行われると道新で告知があったので駆け付けてみた。
出演する二つのグループとは打楽器アンサンブル「Esperanza(エスペランサ)」とジャズコンポの「酒本廣継 2 Trombone Meeting +2」だった。
最初は14時から約50分、Esperanzaの4人が打楽器の演奏を披露した。
使用した楽器は、マリンバ、ヴィブラフォン、グロッケン、シロフォンであったが主としてマリンバが使用された。
彼らは打楽器ということで聴衆の飽きを警戒したのだろうか、バラェティに富んだプログラムを編成した。それは2曲目と4曲目に用意した楽器を使わず、彼らの肉体を楽器として演奏したことである。
具体的には「ボディパーカッション」と称して、自分たちの身体の各所を叩いて「スパニッシュダンス」という曲を演奏した。
さらに4曲目には「ヴォイスアンサンブル」と称して、それぞれが特定の野菜の名を連呼することで音楽に仕上げた「野菜の気持ち」という曲を披露してくれた。
いずれも打楽器奏者としての可能性を広げる試みだったのだろう。
計7曲を披露してくれたが、もちろん本職の打楽器を使っての演奏は、4人全てがプロ、あるいはセミプロで活躍している人たちだから確かな演奏を披露してくれた。
《Esperanzaメンバー》
◆白戸 達也(リーダー?) ◆石川 千華 ◆伊藤 汐里 ◆佐藤 奏子
若干の休憩を入れて15時から登場した「酒本廣継 2 Trombone Meeting +2」は、プラス2の二人以外は全員がプロの奏者で2本のトロンボーンをメインとして本格的なスタンダードジャズを聴かせてくれるグループだった。(編成は2本のトロンボーンとギター、ウッドベースである)
酒本氏はプレイヤーであるとともに、トロンボーンの指導者としても活躍しているようで、もう一人のトロンボーンプレイヤーは彼の愛弟子で若干19歳の坂本菜々という女性プレイヤーだった。
また、+2というのも彼の教え子で、高2と中1という若い女の子だったが、二人ともしっかりした演奏ぶりが印象的だった。
トロンボーンの音色がそうであるように、どこか気怠い雰囲気を醸し出すジャズに魅かれるものがあった。
《酒本廣継 2 Trombone Meeting メンバー》
◆酒本廣継(リーダー、トロンボーン) ◆坂本 菜々(トロンボーン)
◆長沼 発(ギター) ◆本間 洋佑(ウッドベース)
このように赤れんがで催されるイベントはかなり質の高いプレイヤーが毎回出演しているように思える。
告知を見逃さないようにしながら、楽しみたいと思っている。
クリスマスイブの今日は一日中雪がしんしんと降り積るホワイトクリスマスとなった。そこで本日も含めて、これまでのぶらり散歩で撮り貯めた冬ならではの光景三態をレポートすることにした。
昨日(12月23日)である。北大の農場と札幌競馬場の間を走る〔石山通〕をウォークしているときだった。前を往くご婦人が何やら引っ張っているのだが、ソリを引っ張っているようには見えなかった。
近くに寄ってみると、段ボールに紐を付けて引っ張っているのである。雪の上をけっこうスイスイと引っ張っていた。

想像逞しい私は、次のように想像を膨らませた。
買い物に行った婦人は店で買い物をしているうちに、予定にはなかったが家に必要なものが目に入ってしまった。しかし、それはかさばるものでとても抱えては帰られない。
店員に相談すると「今日は雪道だから、段ボールを引っ張って帰ったら?」と提案され、「あら?それはいい考えね」とか答えて、そうなったのではないだろうか?
写真は婦人の許可も得なかったので、後ろ姿一枚しか撮らなかった。
ちなみに、ロードヒーティングされているところはどうするのか、と見ていたら、やはりそこは小脇に抱えて通過していた。
続いて本日(12月24日)である。オーソドックスな冬の写真である。
本日は円山方面を歩いた。すると、小さな通りの街路樹がナナカマドだった。
雪が降り積もる中にナナカマドの紅い実が鮮やかだったので、思わずシャッターを切った。まあ、どこにでも見られる光景である。



3枚目はちょっと皮肉っぽい一枚である。
少し前になるが、12月19日(金)、この日は地下鉄を使って苗穂地区まで遠征して歩いた。典型的なトマソン物件を発見したのだが、それは後日レポートする。
この日もけっこう雪が降っていて、歩道は歩きにくい状態だった。
ある一軒の家の前に「ロードヒーティングに付き車輌の駐車禁止」という看板が立っていた。ところが!

家の前は雪がたんまりと積もっていて、ロードヒーティングなどしている気配もない。
電気料金の値上がりなどから、通電を止めたのだろうか?
それなら看板も外したほうがよろしいのでは?
思わず「何でやねん!」と突っ込みの一つも入れたくなった私だった。

とまあ、他愛のない話題でクリスマスイブのレポートを閉じることにする。

医師であり、国際山岳医の資格をもつ大城和恵医師は、いかにもスポーツウーメンという精悍な体つき、表情で我々の前に登場した。
12月のかでる講座は、12月15日(月)午後、かでる2・7において「心臓病ってこわくないの? ~三浦雄一郎氏エベレスト登頂を支えた経験から~」と題して、心臓血管センター北海道大野病院の大城和恵医師が講師を務めた。
講座の大半はテーマにもあるとおり、大城氏の専門である心臓病の予防に関するものだった。しかし、私の関心はやはり三浦氏のエベレスト登頂に際して大城氏がどのようにサポートしたのか、という点にあった。
そこで私のレポートも、大城氏が講義の一部で触れた三浦氏の部分のみについてレポートすることとする。
三浦氏の登頂にあたって、心臓突然死のリスクは次のように考えられたという。
(1)登山は通常の生活と比べて4.3倍心臓突然死のリスクが高くなる。
(2)突然死の90~95パーセントが男性である。
(3)34歳以上に多い。
(4)規則的な運動をしていない人が起こし易い。
(5)ストレスが影響する。
(6)初日が半数。
(7)心筋梗塞、狭心症、糖尿病、高コレステロール血症、高血圧を持っている方が起こり易い。
そうすると、三浦氏は(1)、(2)、(3)、(7)が該当したという。特に三浦氏の場合は(7)の症状を見事に備えていたのである。そのことが大城氏を帯同することになった要因でもあると思われるのだが…。

※ 講義をする大城和恵医師です。
そこで大城氏は三浦氏の心臓突然死を予防するために7つの戦略を立てたそうだ。その7つとは…。
(1)ゆっくり歩く。
(2)30分毎に水分補給をする。
(3)栄養を摂る。
(4)降圧剤の内服についての留意点。
(5)一度に歩く距離を短くする。
(6)酸素を積極的に使用する。
(7)上部キャンプを細かく設置する。
どれも高齢の者が登山をする際に気を付けたい点ばかりであり、低山登山を続ける私にもレベルは違えども参考になる点だった。
その中で(3)の降圧剤についてあるが、大城氏は登山中の降圧剤の使用については否定的な考えのようである。したがって、三浦氏があまり薬を好まず服用していないことが分かってはいても見逃していたという。高血圧対策としては戦略の中にあるようなことと共に、さらに詳細な対策を立てて挑み心配された事態を招くことはなかったそうだ。
そして最後に、大城医師は心臓突然死を防ぐには「予防に尽きる!!」と強調した。その予防とは、「節酒、運動、減量、食事改善、減塩」ということだ。
どれも私にとっては頭の痛いことだが、多少は意識しながら生活しなくては、と講義後には思ったのだが…。
12月15日(月)、この日はある講座を受講することになっていたが、その前にウォークを取り入れることにした。
目的は前日の北翔大ポルトの講座で札幌軟石に関して有力情報を得ていたので、その物件を確認するためにその場所に向かおうとした。
一つ目は中央区の北1西9にある札幌市リンケージプラザの駐車場だ。
リンケージプラザは旧札幌市立病院があったところで、現在は大通まちづくりセンター、ボランティア活動センター、札幌市博物館活動センターなどが入居しているが、どうも仮の施設のようだ。情報ではやがてNHK札幌放送局が移ってくるらしい。
そうした仮の施設ということもあってか、駐車場になっているところは未舗装で雑草も目立つ空き地のようなイメージのところだった。

駐車場には二か所に岩の塊状のものが見えた。片方は駐車場入口のところにあり、駐車場の門の役割を果たしていると見えなくもないのだが、問題はもう一つの岩塊だった。
駐車場の真ん中あたりに鎮座しているのである。子細に観察すると札幌軟石が積まれているのだが、その存在意義はさっぱり分からない。
市立病院時代に使われていた何かの名残だろうか?
やがてこの塊も消されていく運命なのだろう…。

何の役に立ちそうもない札幌軟石の岩の塊はトマソン物件に該当すると私は判断した。
そこでこのリンケージプラザ駐車場内の札幌軟石の塊を「トマソン物件 札幌第3号」とすることにした。(第1号、第2号はこちら ⇒)

続いて、やはり前日の講座で都心の南4西7のところに「札幌軟石の建物を取り壊す際に、その一部を記念碑的に遺してあるところがある」と聞かされたので、トマソン物件ということではないが、興味がわいたので確認してみたいと思った。
ところが一帯を仔細にくまなく探し求めたのだが、目的の記念碑的な札幌軟石を発見することはできなかったのだが…。
界隈を歩いていて不思議なものが目に入った。ある住宅の壁に家型の影が投影されたような光景が目に入ったのだ。
「これは典型的な〔原爆タイプ〕ではないか!」と私は咄嗟に悟った。

〔原爆タイプ〕とは、赤瀬川氏によると「かつて存在した建物の痕跡が、隣接する建物の壁にシルエット状に残されている物件」ということだ。(トマソン物件は赤瀬川氏らによって何種類かのタイプに分類されている。いずれ紹介したいと思う)

積雪があったが近づいてみると、かつて存在した建物は小屋のようなものだったのだろうか?それとも臨時に建てた子供部屋だったのだろうか?現在の建物にぴったりと接するように建てられていたようだ。
壁のシルエット状の境目には若干の凹凸が見られた。
この物件はもう典型的な「原爆タイプ」(それにしても恐ろしいネーミングである)なので「トマソン物件 札幌第4号」とすることにする。
とまあ、一人でトマソン、トマソン、とはしゃいでいる私である…。









