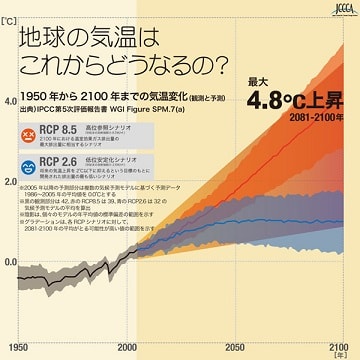わくわく見どころがいっぱいの芦別ルート
芦別市の後半のルートは、田舎道から市街地へ至るルートだったが、石炭産業で栄えた街の例にもれず寂しさを感じさせる街並みだった。ウォークを終え、食した「ガタタンラーメン」が往時の栄華を偲ばせた。
芦別市を走る国道38号線は、街並みを挟んで旧道(?)とバイパスが並行するよう走っているようだ。ルートはバイパスから旧道へ抜ける田舎道だったようだ。
やがてたくさんの車が行き交う旧道の38号線に出た。

ここにもまた芦別川に架かる橋に出会った。「芦別大橋」である。(バスパスに架かる橋が「新芦別大橋」、旧道に架かるのが「芦別大橋」というわけです)
芦別大橋からは鉄道橋が望め、マップによると写真ポイントとのことで一枚カメラに収めた。

ルートは,JR根室本線を陸橋「緑橋」を渡ると、市街地へと導かれる。
市街地に入っても行き交う車以外、人にはほとんど出会わない。
JR「芦別駅」に近づいたところで傑作(?)の建物が目に付いた。立派な建物の壁面に描かれたホテル名が何と「アシントンホテル」とあるではないか!
命名した方は真剣に考えた末の命名だったのかもしれないが、それを目にした私にはワシントンホテルのパロディではないのかと思ってしまった。
評判が気になりウェブ上で検索してみると、やはり私と同じような感想を持った方がいたようである。

そうしているうちにJR「芦別駅」に着いた。芦別駅前には「北の京 芦別」を模した五重の塔のミニチュアが建っていて、やはり芦別市のシンボルだったことを伺わせてくれた。

駅舎の方は時代から取り残されたような古い建物だった。(この後訪れた赤平駅とは対照的だった)

そして駅前である。
哀しいかな炭鉱で栄えた街のほとんどがそうであるように、芦別市の駅前通りも閑散としていて、寂しさは隠せようにもないという感じだった。

そんな街中で一つ他の街との違いを見つけた。
それは街中に良く見られるマンホールの蓋だった。芦別市のマンホールの蓋は「星の降る街 芦別」を象徴する星座を象った蓋だった。それが街の外れでは気が付かなかったのだが、街の中心に来るとそのマンホールの蓋が彩色されているのに気が付いた。星座を表す青い色と白い文字が鮮やかに描かれていた。

ゴール近くの国道沿いには「蘆別神社(あしべつじんじゃ)」があった。街中にあるためか参道は短かった。あまり信心深いとはいえない私であるが、いつもそうするように神前でのお参りだけは欠かさなかった。

そして市街地中心に設けられた市民の憩いの広場「中央分離帯」を通ってゴール地点の道の駅「スタープラザ芦別」に帰ってきた。


※ スタート&ゴール地点にある道の駅のトイレです。上から見ると星形らしいのですが…。
帰着後、道の駅のレストランで芦別名物の「ガタタンラーメン」を食そうと思ったが、時間が11時を過ぎたばかりだったのでまだ開店前だった。近くの人に尋ね、既に開店している近くの「きんたろう」という食堂を紹介された。
そこで「ガタタンラーメン」(880円)を注文し、食した。
「ガタタン」とは中華料理の「含多湯」が由来だという。肉や魚介類、野菜など多くの具材を塩味のとろみがついたスープにしたものを言うそうだ。肉体労働で疲れた炭鉱員には栄養豊富な点が好まれて、芦別において広まった料理だという。
私が食した「ガタタンラーメン」には、豚肉・小エビ・ホタテ・イカ・ナルト・竹輪・シイタケ・タケノコ・トウモロコシ・ニンジン・グリーンピース・長ネギ・スナップエンドウ・ゆで卵などが細かくきざまれ、塩味のとろみのあるスープと麺があるという感じで、まあ具沢山、盛り沢山のラーメンだった。
肝心の味の方だが、私の舌にはちょっと薄味でパンチに欠けるかなぁ、というのが正直な感想である。


芦別市のフットパスルートは、前半はそれなりに見応えのあるポイントがあったが、後半は芦別の寂しさが気になるルートだったかな?と振り返っている。また、渡った橋が鉄道の陸橋も含めて6つの多くの橋を渡ったのも印象的なルートだった。
「タタンラーメン」…、もっと全道的に広がってもいいのではと思うのだが、やはりパンチに欠けるところがいま一つ人気を博しない原因なのだろうか?
《フットバスウォーク実施日 ’14/09/28 距離 約9.8Km》
芦別市の後半のルートは、田舎道から市街地へ至るルートだったが、石炭産業で栄えた街の例にもれず寂しさを感じさせる街並みだった。ウォークを終え、食した「ガタタンラーメン」が往時の栄華を偲ばせた。
芦別市を走る国道38号線は、街並みを挟んで旧道(?)とバイパスが並行するよう走っているようだ。ルートはバイパスから旧道へ抜ける田舎道だったようだ。
やがてたくさんの車が行き交う旧道の38号線に出た。

ここにもまた芦別川に架かる橋に出会った。「芦別大橋」である。(バスパスに架かる橋が「新芦別大橋」、旧道に架かるのが「芦別大橋」というわけです)
芦別大橋からは鉄道橋が望め、マップによると写真ポイントとのことで一枚カメラに収めた。

ルートは,JR根室本線を陸橋「緑橋」を渡ると、市街地へと導かれる。
市街地に入っても行き交う車以外、人にはほとんど出会わない。
JR「芦別駅」に近づいたところで傑作(?)の建物が目に付いた。立派な建物の壁面に描かれたホテル名が何と「アシントンホテル」とあるではないか!
命名した方は真剣に考えた末の命名だったのかもしれないが、それを目にした私にはワシントンホテルのパロディではないのかと思ってしまった。
評判が気になりウェブ上で検索してみると、やはり私と同じような感想を持った方がいたようである。

そうしているうちにJR「芦別駅」に着いた。芦別駅前には「北の京 芦別」を模した五重の塔のミニチュアが建っていて、やはり芦別市のシンボルだったことを伺わせてくれた。

駅舎の方は時代から取り残されたような古い建物だった。(この後訪れた赤平駅とは対照的だった)

そして駅前である。
哀しいかな炭鉱で栄えた街のほとんどがそうであるように、芦別市の駅前通りも閑散としていて、寂しさは隠せようにもないという感じだった。

そんな街中で一つ他の街との違いを見つけた。
それは街中に良く見られるマンホールの蓋だった。芦別市のマンホールの蓋は「星の降る街 芦別」を象徴する星座を象った蓋だった。それが街の外れでは気が付かなかったのだが、街の中心に来るとそのマンホールの蓋が彩色されているのに気が付いた。星座を表す青い色と白い文字が鮮やかに描かれていた。

ゴール近くの国道沿いには「蘆別神社(あしべつじんじゃ)」があった。街中にあるためか参道は短かった。あまり信心深いとはいえない私であるが、いつもそうするように神前でのお参りだけは欠かさなかった。

そして市街地中心に設けられた市民の憩いの広場「中央分離帯」を通ってゴール地点の道の駅「スタープラザ芦別」に帰ってきた。


※ スタート&ゴール地点にある道の駅のトイレです。上から見ると星形らしいのですが…。
帰着後、道の駅のレストランで芦別名物の「ガタタンラーメン」を食そうと思ったが、時間が11時を過ぎたばかりだったのでまだ開店前だった。近くの人に尋ね、既に開店している近くの「きんたろう」という食堂を紹介された。
そこで「ガタタンラーメン」(880円)を注文し、食した。
「ガタタン」とは中華料理の「含多湯」が由来だという。肉や魚介類、野菜など多くの具材を塩味のとろみがついたスープにしたものを言うそうだ。肉体労働で疲れた炭鉱員には栄養豊富な点が好まれて、芦別において広まった料理だという。
私が食した「ガタタンラーメン」には、豚肉・小エビ・ホタテ・イカ・ナルト・竹輪・シイタケ・タケノコ・トウモロコシ・ニンジン・グリーンピース・長ネギ・スナップエンドウ・ゆで卵などが細かくきざまれ、塩味のとろみのあるスープと麺があるという感じで、まあ具沢山、盛り沢山のラーメンだった。
肝心の味の方だが、私の舌にはちょっと薄味でパンチに欠けるかなぁ、というのが正直な感想である。


芦別市のフットパスルートは、前半はそれなりに見応えのあるポイントがあったが、後半は芦別の寂しさが気になるルートだったかな?と振り返っている。また、渡った橋が鉄道の陸橋も含めて6つの多くの橋を渡ったのも印象的なルートだった。
「タタンラーメン」…、もっと全道的に広がってもいいのではと思うのだが、やはりパンチに欠けるところがいま一つ人気を博しない原因なのだろうか?
《フットバスウォーク実施日 ’14/09/28 距離 約9.8Km》