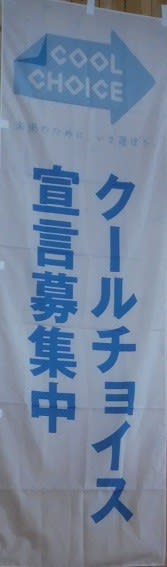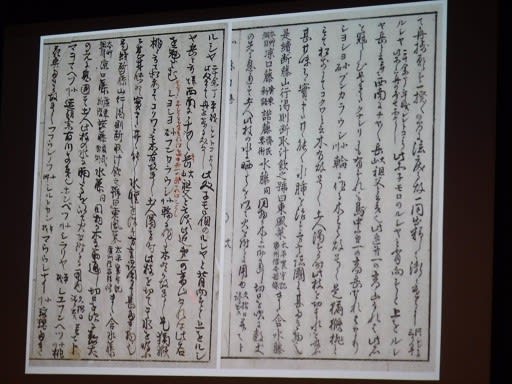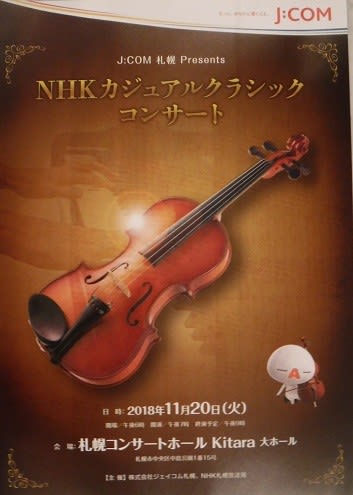「あの人と幸せでしょうか、お母さん。父さんは無口を通し逝きました」…。この意味深な短い手紙がモチーフとなって映画が製作されたという。子どもが母に書いた手紙であるが、そこには深く抜きがたい傷が横たわっていた…。

11月27日(火)午後、道民カレッジ事務局が主催する「懐かしフィルム上映会」があった。先月に続いて2回目の開催だったが、今回取り上げられたフィルムが『日本一短い「母」への手紙』だった。
ご存知の方も多いと思われるが、戦国時代に本多重次という武将が戦場から妻にあてて「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」という極めて簡にして要を得る手紙を送ったことで知られている。その本多重次の故郷である福井県丸岡町が町興しの一環として『日本一短い「母」への手紙』を募集し、優秀作を表彰していることが一時話題になった。
その応募作の中から優秀賞に選ばれた作品の中に「あの人と幸せでしょうか、お母さん。父さんは無口を通し逝きました」という作品があり、その作品がヒントとなり映画ができたということのようだ。
映画は父の前原道夫(小林稔侍)と姉の真紀(裕木奈江)と弟の宏(原田龍二)の三人が暮らす家庭が舞台である。二人の姉弟の母多恵(十朱幸代)は18年前に家族を捨てて別の男のもとへ走ったのだった。二人の父は心臓発作で急死してしまう。その死に対して真紀が母に対する心情を表したのが先の短い文章だった。

※ 映画はカラーだったが、ウェブ上に掲載の写真はなぜか白黒だった。
その後に続くストーリーについては省略させていただくが、家族を捨てた母親に対して、弟はこだわりを持っていないのに対して、姉の方は激しく母を憎む、これはある意味で男と女の違いなのだろうかと思ってしまった。
この映画ではキャスティングがはまっていたのではと思えた。寡黙で実直そうな父親役の小林稔侍、いかにも派手好みな母親役の十朱幸代、一途に思い詰めてしまうような真紀役の裕木奈江、一方いかにも軽そうで深く考えない宏役の原田龍二と役者が揃ったように思えた。
特に十朱幸代は調べてみると、映画制作時(1995年)は53才なのだが、その美貌には少しも衰えが見られず、銀座の美人ママ役がぴたりとはまっていた。

映画は最後に真紀が「ずっとおかあさんがほしかった」と抱き合うのだが、もし私は姉弟の立場だったとしたら、どう考えるだろうか?両親の離別の原因が原因だけに、私は真紀の思いに共感を抱くのだが…。