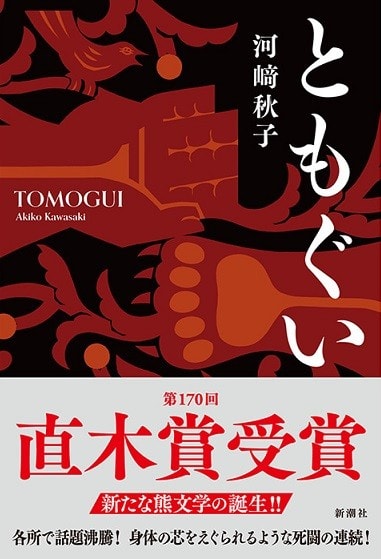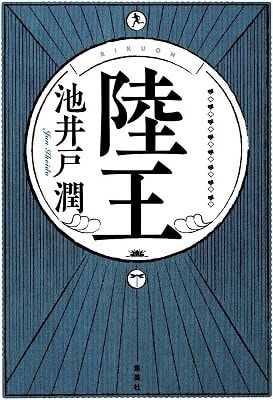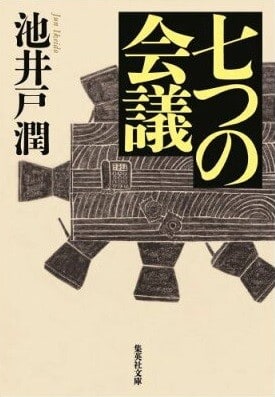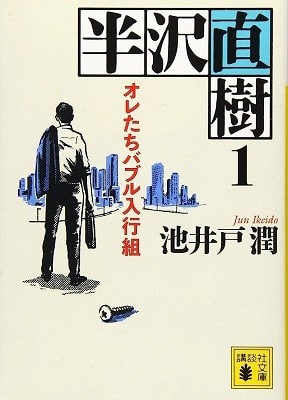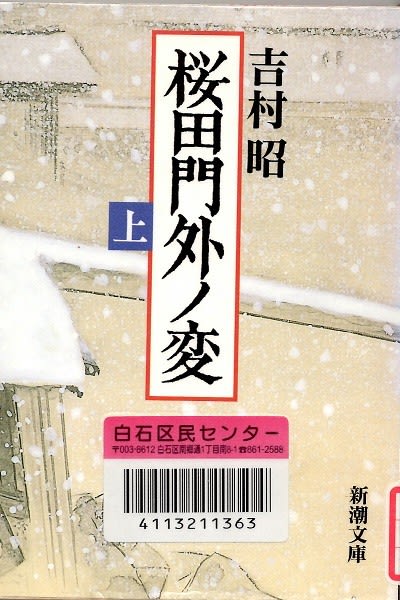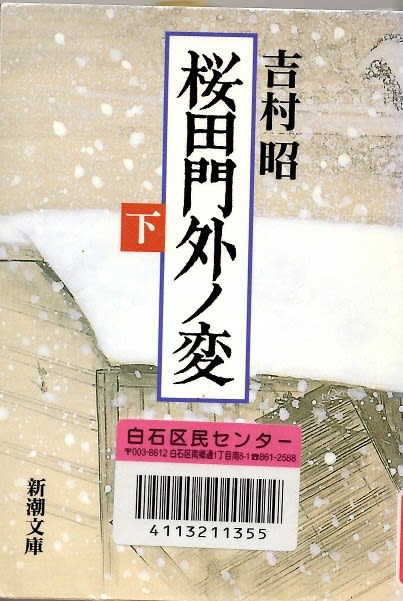思い返せば昨年の夏だったろうか?知人との雑談中に「今、伊達政宗を読んでいて、とても面白いのですよ」と話したところ、友人は「じゃ、次は徳川家康ですね」と話されていたのを記憶していて、あまり深く考えもせずに「徳川家康」を手に取りました。

これが実に面白いのです。徳川家康が幼少の頃、竹千代と呼ばれた人質時代から始まって、家康の成長を追い続ける大河のような物語に私は直ぐに夢中になりました。
「徳川家康」のソフトカバー版「講談社文庫」全26巻のうち、現在は第18巻目「関ケ原の巻」まで読み進んでいます。

山岡荘八の筆致は実に巧みです。あたかも徳川家康の生き様を寄り添うように観察していたかのようなストーリー展開なのです。(それは「伊達政宗」のときも同様でした)史実を忠実に追ってはいるものの、相当に山岡荘八のフィクションが含まれているものと想像されるのですが、家康をはじめ、登場人物の事績や性格などを相当深く研究されたうえで書き進めているために、読み手にするとそこにリアルな世界が広がる思いなのです。

第18巻は、豊臣秀吉が没して、豊臣秀吉に信頼され権勢を振るっていた石田三成が秀吉の嫡男である豊臣秀頼を立てて密かに後継を狙い、家康の排除を企図するも「関ケ原の戦い」に入っていく様が描かれる場面です。
いわば長い長い戦国時代の最終章ともいえる場面です。はたしてどのような経緯を辿り戦いに突き進むのか、ワクワクドキドキの場面が予想されます。

私はこの「徳川家康」を全て札幌市の図書館から借りる形で読み進めています。図書館の貸出期間は2週間ですが、私は文庫版「徳川家康」を一度に3冊ずつ借りています。しかし遅読の私は2週間で3冊は読了できません。(私が読むのがほとんど就寝時ということもあるのですが…)そこで一度だけ延長することが認められているシステムを利用して、約1ヵ月かけて3冊を読了するペースです。

近年、図書館で本を借り出すのはPCで予約できるため、とても便利になりました。借りた本が読了する3~4日前に借りたい本を予約すると、借りた本を返本する段階で予約した本が用意されていて、返本と借り出しが一度に行えるのでとても便利です。
このようにして私は「徳川家康」を読み進めています。
記憶では昨年8月頃から読み始めたと思いますが、今のペースでいくと全26巻を読了するのは4月頃になりそうです。それまで大いに「徳川家康」を楽しみたいと思っています。