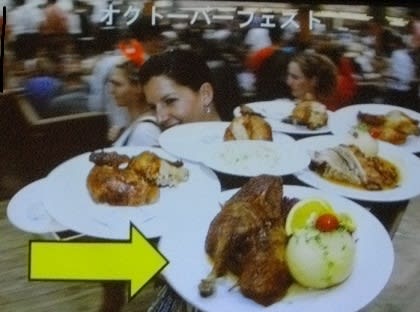毎日執筆しなければならないというプレッシャー、読者の厳しい批判に耐えられる神経、などなど…。北海道新聞の1面コラム「卓上四季」を担当した経験のある二人のベテラン記者が対談形式で執筆の裏側を語った。
北海道新聞(通称:道新)の記者と読者の交流を目的とした「道新ニュース・カフェ」が開催された。カフェは2部に分かれていて、道新コラム「卓上四季」の担当記者の話と、北方領土問題を担当した記者の話を聞くという2部立てだった。私は両方ともに希望したのだが、前半の「卓上四季」のみ聴講可能な入場券が届いた。
「卓上四季」を語ったのは、高橋純二編集委員と菅原淳経済部長の二人だった。
二人が「卓上四季」を担当したのは、高橋氏が2004年2月から2006年6月まで、菅原氏が2006年7月から2010年6月までだそうだ。菅原氏が高橋氏から受け継いだということもあり、二人はリラックスした形で対談は進んだ。
新聞の1面コラムはその新聞の顔である。執筆担当者は文章が書けて、その上その新聞社の知性を代表するような人でなければならない。人選は時の編集局長に委ねられているということだが、記者としてさまざまな経験を積み重ね、ベテランという域に達した人の中から、新聞社の知性を代表する人ということで二人はメガネに適った人だったということだろう。
コラム担当になると、もっぱらコラムの執筆に専念するという。毎日毎日あの580字という短い文章の中に時の話題や関心事、あるいは人々の関心を喚起させるなど、多岐に渡る内容を平易な言葉で分かり易く表現しなくてはならないのだから大変である。
二人は毎日の文章を捻り出すために、それぞれの方法でアンテナを張り、緊張しながら毎日を過ごしていたということだ。それだけにその日の原稿を書き終えると、開放感に包まれ居酒屋へ直行することも度々だったとか…。
二人と比ぶべくもないが、文章を捻り出すということにおいては、私も毎日このブログを投稿するためにそれなりに苦労をしているので、二人の気持ちが少しは分かる気がすると言ったら「レベルが違うよ」と失笑されそうだ。
菅原氏がコラムニストの辛さを上手く表現していた。
コラムニストとして朝起きると怖いことが三つあると…。一つは、「今日、自分は原稿が書けるだろうか」という怖さ。二つ目は、「今日はいったい何を書いたら良いんだろうか」という怖さ。三つ目は、「他紙のコラムと比べて自分のコラムはどうなのか」という朝、他紙を読む怖さ。と語っていた。どれも分かる気がする。(と言ったら驕りと取られるだろうか?)

※ 残念なことにカメラはNGだった。そこで二人ともウェブ上から拝借した。写真は千歳支局長時代の菅原氏である。
また、高橋氏はコラムニストとしての心構えを次のように話した。
コラムニスとは常に野党であるべきだ、とその心構えを話した。(批判的精神を忘れるな、ということだろう。註 丸尾)
そして、自分は何も知らないんだというところからスタートし、読者の問題意識を喚起するように努めたということだ。
最後に、読者からの反響、お叱りが常に緊張感を与えてくれた、と…。

※ この方はテレビで見たことがある人もいるかもしれない。UHBテレビなどでコメンテーターをしている高橋氏である。
その他、コラムニストのあれこれをさまざまな角度から語ってくれたが、二人とも異口同音に「苦しかったが、楽しかった」と語ってくれた。その最大の理由は、「書きたいと思ったことを自由に書かせていただいたから…」と話したのが印象に残った。
自由にとはいえ、新聞の1面を飾るのだからたくさんの制約があるだろうことは容易に想像できるが、その中でも最大限の自由を与えられていたということだろう。
ニュース・カフェには先輩のF氏も参加されていた。
ニュース・カフェが終わった後、F氏とカフェで歓談した。二人で、「コラムニストの肉声を聴いたことで、これからは今までよりも興味深く新聞のコラムを読めそうですね」と話し合ったのだった…。
北海道新聞(通称:道新)の記者と読者の交流を目的とした「道新ニュース・カフェ」が開催された。カフェは2部に分かれていて、道新コラム「卓上四季」の担当記者の話と、北方領土問題を担当した記者の話を聞くという2部立てだった。私は両方ともに希望したのだが、前半の「卓上四季」のみ聴講可能な入場券が届いた。
「卓上四季」を語ったのは、高橋純二編集委員と菅原淳経済部長の二人だった。
二人が「卓上四季」を担当したのは、高橋氏が2004年2月から2006年6月まで、菅原氏が2006年7月から2010年6月までだそうだ。菅原氏が高橋氏から受け継いだということもあり、二人はリラックスした形で対談は進んだ。
新聞の1面コラムはその新聞の顔である。執筆担当者は文章が書けて、その上その新聞社の知性を代表するような人でなければならない。人選は時の編集局長に委ねられているということだが、記者としてさまざまな経験を積み重ね、ベテランという域に達した人の中から、新聞社の知性を代表する人ということで二人はメガネに適った人だったということだろう。
コラム担当になると、もっぱらコラムの執筆に専念するという。毎日毎日あの580字という短い文章の中に時の話題や関心事、あるいは人々の関心を喚起させるなど、多岐に渡る内容を平易な言葉で分かり易く表現しなくてはならないのだから大変である。
二人は毎日の文章を捻り出すために、それぞれの方法でアンテナを張り、緊張しながら毎日を過ごしていたということだ。それだけにその日の原稿を書き終えると、開放感に包まれ居酒屋へ直行することも度々だったとか…。
二人と比ぶべくもないが、文章を捻り出すということにおいては、私も毎日このブログを投稿するためにそれなりに苦労をしているので、二人の気持ちが少しは分かる気がすると言ったら「レベルが違うよ」と失笑されそうだ。
菅原氏がコラムニストの辛さを上手く表現していた。
コラムニストとして朝起きると怖いことが三つあると…。一つは、「今日、自分は原稿が書けるだろうか」という怖さ。二つ目は、「今日はいったい何を書いたら良いんだろうか」という怖さ。三つ目は、「他紙のコラムと比べて自分のコラムはどうなのか」という朝、他紙を読む怖さ。と語っていた。どれも分かる気がする。(と言ったら驕りと取られるだろうか?)

※ 残念なことにカメラはNGだった。そこで二人ともウェブ上から拝借した。写真は千歳支局長時代の菅原氏である。
また、高橋氏はコラムニストとしての心構えを次のように話した。
コラムニスとは常に野党であるべきだ、とその心構えを話した。(批判的精神を忘れるな、ということだろう。註 丸尾)
そして、自分は何も知らないんだというところからスタートし、読者の問題意識を喚起するように努めたということだ。
最後に、読者からの反響、お叱りが常に緊張感を与えてくれた、と…。

※ この方はテレビで見たことがある人もいるかもしれない。UHBテレビなどでコメンテーターをしている高橋氏である。
その他、コラムニストのあれこれをさまざまな角度から語ってくれたが、二人とも異口同音に「苦しかったが、楽しかった」と語ってくれた。その最大の理由は、「書きたいと思ったことを自由に書かせていただいたから…」と話したのが印象に残った。
自由にとはいえ、新聞の1面を飾るのだからたくさんの制約があるだろうことは容易に想像できるが、その中でも最大限の自由を与えられていたということだろう。
ニュース・カフェには先輩のF氏も参加されていた。
ニュース・カフェが終わった後、F氏とカフェで歓談した。二人で、「コラムニストの肉声を聴いたことで、これからは今までよりも興味深く新聞のコラムを読めそうですね」と話し合ったのだった…。