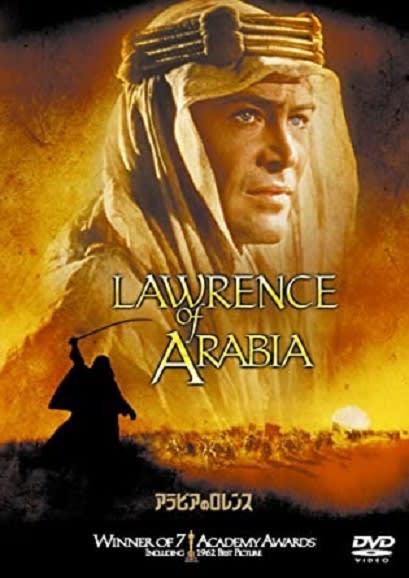札幌市の厚別区の総合公園である「厚別山本公園」を訪れた。丘陵の上に造成された広大な公園だったが、現在はまだ完成前であり、公園の一部が開放されているようだった。

※ 厚別山本公園の平面図です。(市のHPから拝借)
札幌市には各区ごとに総合公園が一か所ずつ配置されている。(中央区だけは「中島公園」と「円山公園」と二か所が総合公園である)札幌市は現在10区に分かれているので総合公園は11ヵ所になる。私はこれまで「厚別山本公園」以外の総合公園は訪れた経験があったので、本日は以前から一度行ってみたいと思っていた「厚別山本公園」を訪れてみた。

※ 公園入口に設置された立派な公園名を表示した門(?)です。

※ その門の横に工事期間などが表示されていました。
「厚別山本公園」はゴミ埋め立て処分場跡に造られている公園で、2014年に造成工事に着工し、2024年完成予定の公園だという。位置的には札幌市と江別市の境界線上にあり、我が家からは12km、車で40分かかって到達した。
到達したところは公園のメイン駐車場ではなく、パークゴルフ場に面したサブ駐車場だった。(メイン駐車場の方は工事中で未完成)それでも乗用車は170台も駐車できる広い駐車場である。

※ 私が駐車したサブ駐車場です。
公園は南北に長く各施設などが連なっている形で、北端から「ビオトープ」、「パークゴルフ場(36ホール)」、「展望広場」、「遊びの広場」、「多目的(芝生)広場」と縦に連なって造られていた。以上のところはすでにオープンし、市民は自由に楽しめているようだ。(但し、パークゴルフ場は現在閉鎖中)

※ 公園内には南北に伸びる真っすぐの遊歩道が貫いていました。

※ 北側から順に、ビオトープです。

※ 36ホールのパークゴルフ場です。

※ 展望広場です。前方の最も高い陸橋(?)の上から望んだ景色を後掲します。

※ 遊びの広場の遊具です。遊具の色に特徴があります。

※ 同じ遊びの広場にはこのような小さな家がたくさん散在していました。

※ 多目的(芝生)広場です。ここからさらに南側に「森の遊び場」、「緑の育ち場」が
造成されています。
一方、現在工事中のところは、さらに 南側の「森の遊び場」、「緑の育ち場」といった木が生い茂り、その林を活かした憩いの場と、「中央エントランス広場」と「メイン駐車場(230台駐車可能)」などが工事中だった。

※ 工事中だった「中央エントランス広場」と「メイン駐車場」です。
公園の特徴の一つはけっこう大きな水面を利用した「ビオトープ」ではないかと思われる。札幌市内の全ての公園を熟知しているわけではないが「ビオトープ」を有する公園は数えるほどしかないはずだ。その点では面白い公園になるように思われる。

また、現在工事中の「森の遊び場」、「緑の育ち場」というエリアが具体的にどのような形で姿を現すのかも興味深いところである。
「総合公園」は、「都市公園の一種で、都市基幹公園に分類され、都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園」であるとされている。「厚別山本公園」完成の暁には、厚別区民だけではなく、広く札幌市民にも愛され、利用される公園になるように思われる。

※ 展望広場から札幌中心部を望みましたが、森の影に隠れてしまいました。

※ 反対側には 江別市大麻地区、その向こうに北海道百年記念塔が望まれます。
私は昨年から札幌市内にあるパンクゴルフ場全コース制覇に取り組んでいる。現在はパークゴルフ場そのものが閉鎖していて今年は一度もプレイできていないが、閉鎖解除の暁にはこの「厚別山本公園」のパークゴルフ場にも訪れなければならないと思っている。