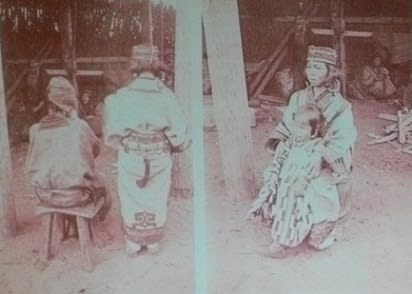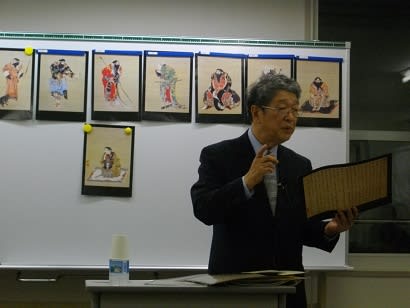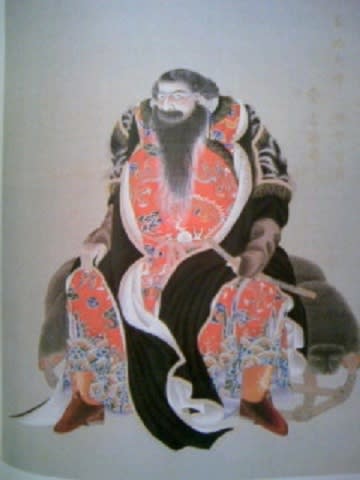三日前に投稿した「街歩き研究家」の和田哲氏から聴いたお話はぜひ紹介したいと思い、続編を綴ることにした。◆定山渓鉄道、◆中島スポーツセンター、◆アンパン道路、◆悲しみの盤渓、の後編をお読みいただけたらと思います。
和田氏から伺った “札幌のトリビア” は、そのいずれもが興味深かった。いずれもが私の記憶に残したい思いもあって、その続編を綴ってみることにした。
まずは「定山渓鉄道」である。定山渓鉄道は、大正年代に入って定山渓温泉への観光客の輸送、木材の輸送、鉱石と石材の輸送を主な目的として計画され、1918(大正7)年10月に東札幌駅 ⇔ 定山渓駅間(27.2km)で開業し、1969(昭和44)年11月モータリゼーションの普及などから経営不振となり廃線にいたった鉄道である。

※ 定山渓鉄道の遺構の一つ「旧石切山駅」です。現在は地域の振興会館として活用されています。
定山渓鉄道に関して興味深いお話を伺った。それは定山渓鉄道が経営不振に陥った際に、当時「買収王」とも称され辣腕を振るっていた五島慶太氏率いる東急電鉄が株を買収し、実質的に経営者となった際に、五島慶太は国鉄の札幌 ⇔ 江別間の線路が大きく湾曲して遠回りしていたことから、札幌 ⇔ 江別間を直線で結ぶ「札幌急行鉄道」を計画したという。そしてその線路を北海道炭鑛汽船が経営する「夕張鉄道線」との連絡も企図していたという。しかし、五島慶太が志半ばで逝去したことから、この計画は実現しなかった。もし、計画が実現していたら、札幌から江別にかけての沿線の風景は今とはかなり違ったものになっていたのではないかと思うと興味深い。
続いて「中島スポーツセンター(正式名:北海道立札幌中島体育センター)」である。中島スポーツセンターは、1954(昭和29)年の第9回国民体育大会の大会々場として建設され、建設当時は国内でも有数の規模を誇るスポーツセンターだったという。アリーナを客席とすると6,000人は優に収容できる規模だったそうだ。そこでは大相撲札幌場所やプロレス、サーカス、コンサートなどあらゆる催しが開催されたそうだが、特にプロレス興行が盛んに行われたことで有名だったという。

※ 当時、威容を誇った初代の中島スポーツセンターです。
現在は、豊平公園に「北海道立総合体育館(通称:きたえ~る)」が開設され、中島スポーツセンターは規模を縮小して建て替えられ、施設は札幌市に移管され、純粋なスポーツ施設として中島公園内に建っている。
三つ目の話題は「アンパン道路」である。このお話には、札幌市の街の変遷が関わっている。1910(明治43)年、当時の豊平町の一部が札幌区に編入されたことにより、そこににあった役場が編入されなかった月寒に移転されることになったそうだ。すると豊平町の一部だった平岸から新しい役場へ行く道路 がなく、平岸地区の住民が困難を被ったそうだ。その不便さを解消するために、平岸と月寒を結ぶ道路の建設が叫ばれ、陸軍第7師団歩兵第25連隊に道路建設の協力を要請、地元民も参加して全長約2.6キロメートルの道路建設工事が行われて4カ月で完成したという。町は道路工事に従事した兵士に間食としてアンパンを配布したことから、この道路は「アンパン道路」という通称で後世親しまれることとなったそうだ。

※ 札幌市民の懐かしの味「月寒アンパン」です。
そのアンパンは私も食したことがあるが、普通市販されているアンパンとは違い月餅に近い食感でしっとりとしていて独特の風味を感じるアンパンである。また、私はここの「アンパン道路」を実際に歩いてみたこともあるが、短い距離ながら高低差がけっこうあって、昔の人たちが道路建設を躊躇されたのも分かるような気がした。
最後は「悲しみの盤渓」のお話である。和田氏から伺ったお話は感動的なものだった。どのようにまとめたら良いか呻吟したが、結局ウェブ上にその詳細が掲載されていたので、少し長くなるが、それを拝借することとしたい。
1912年(明治45年)、琴似尋常高等小学校附属盤之沢特別教授場として創立する。
1922年(大正11年)には独立して盤渓尋常小学校となる。その背景には、札幌の発展とともに山鼻や円山の住宅化が進行したため、押し出されるような形になった畑地が盤渓へと移ってきて地域が振興したという経緯があった。しかし学校用地の確保には、農民にとっての魂とも言うべき土地を手放す必要がある。住民による会合は十数回に及んだが決着を見ず、ついには殴り合いにまで発展し、我満六太郎が用地を寄付することでようやく事態は収束した。
この時、学校の名が当時の地名の「盤之沢」から漢文調の「盤渓」に改められた。この命名者は1917年(大正6年)から盤之沢特別教授場の教師を務め、小学校独立に尽力し、後に盤渓尋常小学校の初代校長を任命された結城三郎であった。この「盤渓」の名は地域に浸透し、小学校に続き「盤之沢神社」についても社殿の改築を機に「盤渓神社」に改め、1943年(昭和18年)には正式な地名も「盤之沢」から「盤渓」に改められた。
1950年(昭和30年)、札幌市立盤渓小学校となる。1977年(昭和52年)には札幌市特認学校の指定を受けた。
初代校長・結城三郎
盤渓小学校が独立開校した1922年(大正11年)当時、盤渓の集落は琴似村役場から山道を8キロメートルもたどらねばならない僻地であり、教員を確保しても早い者は2か月で逃げ出す有様だった。そのような中、1917年(大正6年)、開校から7人目の教師として着任し6年にわたり当地での教育に携わり人格者として生徒や住民からも慕われた結城三郎が初代校長の内示を受けたことは、村人たちにとっても喜ばしいことであった。
同年12月21日、開校式を3日後に控え、羽織袴の正装をまとった結城は、琴似村役場にて辞令と教育勅語を受け取った。役場を出たのは午後2時で、日没は午後4時であるから、明るいうちに盤渓に帰り着くことは無理である。途中、教育勅語を取り扱うための白手袋とふくさを立ち寄った円山の定松商店で宿泊を勧められるが、結城は「畏れ多い『お勅語』を民家にはおけない」という理由で断り、提灯を借りて先を目指した。
気温は氷点下7度、風速7メートルという悪条件の中、なんとか幌見峠を越えた結城が、峠下の久保田家で2本目のロウソクに点火してもらったのは午後10時半ごろのことであった。だが、そこから1キロメートルほど進んだあたりで力尽き、翌朝に雪の下で遺体となって発見された。小学校まであと僅か50mほどの場所であった。享年42。教育勅語はその胸に抱かれて無事だった。
結城は正式に校長として着任できなかったため、1960年(昭和35年)に開かれた開校50年記念式典の際も校長として取り上げられなかった。恩師の扱いに驚いた教え子たちは「結城先生復活」を呼びかけ、趣意書を作成し寄付を募り、盤渓小学校グラウンドの東端、山の斜面とぶつかるあたりに、高さ1.5メートルの「あゝ結城先生」の碑を建立した。1964年(昭和39年)5月17日、碑の除幕式が行われ、教え子達は碑の前で先生に教わった「金剛石の歌」を歌い偲んだ。その後、結城は札幌市教育委員会から正式に初代校長として認められた。

※ 現在の盤渓小学校の庭の片隅に佇む「あゝ結城先生」像です。
ちょーっと長くなってしまったが、とても感動的なお話をぜひ紹介したいと思い長くなってしまったことをお許しください。
いや~、地域の歴史を掘り起こすことって非常に興味深いことですね。改めてその子とを教えられた和田氏の講演でした。