「藍」とは、あの「青は藍より出でて、藍より青し」の藍である。旬の話題でいえば、現在のNKH大河ドラマ「青天を衝け」の主人公の渋沢栄一の生家が藍作農家である。その「藍」が北海道で盛んに生産されていた一時期があったというお話を伺った。
私が毎年楽しみにしている道民カレッジの「ほっかいどう学 かでる講座」は、今年は全てオンライン講座となってしまった。年間10回開催される講座の第2回講座が先日配信されので視聴(受講)した。第2回の講座の内容は「先人たちの息吹を感じる歴史的建造物とその生業」と題して北海道開拓の村館長である中島宏一氏が講師を務められた。
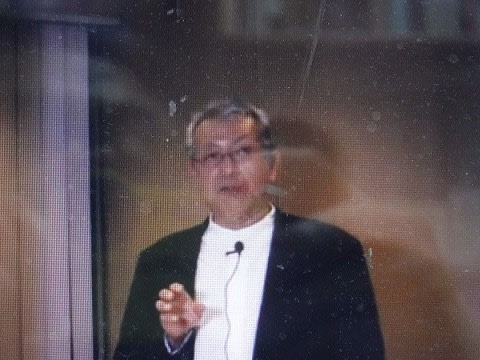
※ 講義中の中島宏一館長です。PC画面越しなので不鮮明です。
中島氏は「北海道開拓の村」が北海道内に現存していた歴史的建造物を移築、または再現して保存している建物が52棟展示されており、それらは漁村群、農村群、山村群、市街地群の4つエリアから成っていることを紹介された。ここまでは「北海道開拓の村」のほんのさわりの紹介であるが、中島氏のお話はここからがユニークだった。というのは…。
中島氏は、52棟ある歴史的建造物の中から旭川市から移築した「旧近藤染舗」をピックアップし、北海道開拓の一断面を紹介するという話の構成を取ったのだ。

※ 北海道開拓の村に移築・再現された「旧近藤染舗」の建物です。
「旧近藤染舗」は徳島県出身の近藤仙蔵氏が1898(明治30)年に旭川で創業したという。近藤氏は染の材料として藍を使用し、半纏、帆前掛け、幟などの製造を手掛けたという。「近藤染舗」は子孫によって受け継がれ、現在も旭川の地において「株式会社近藤染工場」として大漁旗の製造を行っているそうだ。
さて、「旧近藤染舗」が藍染の原料である藍葉をどのように入手したかというと、それはやはり当時藍作の本場の一つだった徳島県から移住した人たちによってだったという。静内、二木、さらには篠路町などに徳島県人が移り住み、藍を作付け、生産していたという。
その中でも特に郷里徳島で「興産社」を設立し、篠路町に入植した阿部興人氏、滝本五郎氏たちは多くの徳島県人たちと藍作を始めたそうだ。その地は後に「あいの里」と命名されるほど一時は藍作が盛んとなったという。
なぜ徳島県人が北海道に多く入植したかというと、藍は育てるのに多くの肥料を必要とする多肥作物だそうだ。そこで求められたのが当時北海道で盛んに生産されたニシン粕だったそうだ。ニシン粕は北前船によって徳島まで運ばれていたのだが運賃も重なり高価な肥料であったようだ。明治20年代の日本の不況により各地の農家も疲弊する中、徳島の人たちはニシン粕を現地調達できるということも北海道入植に一因だったそうだ。
1889(明治29)年には札幌桑園に藍製造場ができ、札幌区内をはじめ札幌郡、空知、石狩、小樽、余市、夕張、千歳、浜益などから葉藍を買い上げて藍染の原料となる “すくも” を製造していたという。
しかし、時代は化学染料が主流を占めるようになり、藍染の需要が減少することにより藍作はすたれ、他の農作物の生産へと移っていったという。
現在、北海道で藍の作付けを行っているのは伊達市の篠原氏一軒だけだという。篠原氏の作付けは一軒の農家としては日本一の作付面積で、都道府県別では徳島県に次いで全国第2位の生産量を誇り、藍染教室や伝統文化保存のために原料を提供しているそうだ。

※ 「北海道開拓の村」の全景です。
中島氏のお話は概ね以上のようなお話だったが、話が物語性に富み、興味深く拝聴することができた。中島氏から他の歴史的建造物に関しても今回のような形でお話を伺いたいと思った。









